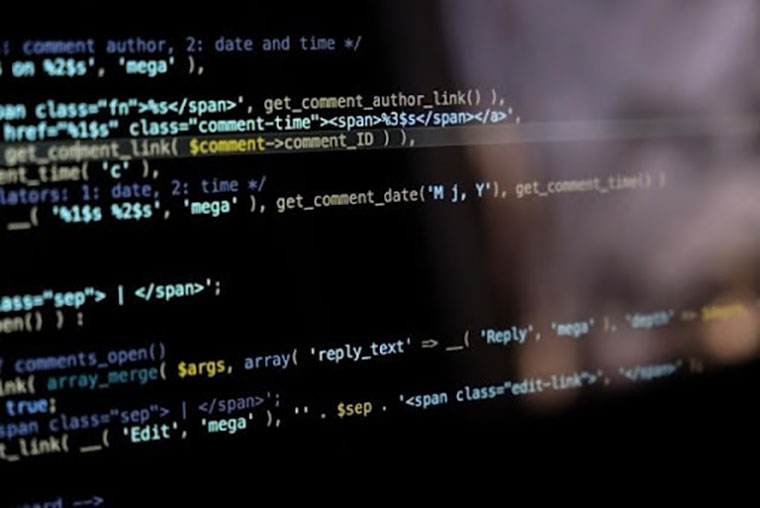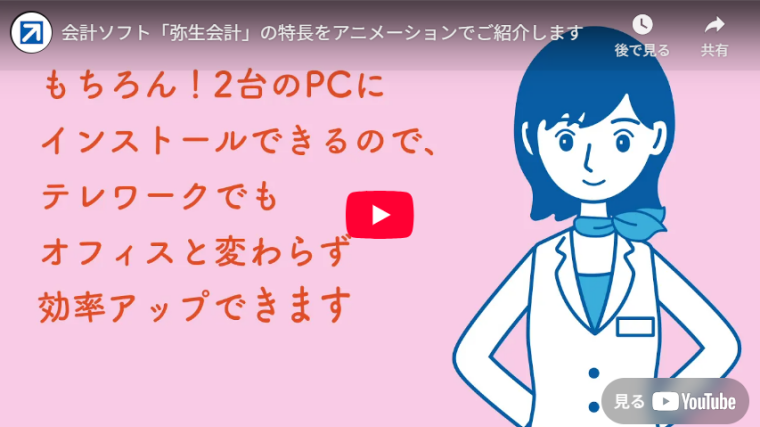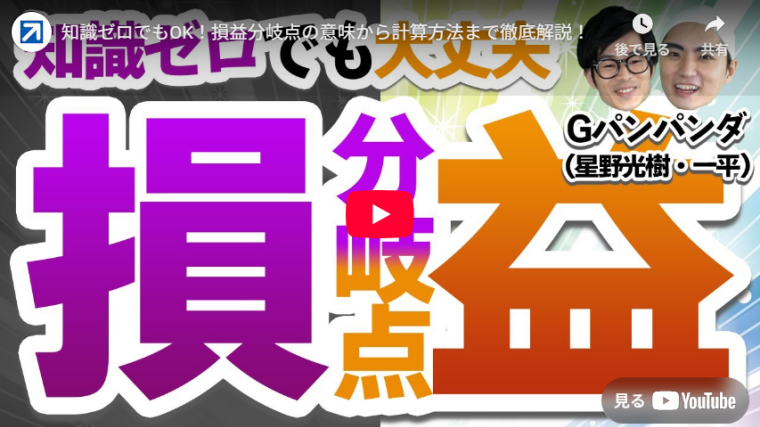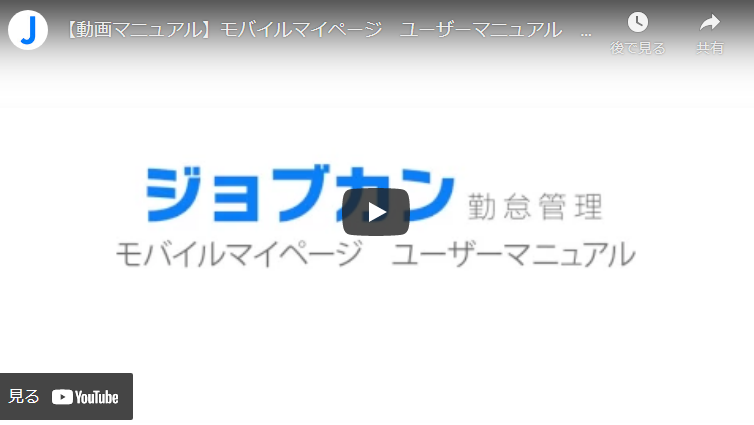ソフトウェア系企業が動画を活用するメリット
高度な機能を持つソフトウェアほど、その魅力や使い方を言葉だけで伝えるのが難しくなるため、動画の活用が有効な手段となります。ここでは、ソフトウェア系企業が動画を活用するメリットを解説します。
複雑な内容を視覚的にわかりやすく伝えられる
ソフトウェアの操作や機能は、文章や静止画だけでは理解しづらいケースが多々あります。
特にクラウドサービスやSaaS製品のように、UI/UXが鍵を握る商材は、実際の操作画面や流れを動画で見せることが、理解促進に最も効果的です。
アニメーションや画面収録を活用すれば、専門用語が多く含まれる内容でも、視聴者にとって直感的に理解しやすくなります。結果として、問い合わせの削減や導入率の向上にもつながります。
商品理解と導入意欲を高める
動画を活用すれば、サービスの特長やユースケースを短時間で明確に伝えることができます。
例えば、「○○ソフトは勤怠管理がスムーズにできる」と伝えるよりも、「3ステップで打刻完了!管理画面でリアルタイムに確認可能」というように、動きとストーリーを伴って伝えるほうが、視聴者に強い印象を残せます。
また、事例動画やインタビュー動画を用いることで、「他社でもうまく活用されている」という社会的証明が働き、導入の心理的ハードルを下げることも可能です。
マニュアルやFAQの代替として活用できる
多機能なソフトウェアほど、操作方法の説明が煩雑になりがちです。従来はPDFマニュアルやヘルプページが主流でしたが、近年では動画マニュアルを活用する企業が増加しています。
動画であれば「どのボタンを押すか」「どんな画面遷移があるか」が一目でわかり、学習コストを大幅に削減できます。
特に、新規導入時やアップデートのたびに発生するユーザーサポート負荷を軽減でき、カスタマーサクセスの観点でも有効です。さらにツールを活用すれば、社内で簡単に動画マニュアルを作成・配信することも可能です。
情報発信の幅が広がる
ソフトウェア系企業では、新機能のリリースやアップデート情報、セミナーの告知、活用ノウハウなど、継続的に情報を発信する必要があります。
動画コンテンツであれば、Webサイト・YouTube・SNSなど複数のチャネルで展開できるため、接触回数を増やし、ブランドの認知拡大に貢献します。
例えば、製品紹介のダイジェスト動画を投稿し、詳細はWebサイトで紹介するといったクロスメディア戦略にも有効です。視覚と音声で訴求できる動画は、スクロールに慣れたユーザーの目にも留まりやすく、情報発信の主軸となり得ます。
ソフトウェア系企業での主な動画活用方法
ソフトウェア系の企業における動画の活用方法としては、主に3つ挙げられます。それぞれどのような方法なのでしょうか。
商品・サービス紹介動画
1つ目は、商品・サービスの紹介動画です。自社の商品やサービスの機能性や特徴などを動画で紹介します。
特にソフトウェア系の商品やサービスは専門職向けのものがあるため、動画でのPRが重要になります。なお、この方法は多くの企業で取り入れられており、インターネット上だけではなく、テレビや野外ビジョンで動画が流れていることもあります。
商品・サービス紹介動画の内容はさまざまです。アニメーションを用いて紹介している動画もあれば、有名人を起用して紹介する動画もあります。前者の場合はわかりやすく商品を紹介でき、後者の場合は話題を呼びやすくなります。それぞれ特徴が異なるため、動画の内容を考える際の参考にしてみましょう。
商品・サービスのマニュアル動画
2つ目は、商品・サービスのマニュアル動画です。マニュアルと聞くと文章のイメージがあるかもしれませんが、近年では動画マニュアルを用いる企業も増えています。
これらはソフトウェア系の企業だけではなく、幅広い業界で用いられています。実物がある場合には、取扱説明書の代わりに動画マニュアルのQRコードを同封することもあります。
ソフトウェア系の場合は、アニメーションが用いられることが多いです。アニメーションは目に見えない部分も再現できる上にわかりやすくなるため、複雑な操作方法も動画にすることで伝えやすくなります。その上、インターネットに公開すれば操作性に魅力を持って購入してもらえる可能性も高まります。
求人動画
3つ目は求人動画であり、ソフトウェア系も含めた幅広い業界で用いられています。特にソフトウェア系は需要が高い業界だからこそ、積極的に動画で人材を募集することで優秀な人材が集まりやすくなります。
求人動画の場合は、実写動画がおすすめです。実写動画はありのままの姿を伝えられるため、職場の雰囲気や実際に働いている人の想いを伝える上で役立ちます。また、新型コロナウイルスの影響で企業説明を動画で行うケースも増えています。
ソフトウェア系企業での動画活用事例
ここからは、ソフトウェア系企業での動画活用事例をいくつかピックアップして紹介します。自分が作りたい動画の内容や予算などを考慮しながらチェックしてみてください。
株式会社freeeの場合
株式会社freeeでは、自社の会計アプリ「freee」に関するプロモーション動画を公開。スマホの画面を用いて機能性や特徴を紹介しており、スマホで利用する場合のイメージがしやすくなっています。

また、積極的に文字を多用していることも特徴です。文字が多いと読みにくいと思うかもしれませんが、この動画はサイズやフォントにこだわっているおかげで読みにくいとは思わないでしょう。
その上、文字だけでもどのような動画なのかわかるため、電車の中といった音が出しにくい空間でも内容が把握できるようになっています。
弥生株式会社の場合
株式会社freeeと同じく会計ソフトを開発・運用している弥生株式会社でも、ソフトに関する情報を動画で紹介。アニメーションでわかりやすくしており、会計ソフトが初めての方でもどのような機能性なのか把握しやすくなっています。
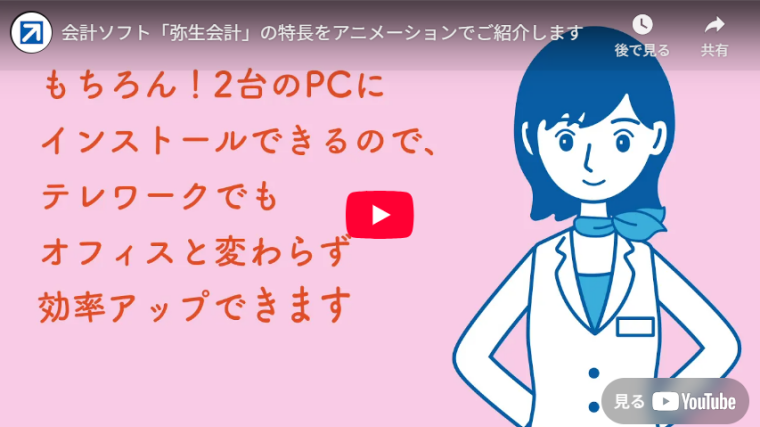
弥生株式会社の場合は会計ソフトを取り扱うこともあり、会計に関する情報も発信しています。お笑いコンビのGパンパンダを起用した動画となっており、ストーリー形式で会計に関することを学べます。
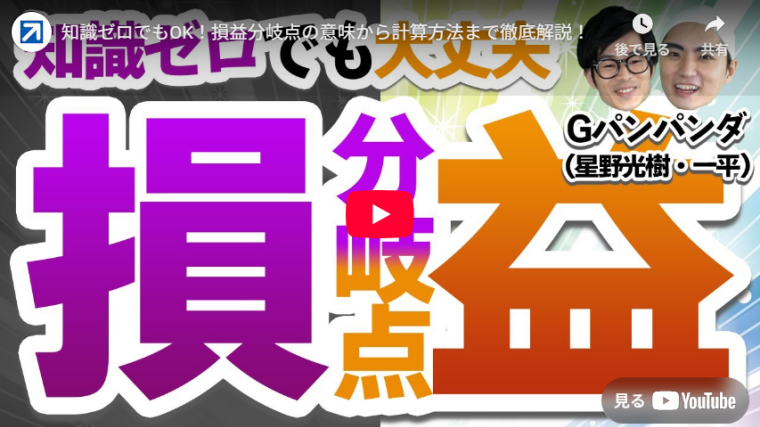
株式会社DONUTSの場合
株式会社DONUTSでは、自社が運用している「ジョブカン」に関するマニュアル動画をインターネット上で公開しています。ナレーションや実際の画面などを用いて紹介しており、動画を真似することで簡単に操作できます。
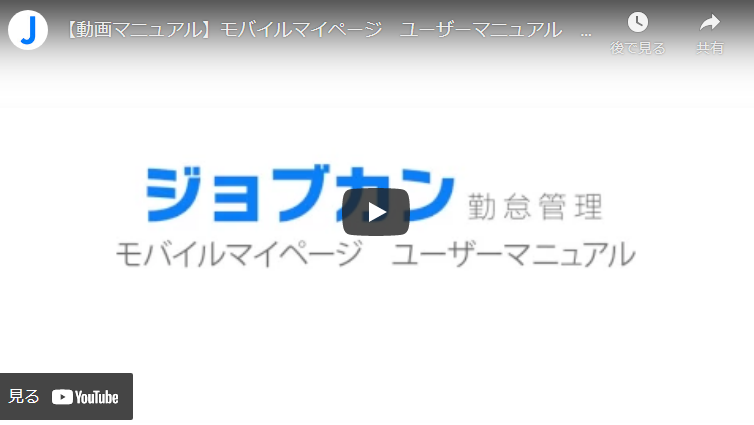
ソフトウェア系企業が動画を制作・活用する際のポイント
ソフトウェア系の企業が動画を制作および活用するためには、いくつかのポイントがあります。効果的に活用するためにも、こちらの項目まで読んでおきましょう。
ターゲットに合わせた動画制作を
動画を制作する際には、ターゲットが重要です。例えばITに詳しくない人でも操作できるソフトウェアを紹介する場合、専門用語を使ってしまうと導入してもらえない可能性があります。
反対に専門用語を使わずにわかりやすい言葉で説明すれば、ITに詳しくない人でも操作できるソフトウェアだと思って導入してもらえるでしょう。
ターゲットを考えることは、動画の内容を考える際にも有効的です。いきなり動画の内容を考えるのは難しいですが、先にターゲットが決まっていれば逆算する形で考えられます。
そのため、これから動画を制作する方はどのような人に届けたいのかハッキリとさせることから始めましょう。
動画制作は必ずプロに任せる必要はない
動画制作は難しいイメージがあるため、プロに依頼しないといけないと思うかもしれません。確かにCGといったハイレベルなスキルが求められるものはプロに任せたほうがおすすめですが、それ以外であれば自分たちでも制作できる可能性があります。
近年では、動画制作をしたことがない場合でも制作できるソフトやサービスが数多くでています。その上、動画制作のスキルを習得すれば今後にも活かせるため、この機会に覚えてみるのも良いかもしれません。
ソフトウェア系企業も動画の活用を!
今回は、ソフトウェア系の企業における動画の活用方法や主な事例などを紹介しました。
ソフトウェア系の企業でもマニュアルや求人などで動画を活用できます。実際に活用している企業も複数あるため、それらを参考にしながらあなたの会社でも制作してみてはどうでしょうか。