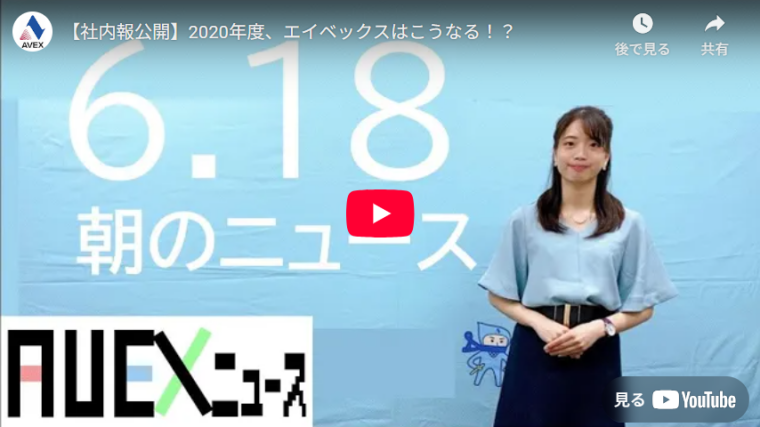この記事は、こんな方におすすめです
- ✅ 社内報の動画化を検討しているが、編集スキルに不安がある
- ✅ 社員の紹介や活動を動画で伝える仕組みを整えたい
- ✅ 企画から配信・管理まで、一括で効率よく行いたい
▶ メディア博士の資料を見てみる
社内報とは
社内報とは会社全体の方針を伝えたり、社内でのイベントやコミュニケーションの機会を作るための手段の一つです。
これまでは、冊子にされた紙媒体が主でしたが、最近では社内報アプリを取り入れる会社や、WEBや動画を使ったメッセージなど、様々な社内報の形が出てきています。
ほとんどの従業員がデジタルデバイスを使用している企業の場合だと、WEBやアプリなどを使った社内報が効果的ですが、従業員があまりデジタルデバイスに触れる機会がない場合は、紙媒体での社内報がおすすめです。
最近ではほとんどの人がスマートフォンをもっているので、従業員の年齢層によって媒体を使い分けるというのも一つの効果的な手法です。
社内報の目的
社内の情報共有を円滑にする事と社内のコミュニケーションを促進する事が社内報の主な目的です。
例えば、会社の理念や、将来のビジョンを社内報で定期的に発信することで、従業員に経営方針が浸透し、会社全体で足並みを揃えていくことができます。従業員一人ひとりが会社の将来のビジョンに向かって仕事をしていくので、結果として会社の成長に繋がります。
さらに、大企業で他の部署の人との交流が少ない場合や、支店が多い場合などは他の部署がどのような活動をしていたり、どんな人が働いているのかわからないですよね。
そのようなときに、社内報を通して情報共有を図ることで、会社全体の活性化を促進することもできます。また、社内報で素晴らしい実績を収めた人を紹介することで従業員のモチベーションの向上も期待できます。
社内報の中に動画を取り入れるメリット
社内報が社内のコミュニティを強め、会社の成長に繋がることはお分かりになられたかと思います。次に、社内報に動画を取り入れるメリットについて紹介していきます。
社内報の中に動画を取り入れるメリットは以下の4点です。
コストを削減することができる
動画の場合は一度作ってしまえば、使い回すことができるのでコストの削減に繋がります。
例えば経営理念や将来のビジョンの動画、もしくは新人の研修向けに動画を作成する場合は、何度も繰り返しその動画を使うことができるので、担当者の負担を軽くすることだけでなく、人件費、動画制作にかかる費用を削減することができます。
繰り返し使える動画媒体は、紙媒体などに比べて環境にもいいので、社会のエコに貢献する企業の社会的責任を果たす役割もあります。
迅速かつ正確に伝えることができる
動画は、テキストや画像に比べて圧倒的な情報量があります。
文字だけでは伝わりづらい表情や細かいニュアンスなどを、動画ではしっかり伝えることができます。さらに、動画では物事をより短い時間で理解させることができるので、時間短縮にも繋がります。
DVDや印刷物などは、郵便物として送られてくるまでに時間がかかってしまいますが、動画コンテンツの場合だと、制作してインターネットにアップロードするだけで、距離を問わず全従業員に向けて発信することができます。
以上の点から情報を迅速かつ正確に伝えられるという点で動画は優れているといえます。
最近では、コロナ渦をきっかけにリモートワークを採用している企業も増えており、より一層動画コンテンツの重要性は増してきています。
従業員の印象に残りやすい
人は目と耳を使って情報を得たときのほうが印象に残りやすいといわれています。そのため、テキストだけのコンテンツよりも動画のように、音声と映像を組み合わせたときのほうが印象を強めることができます。
また、動画では細かい編集をすることができるので、細かい世界観を演出したり、大事な部分を強調したりと、従業員に与える印象をコントロールすることが可能です。
社長や従業員の人柄が伝わりやすい
先程も述べたように動画コンテンツでは、テキストだけでは伝わりづらい表情などを見る人に伝えることができます。
社内インタビューや、社長の挨拶といったコンテンツを作成する場合、テキストだけだとその人の人柄があまり見えてきませんが、動画コンテンツにすることで、その人の話し方や表情から人柄や雰囲気までを鮮明に伝えることができます。
人柄が伝わることで、社員同士に親近感が生まれ、社内のコミュニティを活発化することができるので、社内のコミュニティを強化したいという企業は、可能な限り社内報に動画を取り入れるようにしましょう。
社内報の事例を紹介!
ここからは、実際の社内報動画について紹介していきます。
【社内報動画】引っ越し

この動画では、新オフィスの紹介をしています。
某TV番組に似せた構成にすることで、ユニークな印象の動画に仕上がっています。従業員に飽きさせない工夫が施されているのもいいですね。
【社内報公開】2020年度、エイベックスはこうなる!?
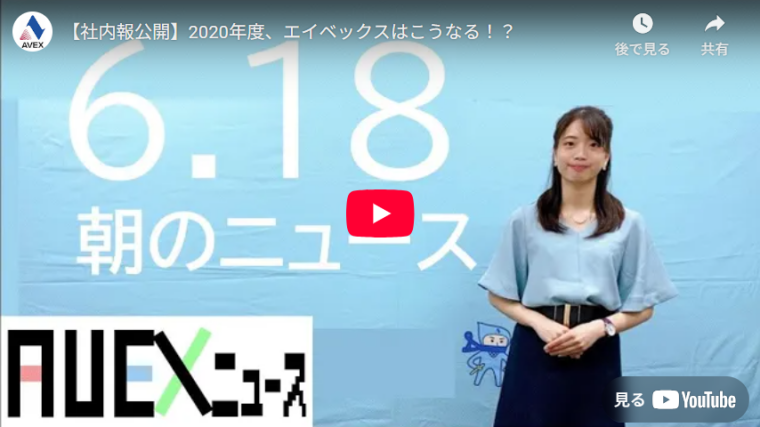
こちらの動画では、71期目を迎えた会社で、今後一年をどのような一年にしていくのか社長にインタビューするという内容の動画です。
ニュース形式の動画にすることで、伝えたいことがはっきりと伝わる効果を生み出していますね。また、社長の口から直接従業員への思いや今後の会社の見通しについて聞くことができるというのは、従業員にとってとても有益な動画だと言えます。
社内報の中に動画を取り入れる際の注意点
社内報の中に動画を取り入れる際には、ただやみくもに動画を追加するだけでは、逆に視聴されなかったり、メッセージが正しく伝わらなかったりといった課題が発生することもあります。
ここでは、社内報の中に動画を取り入れる際の注意点について解説していきます。
動画の目的と役割を明確にしてから制作する
最もよくある失敗は「とりあえず動画を入れてみた」というパターンです。目的が曖昧なまま動画を制作してしまうと、誰に何を伝えたいのかがぼやけ、従業員に響かない内容になってしまいます。
例えば、「社内表彰の紹介」動画なのか、「社長メッセージの共有」なのか、「業績の報告」なのかによって、企画構成や語り口調、映像トーンもまったく異なるはずです。
まずは社内報全体の中で、動画が担うべき役割を明確にし、そのうえでコンテンツ内容を決定するようにしましょう。
視聴環境を考慮した設計にする
社内報動画の視聴環境は企業によって異なります。社内PCでの視聴が前提の企業もあれば、スマートフォンでの視聴が主流なケースもあるでしょう。
また、現場スタッフや工場勤務の従業員が多い場合、音声を出せない環境であることも珍しくありません。このような環境に合わせて、以下の点を事前に確認・対応しておく必要があります。
・音声がなくても内容が理解できるように字幕をつける
・通信量がかからないよう、動画の解像度や容量を抑える
・再生形式やプラットフォームが業務端末で対応しているか確認する
・視聴ログや既読確認が必要な場合は専用配信ツールを利用する
このような設計を怠ると、「せっかく作ったのに誰も見ていない」という状況にもなりかねません。
動画の長さとテンポに注意する
社内報動画は基本的に「業務の合間に見る」ものです。そのため、長すぎる動画や展開の遅い動画は敬遠されがちです。
特に冒頭で何も起こらない動画や、自己紹介だけで1分以上使ってしまうような構成は離脱を招きやすくなります。
理想的な長さは2~4分程度。5分を超える場合は、セクションごとにチャプター分けや目次テロップを入れるなどして、視聴者の集中力を維持できる工夫が求められます。
また、リズム感を持たせるためにテロップの切り替え、効果音、BGMなどを適切に取り入れると、最後まで飽きずに見てもらえる可能性が高まります。
出演者やナレーションに対して適切な配慮をする
社内動画に登場する人は、必ずしも表現や話し方に慣れているとは限りません。特に社長や役員が話す動画では、緊張によって表情が硬くなったり、言葉に詰まってしまったりするケースも多々あります。
そのため、撮影前に簡単なリハーサルを行い、伝えたい内容を事前に整理しておくことが重要です。また、出演に対して抵抗がある社員には、無理に登場を依頼せず、イラスト・音声のみ・テキストで代替するなどの柔軟な対応も検討すべきです。
ナレーションを加える場合も、外部ナレーターに頼むか、イントネーションの調整ができるAI音声を活用することで、全体の聞き取りやすさを確保できます。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、社内報動画の必要性とそのメリットについてご紹介しました。
社内報の中に動画を上手く活用することで、より多くの情報を従業員に伝えることができ、多くの人の意識を変えることも可能になります。また、動画は社員同士をつなぐといった使い方もできるので、結果として社内コミュニティを強化することも期待できます。
海外の企業でも社内報に動画を活用する企業がだんだん増えてきており、今後日本でも社内報に動画を取り入れる企業が増えていくはずです。
社内コミュニティを活発にするためにも、社内報に動画を取り入れてみてはいかがでしょうか。