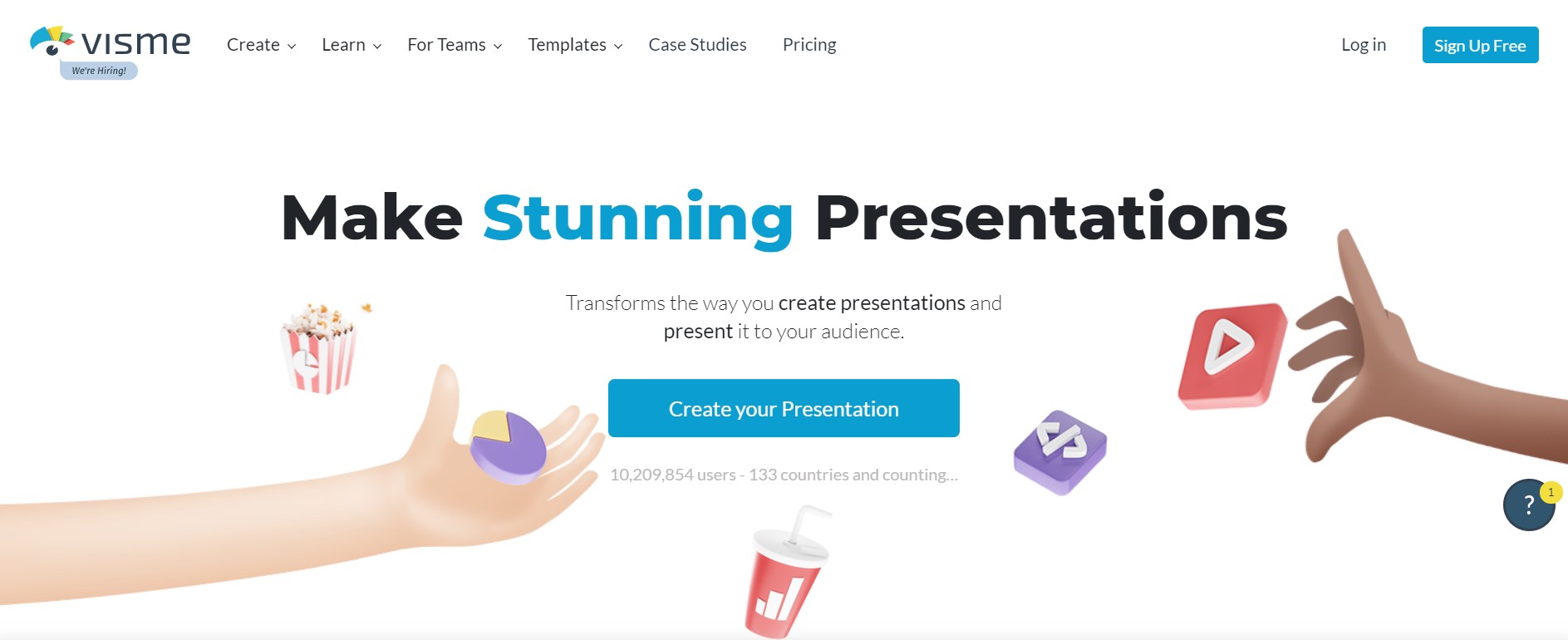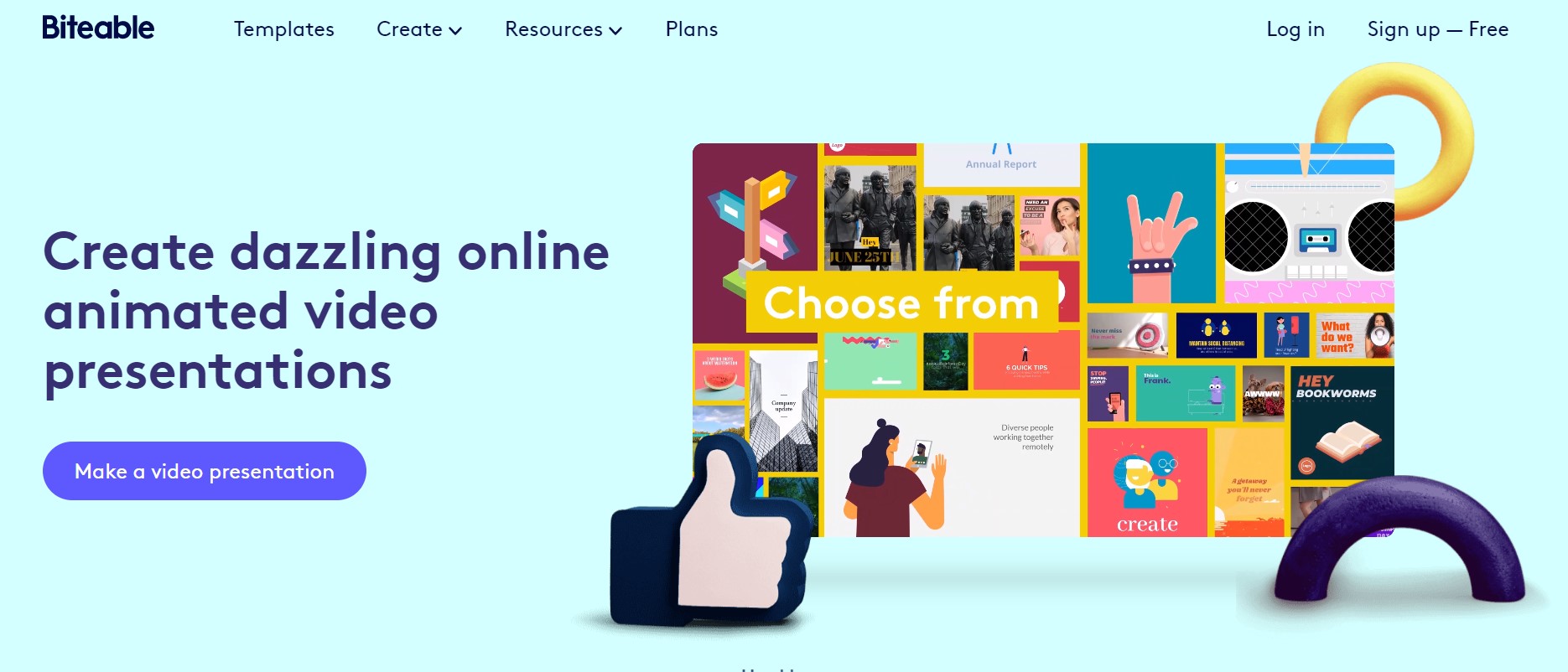この記事は、こんな方におすすめです
- ✅ 動画を活用した効果的なプレゼンを検討している法人担当者
- ✅ 社内での企画説明や提案に動画を取り入れたいと考えている
- ✅ 短時間でインパクトのあるプレゼン動画を社内で作成したい
▶ メディア博士の資料を見てみる
プレゼンテーションは誰もが緊張してしまうもの
まずは、プレゼンテーションの成功に欠かせない基本的な認識からおさえていきましょう。
このような名言を耳にしたことがあるでしょうか?
『敵の前で死に遭遇しても、多くの者はその事実を受け入れる。しかし、会議場で臆することなく話す者はめったにいない。』
この言葉は、戦争が絶えない時代のヨーロッパの詩人が説いた言葉です。この言葉を現代風にアレンジすると、『知人の前では確かに多くの者が恐れを知らずにいれるが、学識者の集会で恐れを知らない者はほとんどいない。』と訳す事ができます。
そもそも人間は、不特定多数の前で発言することやプレゼンテーションが苦手なのです。
理由はいくつかあげられ、
コントロールできない不安感
過去の嫌な記憶とのリンク
自分の自信のなさ
などがあります。
しかし、こういった苦手要素は原因を理解すれば解消されます。そのため、プレゼンテーションとは誰もが苦手なもので、人それぞれの苦手の原因を理解することがプレゼンテーションの成功への基礎認識になります。
プレゼンテーションを成功させるためには?
基礎認識を把握したあとは、プレゼンテーションの成功の鍵を抑えましょう。そもそもいいプレゼンテーションを行う人とは、どのような特徴があるのでしょうか?
プレゼンテーションを成功させる人は、共通してコミュニケーション能力が高いとされています。
そのような人は、自信をもって大勢の人や関係のない人に対して臆することなく発言できたり、情報を素早く・明確に伝える能力があるため、プレゼンテーションの場でも同様に能力を発揮することができ、プレゼンテーションを成功させやすくなります。
また、職場でのプレゼンテーションの場合、プレゼン内容のみならず、そのプロジェクトの責任を果たせるのかどうかも同時に見られています。
自身がプロジェクトの中心が勤まる事を示すためにも、以下の点をプレゼンテーションでアピールできるかが成功の鍵を握ります。
コミュニケーション能力の高さ
自信があるものの、自分が実現できる事と不可能なレベルを示すことができる
情報を重要度別に分析する能力
情報を統率できる能力
プレゼンテーションの成功率を上げるために動画を利用すべき
プレゼンテーション成功の鍵を紹介してきましたが、このようなポイントは育ってきた環境や幼いころからの経験をもとに身に着けるもので、短期間のうちに習得できるものではありません。
だからといって、プレゼンテーションの成功率を上げる手段が無いわけではありません。上記のような能力が不十分な方には、動画をプレゼンテーションに活用することで能力不足を補うことができます。
なぜ動画を活用するとよいかというと、以下のメリットがあります。
ストーリーをまとめて伝え、感情的な反応を促す
文字以上の情報量を短く伝える
聴取側に緩急をつけれる
一つずつ紹介していきましょう。
ストーリーをまとめて伝え、感情的な反応を促す
プレゼンテーションでは、プロジェクトの動機を紹介する場面が必ずあります。文字だけのプレゼンテーションでは動機のみを紹介し、動機からプロジェクトに発展させた方法などを時間の都合上省略しがちになります。
しかし、プロジェクトの発展はストーリー性が高く、聴取側に感情的な刺激を与える重要な部分になります。感情的な反応を促し、プレゼンテーションに関心を持ってもらいたい場合は、プロジェクトのストーリー部分を動画で紹介するようにしましょう。
文字以上の情報量を短く伝える
情報を詰め込みすぎてプレゼンテーションが長引いてしまうことは、聴衆側にとってストレスでしかありません。
プレゼンテーションの目的は、自分のプロジェクトや考えを紹介し理解してもらうことです。そのため、長すぎるプレゼンテーションは本来の意図を失ってしまいます。
プロジェクトの魅力を存分に伝えたいが、プレゼンテーションは長くしてはいけない。こんなしがらみを解決してくれるのが、プレゼンテーションでの動画活用です。
動画は、文字の10倍以上の情報量を一度に伝えることができるとされており、長さと量のバランスに課題がある場合は、ぜひとも動画を活用しましょう。
プレゼンテーションに緩急をつけれる
プレゼンテーションに動画を活用することで、聴衆側に視覚的な刺激を与えることができます。
文字の場面から動画に変わるだけで、プレゼンテーションの単調さがなくなり、さらに聴衆側と発表側の両者に一次的な休憩を設けます。
聴衆側は、プレゼンテーション内の強調部分が分かりやすく、記憶に残りやすくなります。一方で発表側は、プレゼンテーションのテンポを調整できるため、失敗してしまった部分のフォローができます。
プレゼンテーション動画の作成方法
効果的なプレゼンテーション動画を作成するには、いくつかの手順を踏んで計画的に進める必要があります。ここでは、プレゼンテーション動画の作成方法を紹介していきます。
目的と構成を明確にする
プレゼンテーション動画の制作において、最初に取り組むべきは「何のためにこの動画を作るのか」という目的の明確化です。
営業提案なのか、社内報告なのか、あるいは採用向けの会社紹介なのか。目的が変われば、動画で強調すべきポイントや構成も大きく変わってきます。
目的を定めたら、それに沿った構成を検討します。多くの場合、動画は冒頭に視聴者の関心を引きつける導入パートを置き、その後に本題となる説明を加え、最後にまとめや行動喚起(CTA)で締めくくる構成が効果的です。
使用素材を準備する
構成が固まったら、次は動画に使用する素材の準備に進みます。
ここで準備するのは、スライド資料や図解、写真、製品の紹介映像、ナレーション音声など、多岐にわたる素材です。素材の質が動画の完成度に直結するため、できるだけ内容に合った明瞭な画像や映像を選び、文字情報も簡潔に整理しておくことが重要です。
また、視聴者の集中力を途切れさせないよう、1つの画面に情報を詰め込みすぎない工夫も求められます。
音声素材に関しては、プレゼンター本人のナレーションを録音する方法と、ツールによる合成音声を活用する方法があり、用途に応じて選択することができます。
撮影・編集を行う
素材が揃ったら、実際の撮影と編集に取りかかります。プレゼンターが登場する場面を撮影する場合は、スマートフォンでも十分に対応可能ですが、撮影時は明るい場所を選び、背景や服装に注意を払うと、より清潔感のある映像になります。
撮影の内容がナレーションのみであれば、画面にスライドや画像を表示しながら音声を重ねるスタイルでも問題ありません。
編集では、スライドの切り替えタイミングやナレーションとの同期、視認性の高いテロップの挿入、テンポのある場面展開などに注意を払います。
動画の長さは一般的に3〜5分以内が好ましく、冗長にならないよう調整が必要です。視聴者の興味を引き続けるために、要点をシンプルに、かつ印象的に伝える構成を意識しましょう。
レビューと修正を行う
編集が完了した後は、必ず動画全体を通して確認し、改善点がないかをチェックする工程が欠かせません。
制作時には気づきにくかったナレーションの言い回しや音量のばらつき、表示時間が短すぎて読みにくいテロップなど、細かい修正点が見つかることもあります。
また、内容が目的に合致しているか、構成に不自然な流れがないかといった観点でも確認が必要です。できれば第三者にも見てもらい、客観的な視点からフィードバックを得ると、より質の高い動画に仕上がります。
修正を経て完成した動画は、配信先のメディアに合わせた形式で書き出し、公開のステップへと進みます。
ビデオプレゼンテーションに役に立つソフトウェア
プレゼンテーションに動画を活用すべき理由を紹介しましたが、実際にプレゼンテーションの全てもしくは一部で動画を活用する際に役に立つソフトウェアを紹介していきます。
Visme
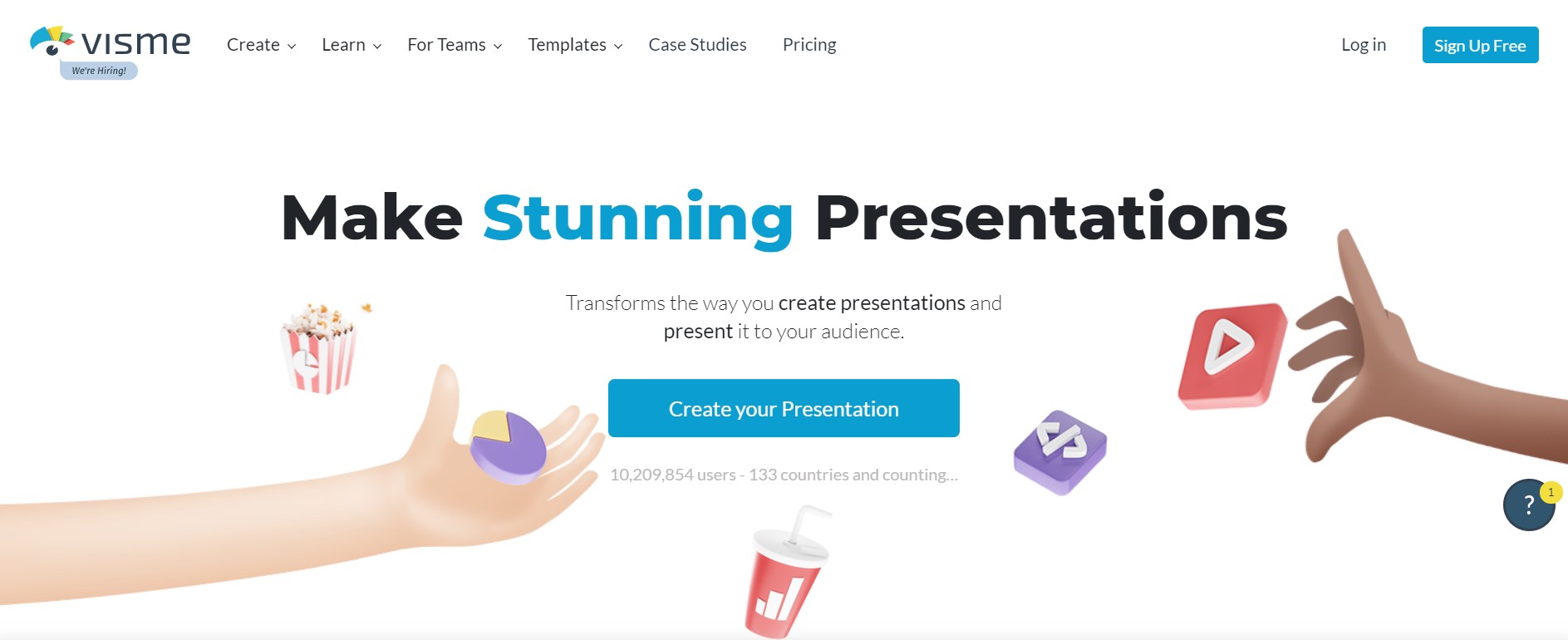
Vismeは、リアルタイムのコラボレーションを必要とするチームや、
インタラクティブなプレゼンテーションのための高度な機能やカスタマイズを必要とする個人にとって最適なプレゼンテーションソフトウェアです。
50種類以上のチャート&グラフやマルチメディア機能などが備わっています。無料版も用意されており、有料版は個人、ビジネス、教育プランの3パターンがあります。
Biteable
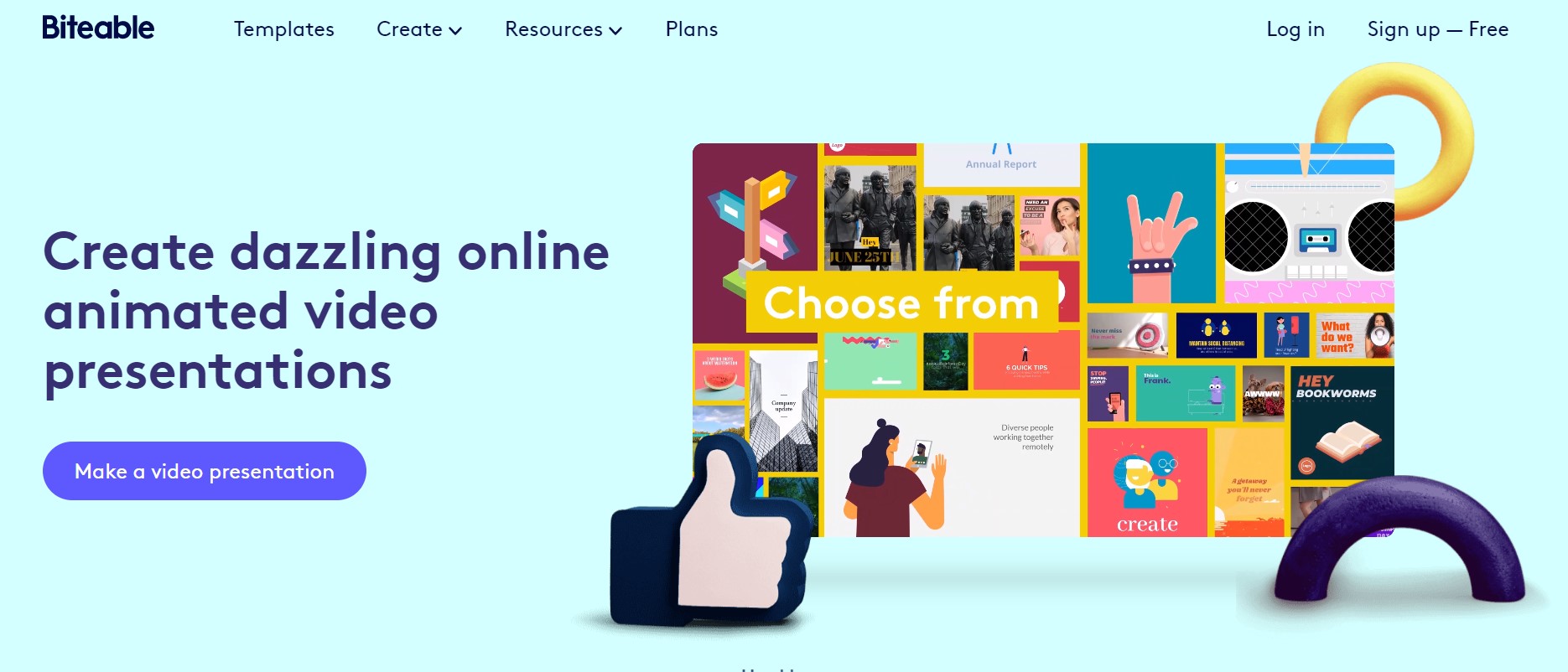
Biteableでは、マーケティングを学んだかどうかに関係なく、プロ並みのビデオプレゼンテーションを数分で作ることができます。膨大な種類のテンプレートとアニメーションがあり、すぐに使えるものばかりが用意されています。
さらに、純正オーディオ提供や独自のオーディオをアップロードもできます。無料プランでは動画の作成のみですが、有料プランでは様々なサービスが用意されています。
日本語対応ビデオプレゼンテーションのソフトウェア
Visme、Biteableはどちらも英語表記のみとなります。日本語対応のものではPowerPointやFilmoraなどがありますが、英語が読めるのであれば、海外のソフトウェアの方がサービスの量、質ともに優れているのでおすすめです。
まとめ
さて今回は、プレゼンテーションでの動画活用について紹介してきました。時代が変わっても、プレゼンテーションの重要性は変わりません。
しかし、プレゼンテーションの手段は文字から動画に変わってきています。魅力的なプロジェクトを実現するためにも、動画を活用したプレゼンテーションに挑戦し、成功させましょう。