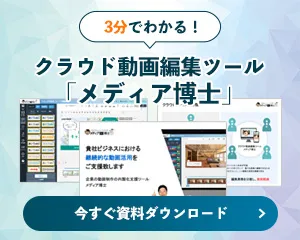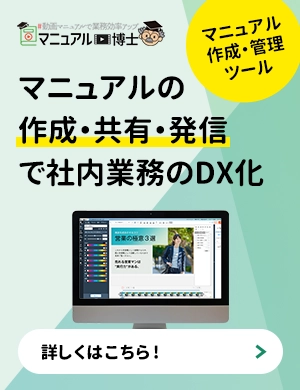小学校のオンライン授業動画の作り方と効果的な活用方法を徹底解説

クラウド動画編集ツールのご案内資料
今すぐ無料ダウンロード通学が困難な現状の中で、授業を継続するために一部の学校ではオンライン授業が取り入れられていますが、公立学校などでは設備面や金銭面、教師の負担などの多くの問題があるため、オンライン授業を取り入れている学校はまだ全体の3割にも及んでいません。
引用元:学校に関する状況調査、取組事例等
ここではこれから本格化するであろうICT教育に向けて授業動画の作り方、そして効果的な活用方法について詳しく解説していきます。
この記事は、こんな方におすすめです
- ✅ 小学校でオンライン授業の導入や運用を検討している
- ✅ 教員に頼らず、動画を活用した教材整備を進めたい
- ✅ 保護者や地域との連携強化に、伝わりやすい動画を活用したい
オンライン授業動画のメリット
新型コロナウイルスが流行する前からオンライン授業を実施していた学習塾業界とは異なり、コロナ禍で初めてオンライン授業を実施したという小学校も多いと思います。ここではまず、オンライン授業動画のメリットを確認していきましょう。
端末さえあればいつでもどこでも通常の授業を継続することができる
オンラインで授業をすることができれば、コロナ禍のような緊急事態にも臨機応変に対応し、授業を継続することができます。例えば新型コロナウイルス蔓延を防ぐために分散登校を実施していた学校では、登校組が授業を受けている映像を在宅組の学生に配信することで、授業を遅らせることなく効率的にすべての学生に同じ授業を提供していました。
遠隔授業で都心と地方の教育レベルの偏りを解消できる
これまでの通学型の授業では都心と地方の教育レベルが開いてしまうことが問題視されていましたが、オンラインで教室をつないで授業をすることで、学生の学力アップを図ることが期待できます。また、お互いのカメラをオンにして行うオンライン授業では先生が生徒の様子を確認しながら授業を行うことができ、カメラをオフにして行う場合では、生徒はチャット機能を使うことで質問や回答することができるので、なかなか対面授業では恥ずかしくて発言できないような内向的な生徒でも学びやすい環境の中学習することができます。
動画なのでわからないところは何度も繰り返し学習することができる
動画教材のメリットは、対面授業では、進度が早くてついていけないといった生徒でも、わからないところを止めて考える時間を確保したり、何度も繰り返し視聴して理解を深めることができる点です。ただ、授業内で画面に写ってしまう先生や生徒の著作権は、今後解決していくべき課題だといえます。
オンライン授業動画を作る時のポイント
オンライン授業動画のメリットが確認できたので、次は授業動画を作る時のポイントについて確認していきましょう。授業動画は長過ぎないようにする(大体15分程度がベスト)
授業動画を作るときは、動画の長さに気をつけましょう。対面授業が45分だからといって、45分ずっと先生が話している画面を集中して見続けられるほど、生徒の集中力は長くは続きません。通常で行っている授業とは構成を変えて動画を作ることを意識してみてください。また、授業で話すことをあらかじめ台本にしておいて、生徒が思わず授業に夢中になってしまうような構成にすることが大切です。そのためのコツとして、2番目のポイントを意識してください。
動画の冒頭で授業内容を宣言する
生徒を思わず夢中にさせるコツはズバリ、動画の冒頭部分で話す内容を宣言し、「今日の授業のポイントは5つあります!」というように、内容をいくつかに絞って話すことを心がけることです。生徒にどの部分が重要なのか意識させることで、学習の吸収効率を高める効果が期待できます。また、「坂本龍馬は最終的にどうなったのか?」というように、あえて結末を教えないで授業にストーリー性をもたせるのも効果的です。
話す速度と長さに気をつける
話すときはできるだけ、間をあけてゆっくり話すことを意識しましょう。画面の向こう側の生徒に内容を理解してもらうために話す速度はゆっくり、強調するべきところは繰り返し話すということが効果的です。また、一度に話す時間は長くても5分程度に収めるのがベストです。先生が話し続ける授業よりも、生徒に考えさせる時間を作ったり、積極的に意見を話してもらうような生徒参加型の授業にしたほうが、生徒のモチベーションと集中力を持続させることができます。
学校での実際のオンライン授業動画活用例
ここからは、実際に小学校で行われているオンライン授業を例にもう一度どのような授業動画が効果的なのか確認していきましょう。岡山中学校・岡山高等学校/オンライン授業
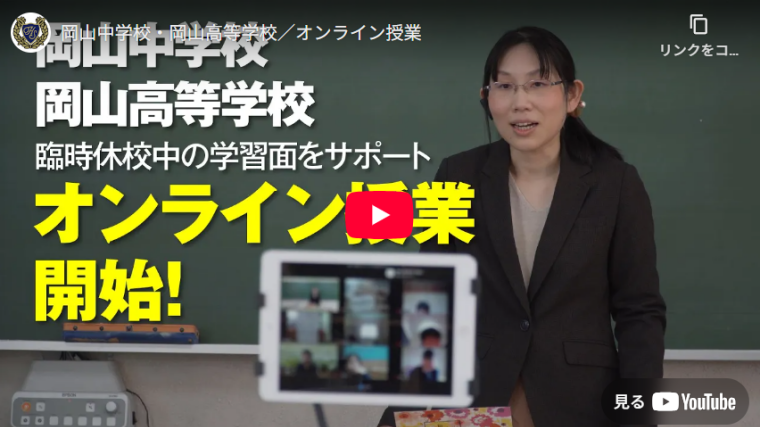
この動画は、岡山中学校・岡山高等学校のオンライン授業の様子を映した動画です。動画を見てみると同じオンライン授業でも各教科の先生ごとに構成や授業の進め方が違うことがわかります。
教師と生徒がお互いでカメラをオンにして行う授業や、黒板を使いながら授業を進めたり、黒板を使わずに資料を画面上で共有しながら授業を進める方法など様々です。
小学2年生|算数|1−1 ひょうとグラフ
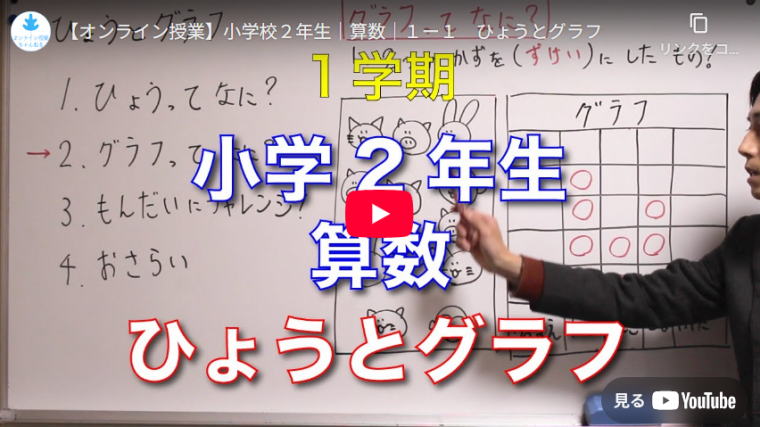
この動画は、オンライン授業ちゃんねる【すえちゃん】というYouTubeチャンネルの動画です。動画の冒頭部分でどのような授業なのか、授業の流れを説明することで、生徒が授業の流れを掴み、すばやく理解ができるように工夫が施されています。
実際の対面授業では、先生が黒板に文字を書いている時間がロスタイムとなりますが、オンラインの動画は自由自在に編集ができるため、無駄な時間を省いて効率的な授業が可能になります。
オンライン授業動画を作る時の注意点
オンライン授業動画を作る時には、ただ授業を録画して配信するだけでは、生徒の学習効果や集中力を十分に引き出すことは難しいのが現実です。ここでは、実際にオンライン授業動画を作る時の注意点について解説していきます。画面収録や自撮り動画では著作権に要注意
授業内容をより豊かにするために、さまざまな資料や画像、動画を取り入れることがありますが、その際には必ず著作権の確認が必要です。市販の教科書の図表や、インターネットからダウンロードした画像を無断で使うと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。たとえ教育目的であっても、営利性のない授業であっても、第三者の著作物を無断で利用することは避けるべきです。
授業で使う資料は、できる限り自作するか、著作権フリーの素材や文部科学省、教育系の公的機関が提供しているものを使用するようにしましょう。
教材動画が学外に公開される可能性がある場合は特に、著作権チェックは怠らないようにしてください。法的なリスクを未然に防ぐことが、安心して動画教材を継続的に活用するための土台になります。
生徒のプライバシーに十分配慮する
オンライン授業動画の中に生徒が映り込む可能性がある場合は、プライバシーへの配慮が不可欠です。録画中に生徒の顔や名前、家庭の背景などが意図せず映ってしまうと、プライバシーの侵害と受け取られる恐れがあります。特に、動画を学校の外に公開する際は、保護者の同意を得ることが前提となります。撮影する際にはカメラアングルを工夫して生徒が映らないようにしたり、名前の呼びかけ方にも注意を払ったりと、あらかじめトラブルのリスクを減らす配慮が求められます。
生徒が主体となるコンテンツを含む場合は、書面での同意を得るなどの対策も考慮しましょう。先生の発信が生徒にとって安心できる環境であることが、教育効果の土台となります。
編集・保存は更新性と簡便性を意識する
一度授業動画を作成して終わりではなく、状況やカリキュラムの変更に合わせて内容を更新することが前提となります。授業の改善や新しい学習指導要領への対応、学年ごとのカスタマイズなどを考えると、更新しやすい編集環境を整えておくことが大切です。複雑な編集ソフトを使わなくても、クラウド型の動画編集ツールを活用すれば、誰でも簡単に動画の差し替えや再編集が行えるようになります。
また、動画と同時に資料や説明文を添えて配信することで、学習の補助資料としての機能も強化されます。継続的に授業動画を活用するためには、制作の手間を減らし、誰でも操作できる仕組みを作ることが最終的な成功につながります。
まとめ
いかがでしたか?コロナ禍のような緊急事態においては臨機応変に対応することが重要で、完璧な授業よりも対応のスピードが求められています。まずは自分なりにオンライン授業動画を作ってみて、だめだと思ったらまた修正を加えてみる。
授業に正解はないので、まずは自分のできそうなことから始めて試行錯誤を繰り返してみましょう。そうしてコツやポイントをつかめば、きっと生徒にクオリティーの高い授業動画を提供することができます。

田村 航
株式会社博士.com
メディア事業・プロモーション業務管轄
サブマネージャー
博士.comに2017年に中途入社し、不動産会社のHP制作やSEOコンサルタントとして従事。
これまでに累計で80社以上のクライアントを担当し、幅広い支援実績を持つ。
その後、メディア事業部へ異動し、これまで培ったSEOやコンテンツ戦略の知見を活かしながら、動画活用のコンサルティングに携わっている。

田村 航
株式会社博士.com
メディア事業・プロモーション業務管轄 サブマネージャー
博士.comに2017年に中途入社し、不動産会社のHP制作やSEOコンサルタントとして従事。
これまでに累計で80社以上のクライアントを担当し、幅広い支援実績を持つ。
その後、メディア事業部へ異動し、これまで培ったSEOやコンテンツ戦略の知見を活かしながら、動画活用のコンサルティングに携わっている。
動画制作・企画・撮影・編集・発信を総合サポート
企業の動画活用内製化支援ツール【メディア博士】
クラウド動画制作ツールでビジネス動画をカンタン作成
クラウド動画作成ツールのメディア博士ならブランディング動画・プロモーション動画・社内広報動画・広告動画などを簡単制作!
誰でも作れる・すぐに作れる・いくらでも作れる
メディア博士での動画作成には、難しい操作や知識は必要ありません。初心者でも手間なく短時間で完成させることができAI機能や専属コンサルタントが動画作成をサポートします。
また、定額プランで月に何本作ってもOK!いつでも更新・アップロードができます。
動画制作の内製化(インハウス化)で動画をフルに活用しませんか?
-

1分でわかる【メディア博士】最新パンフレット
-

【企業担当者向け】社内の誰もができる!スマートフォンでの動画撮影テクニック
-

[飲食業界・外食チェーン向け]現場教育に効果的な動画マニュアル活用のポイント
-

動画構成の考え方と作り方!「伝わる」動画にするためのポイント
-

企業が取り入れたい動画活用スタートガイド
-

YouTubeマーケティング手法とVSEO(動画SEO)のポイント
-

動画のインハウス化の失敗事例から学ぶ 内製化成功のポイント
-

動画作成に役立つ!字コンテ作成用テンプレート&活用サンプル
-

スマートフォン動画撮影チェックシート【全31項目】
-

動画制作の費用を抑えるコツ!内訳別・種類別の費用相場
-

[消費者の動画視聴と購買行動から考える]企業の動画事業活用シーンまとめ
-

動画活用のコンサルティングサポートガイド
-

手振れなし!スマホを使った動画撮影の手引き|電動ジンバルの活用

すべてのタグ一覧


 動画の活用をお考えの方
動画の活用をお考えの方