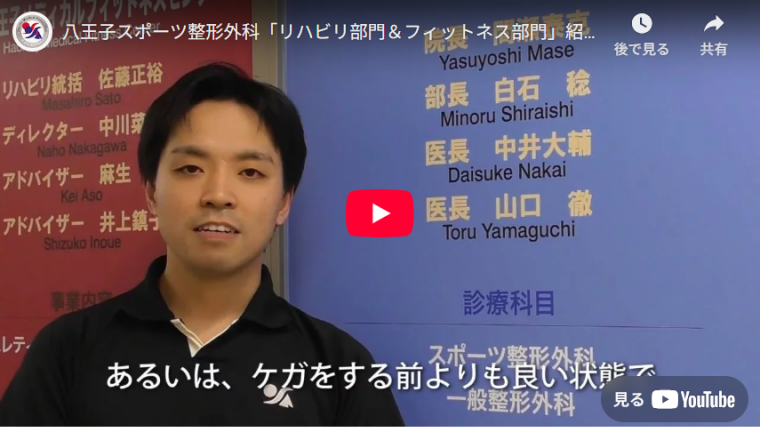さまざまな業種が動画コンテンツを活用してPRをおこない、集客につなげています。スポーツ医療のクリニックや、専門の整体院でも動画コンテンツを制作すれば、新規の利用者を獲得することが可能です。
本記事では、スポーツ医療の動画コンテンツを活用してPRに繋げるためにはどのようなコンテンツが制作出来るのか、どのような事例があるのかを解説します。
スポーツ医療のPRに動画を活用するべき理由
スポーツ医療の分野にとって、動画は単なる宣伝ツールにとどまらず、専門性・信頼性・親近感を伝える可視化の手段として大きな効果を発揮します。ここでは、そんなスポーツ医療のPRに動画を活用するべき理由について解説します。
治療内容や専門性を視覚的に伝えられる
スポーツ医療は一般の人から見ると少し難解な分野です。例えば、「運動器リハビリ」「筋機能評価」「超音波診断装置」など、聞き慣れない専門用語が多く、文章だけでは理解しにくい情報も多くあります。
そこで動画を活用すれば、治療風景や設備の稼働シーン、トレーニングの様子などを映像で「見せる」ことができ、視聴者の理解と納得につながります。
特に、ビジュアルでの説明は信頼感を生みやすく、「このクリニックなら任せられそう」と思ってもらいやすくなります。
アスリートの心理に響く実績と共感を伝えられる
スポーツ医療の対象者には、部活動を頑張る学生や競技を続ける社会人アスリートなど、目的意識の高い層が多く存在します。彼らにとっては、「実績」や「成果」が治療先を選ぶ上での大きな判断材料になります。
その点、過去の症例紹介やリハビリ成功事例を動画にまとめることで、より効果的な訴求が可能になります。実際の患者のインタビューやビフォーアフター映像は、文字や写真よりも圧倒的な説得力を持っています。
トレーニングやセルフケアの指導コンテンツに展開できる
スポーツ医療においては、「来院時だけ」ではなく、日常的なセルフケアや自主トレーニングの質が回復・予防に大きく影響します。そこで有効なのが、患者向けのトレーニング動画の提供です。
例えば、
・スポーツ別(サッカー・野球・陸上など)のウォーミングアップ法
・怪我予防のためのストレッチ
・自宅でできるリハビリ方法
など、動画で解説することで視聴者は繰り返し視聴でき、正しい方法を身につけることができます。
さらに、トレーニング動画は「専門性の高い指導ができる施設である」というブランディングにもつながり、継続的な関係構築が可能です。
スタッフ採用や教育にも応用できる
スポーツ医療の現場では、柔道整復師や理学療法士、アスレティックトレーナーなどの専門職スタッフが必要不可欠です。
しかし、採用活動では「どんな職場なのか」「どんな方針で運営されているのか」が伝わりにくいこともあります。
そこで、職場紹介動画や先輩スタッフのインタビュー映像を制作することで、求職者の不安を解消し、応募動機を高める効果が得られます。また、研修用動画を活用することで、新人スタッフの教育も効率的に行えるようになります。
スポーツ医療のPRに活用できる動画コンテンツ例
スポーツ医療の動画を通してクリニックや整体院の認知度を高めるコンテンツはどのようなものがあるのでしょうか。PRに繋がる動画活用例を紹介します。
クリニックのサービス紹介
スポーツ医療を提供するクリニックによってサービス内容が異なります。クリニックが提供するサービスがどのようなものかを分かりやすくまとめた映像コンテンツの制作もおすすめです。
映像を制作する際には、以下の情報を反映するように心がけましょう。
・スポーツ医療の中でもどの分野を得意としているクリニックなのか
・クリニックの設備
・治療法・リハビリテーションの様子
・スタッフ紹介
視聴者がサービスを実際に利用したいと感じるように、伝えたい情報をまとめて紹介しましょう。
動画を制作するだけでなく、概要欄にクリニックの予約ページやクリニックのホームページにアクセス出来るようコンテンツを制作する際には気をつけるようにしてください。
トレーニング紹介
スポーツ医療では、ケガをしたアスリートへのリハビリをサポートするためのさまざまなトレーニングがあります。
視聴者におすすめのトレーニング方法を紹介するコンテンツも有効です。
トレーニング映像を制作することで、自宅で実践する映像を提供出来るだけでなく、スポーツクリニックや整体院としての権威性を高めることが可能になります。
トレーニング映像を制作する際には、以下の内容を意識しながら動画コンテンツを制作しましょう。
・正しいトレーニング方法を紹介する
・間違ったトレーニングをしないように気をつけるべきポイントを紹介
・トレーニングをしてはダメなケースなど視聴者へのリスク喚起をおこなう
視聴者に誤解を与えないよう、分かりやすい動画制作を心がけましょう。
セミナー形式映像
スポーツ医療に携わるスタッフや、これからスポーツ医療の分野で活躍をしたいという方に向けた映像コンテンツもおすすめです。
セミナー形式の映像を制作することで、スタッフの知識を高められるだけでなく、クリニックのブランディング向上に繋げることも出来ます。
セミナー形式の映像では、一方的に説明をするのではなく
パワーポイントで重要な用語の説明や、画像の使用をおこない視聴者が飽きない工夫が必要です。
スタッフ採用に繋がる動画コンテンツ
スタッフ採用を視野に入れた動画コンテンツを制作することで求人に繋げることも可能です。
通常の求人情報ではクリニックで働く内容を理解出来ても、どのような職場なのか文章や写真だけでは伝わらないことがあります。
現場で働くスタッフの様子や、インタビュー映像を制作すると、現場で働くスタッフの人物像が見えやすくなり応募の後押しをすることが可能です。
スタッフを募集する動画を制作する際には、動画を視聴したユーザーが求人募集に対して応募をするように、導線を検討しながら映像コンテンツを制作しましょう。
スポーツ医療の分野で制作されたPR動画事例
スポーツ医療分野で制作されているPR動画にはどのようなものがあるのでしょうか。実際に制作された動画を元に、優れている点や制作時に参考にすべきことを解説しましょう。
サービス紹介(八王子スポーツ整形外科)
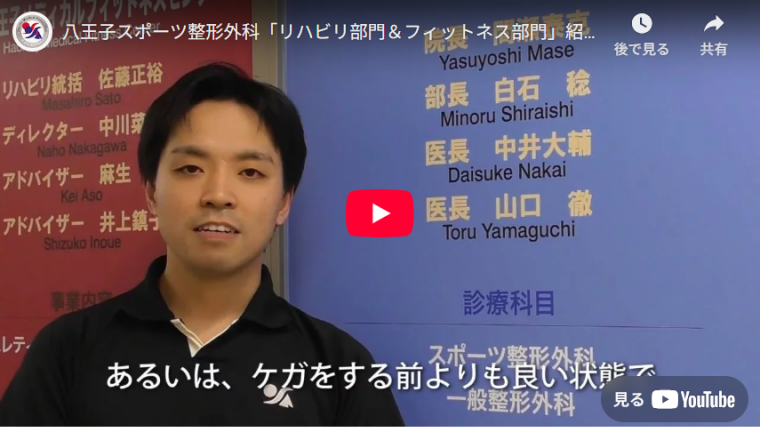
八王子スポーツ整形外科では、通常の治療だけでなく、運動のパフォーマンスを向上させたいアスリートに向けた治療も提供しています。
クリニックの魅力を伝えるため、3分の動画でクリニックのスタッフ、設備、治療内容を分かりやすく解説しているところが他のPR動画に比べて優れています。
施設を紹介する際には動画を視聴したユーザーが、サービスの内容を把握出来るよう、紹介する情報の中か反映すべき内容を精査するように心がけましょう。
魅力的な動画コンテンツを制作するだけでなく、映像を視聴したユーザーがクリニックへ問い合わせを出来るような導線も必要です。
トレーニング紹介

タケダクリニックの動画では、スポーツ医療でおこなわれるトレーニングがどのようなものかを紹介しています。
動画ではたけだクリニックが実際に導入しているラダートレーニングの方法を簡単に解説しています。
動画を視聴したアスリートが実際に取り入れる事ができるように、定点カメラを活用して視覚的に分かりやすく表現をしている点も他のコンテンツに比べて優れています。
動画概要欄では、動画で説明出来なかった情報を補足説明として解説し、動画を見た視聴者が間違ったトレーニングを実施しないよう配慮しながらコンテンツを制作しています。
セミナー形式動画(encounter)

スポーツに関わる人達に向けて、医療情報を分かりやすく紹介するencouterでは、スポーツ医療現場で知るべき情報をセミナー形式の動画で紹介しています。
動画では、運動で使う筋肉にフォーカスし、エコー映像などを用いて筋肉の特徴や働きを分かりやすく解説しています。
動画は10分と短時間にまとめ、視聴者が隙間時間で学習出来るような試みもおこなっています。更に、YouTubeのチャプター機能を活用し、動画の中で反復学習が出来るよう工夫をしています。
セミナー形式の動画を制作する際には、視聴者が映像を何度も見ることを視野に入れて、分かりやすい映像コンテンツを制作しましょう。
学科紹介(帝京大学)

医療スポーツを学べる「スポーツ医療学科・健康スポーツコース」を持つ帝京大学では、どのような学部なのかを紹介する映像コンテンツを制作しています。
医療スポーツの専門学校や大学では、各学校でどのような分野のスポーツ医療を学ぶ事ができるのか、卒業後の進路などを学生向けに発信するコンテンツも有効です。
大学や専門学校だけでなく、整体院やスポーツ医療を提供するクリニックなどでも、スタッフ採用に向けた映像を制作出来ます。
ターゲットに合わせた情報を分かりやすく紹介する
PR動画を制作する際には、一方的に有益な情報を発信するのではなくターゲットに合わせたコンテンツの制作が必要です。
動画コンテンツの制作時に必ず動画を誰に向けて発信をするのか、ペルソナを設定するようにしましょう。
ペルソナに響くコンテンツを制作すれば、視聴者の満足度を高めサービスの利用に繋げることが可能です。
動画を制作する際には、視聴者にとって有益な情報は何かを精査してコンテンツを制作することを心がけてください。
まとめ
・視聴者に有益な情報を発信する
・正しい情報を反映しているのかを確認する
・映像コンテンツを継続的に発信
本記事で紹介した動画事例を参考に、視聴者に響く動画を制作しましょう。
動画制作のノウハウが無く、ハードルが高いと感じている方は、動画制作を支援するツールの活用がおすすめです。
メディア博士は簡単なSTEPで動画制作を可能にする制作支援ツールです。ご自分で撮影した映像素材から、PRに活用出来る訴求力の高いコンテンツ制作が出来ます。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。