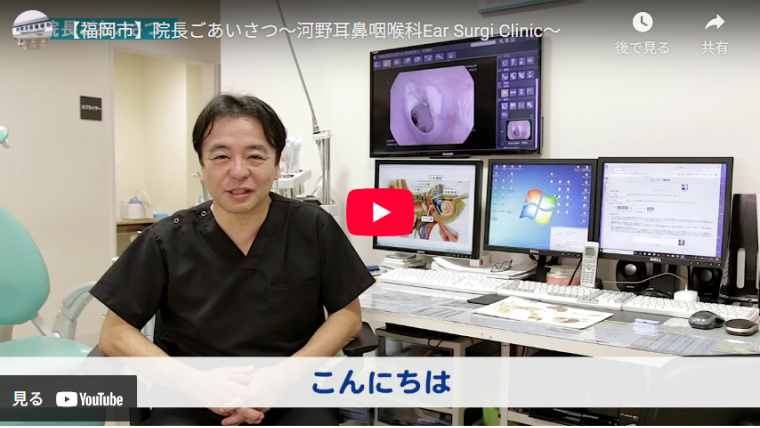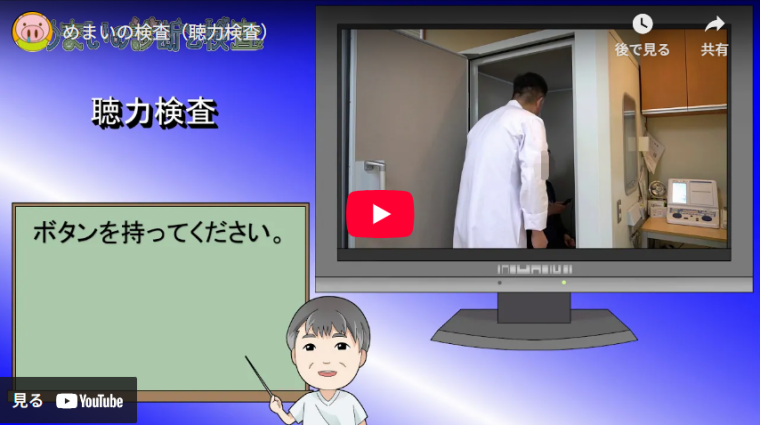耳鼻咽喉科が動画を活用すべき理由
耳鼻咽喉科が他院との差別化を図るうえで注目されているのが「動画」の活用です。ここでは、耳鼻咽喉科が動画を活用すべき理由を具体的に解説していきます。
患者の不安や疑問を動画で解消できる
耳や鼻、喉の症状は、他人には相談しづらく、かといって緊急性が明確でないケースも多いのが特徴です。そのため、「病院に行くほどではないかも」「何科を受診すべきか分からない」という迷いを抱える方が少なくありません。
こうした患者のために、診察内容や症状別の対処法などを動画でわかりやすく発信すれば、病院選びの不安を解消することができます。
また、診療科の専門性を伝えるには、文章だけでは限界があります。動画であれば、医師の説明とともにリアルな映像を届けることが可能です。これにより、患者の安心感が大きく高まり、「ここに相談してみよう」と一歩を踏み出すきっかけになるのです。
医療の信頼性と透明性を高める
耳鼻咽喉科に限らず、医療機関は「安心して任せられるか」が来院の判断基準となります。その点、動画は情報の信頼性や透明性を高めるのに最適です。
例えば、院内の清潔感や設備の充実ぶり、受付や看護師の対応など、細かい部分まで視覚的に訴求することで、見る人の印象が大きく変わります。
さらに、医師やスタッフが実際に登場して自己紹介や想いを語ることで、より人間味が伝わりやすくなります。これが、初診患者の心理的ハードルを下げ、「ここなら話しやすそう」と感じてもらえるきっかけになります。
小さな差が大きな差に変わる「選ばれる理由」になる
耳鼻咽喉科は専門診療であるがゆえに、治療内容や費用に大きな差が出にくく、患者側から見れば「どこも似ている」という印象になりがちです。
動画であれば、病院のコンセプト、診療方針、得意とする症例、院長の人柄など、「言葉では伝えにくい魅力」を自然に伝えることができます。
例えば、「キッズスペース完備」「女性医師が在籍」「補聴器外来に特化」など、特色を丁寧に伝えることで、患者が「ここは自分に合っていそう」と感じる確率が高まります。こうした差別化は、地域に複数の耳鼻咽喉科がある場合、患者の選択に大きな影響を与えるのです。
継続的な患者との関係構築にもつながる
耳鼻咽喉科は、再診や定期的な通院が必要となるケースも少なくありません。動画を活用して季節ごとの健康情報や自宅でのセルフケア方法などを発信すれば、患者とのタッチポイントを維持することができます。
また、YouTubeやSNSで動画を継続的に配信することで、「地域の健康情報を発信してくれる身近な存在」として認識されやすくなります。
これにより、病院と患者との距離感が縮まり、再来院や家族・知人への紹介にもつながりやすくなるのです。
耳鼻咽喉科におすすめの動画活用法6選
耳鼻咽喉科が集客のためのマーケティングに動画を活用する場合、その活用の仕方にはさまざまな方法があります。
ここでは、それらの方法の中でも特に高い効果の見込める6つの動画の活用法を紹介していきます。
取り入れられそうな活用法があれば、ぜひ参考にしてみてください。
病院の紹介動画
耳鼻咽喉科が集客に動画を活用したいと考えた場合、まず用意するべきなのが病院の紹介動画です。
最近は病院を訪れる患者がパソコンやスマートフォンを使い、事前に病院の評判をチェックしてから来院する時代へと変化してきています。
Webサイトを用意したりポータルサイトに登録するなどWebを活用している病院も少なくないかとは思いますが、ライバルに差をつけるのであれば病院を紹介する動画も用意しておくべきです。
病院の歴史や設備、受けられるサービスや病院までのアクセス方法など、ユーザーが必要としている情報を一つの動画にコンパクトにまとめて来院をうながしましょう。
施設や院内の設備の紹介動画
耳鼻咽喉科を利用したいと考えている患者の中には、
・清潔感を感じられる病院かどうか
・最新の設備が取り入れられている病院かどうか
・待合室や駐車場などの設備が整っているかどうか
など、その病院がどういった施設かを気にしている方もたくさんいます。
病院には清潔感が求められるため清潔感の感じられる病院を利用したいと考えるのは当然ですし、設備の古い病院よりも最新の設備が取り入れられている病院の方を利用したいと考えるのも当然です。
施設や院内の設備については画像やテキストよりも動画を活用して伝えた方が伝わりやすいので、施設や院内の設備を紹介する動画を作り、公開するようにしましょう。
病院で受けられるサービスの紹介動画
耳鼻咽喉科が動画を活用するのであれば、病院で受けられるサービスを紹介する動画についても制作しておくべきです。
忘れずに紹介しておきたいのが受けられる診察の内容についてです。
導入されている設備は病院によって異なるため、どういった診察を受けられるかについても病院によって異なります。
病院についた後で目的の診察を受けられないことが判明してしまった場合、患者の満足度が低くなり、今後利用されなくなってしまう可能性があります。
そういった機会損失につながるケースをなるべく少なくするためにも、どういったサービスが受けられるのかについてはしっかりと動画で伝えておくべきだと言えるでしょう。
また、サービスが充実している病院の場合、動画を通してそのことを伝えられれば、より多くの患者の集客につなげることもできます。
病院で働く医師やスタッフ紹介動画
地域に病院が多くなり、受けられるサービスの内容や導入されている設備での差別化が難しくなってくると、病院で働く医師やスタッフで通う病院を選ぶ患者が多くなってきます。
耳鼻咽喉科で受けられる診察は保険の対象となっており、診察にかかる費用での差別化もできないため、どうしても医師やスタッフが差別化のポイントになってきてしまうわけです。
そこで用意しておきたいのが医師やスタッフの紹介動画です。
病院で働く医師やスタッフの人となりがわかる動画を用意し、公開することで、初めての患者がより来院しやすくなります。
耳・鼻・口の健康に関する知識系動画
病院に行くほどの緊急性は感じていないものの、「耳や鼻、口の状態に少し違和感を感じている」という方は少なくありません。
空気が乾燥し、感染症に感染しやすくなる冬の時期となればなおさらです。
そういった方に向けて用意しておきたいのが耳・鼻・口の健康に関する知識系の動画です。
専門家が語る健康系の動画は需要が高く、集客に大きく貢献してくれます。
その動画を見た患者がすぐに来院してくれる可能性はそれほど高くありませんが、良質な動画をアップしておくことで将来の来院につながる可能性が高いので、ぜひ用意しておくようにしましょう。
病院を利用したユーザーへのインタビュー動画
他のユーザーの声や意見は、どの病院を利用するかで迷っている患者の背中を押してくれます。
そこで用意しておきたいのが、病院を利用してくれたユーザーへのインタビュー動画です。
訪れた患者さんに病院や診察の内容、サービスなどについてインタビューし、その内容を公開しましょう。
ネガティブな意見はユーザーを遠ざけるだけなので、ポジティブな意見の多いインタビュー動画になるよう、実際に利用してくれた患者さんにいい病院だと感じてもらえるだけの良質なサービスを提供する必要はありますが、そこをクリアできれば大きな集客効果を発揮してくれるはずです。
実際に動画を活用している耳鼻咽喉科の活用事例3選
耳鼻咽喉科が集客方法の一つとして動画を取り入れる際、ぜひ参考にしてほしいのが、すでに動画を活用している耳鼻咽喉科の活用事例です。
すでに動画を活用している耳鼻咽喉科の活用事例をチェックすれば、具体的に動画をどう活用すればいいのかが見えてきます。
特に参考になりそうな3つの活用事例を紹介していきます。
坂井耳鼻咽喉科

愛知県の春日井市にある「坂井耳鼻咽喉科」。
坂井耳鼻咽喉科はYouTubeに公式のチャネルを解説し、集客に活用しています。
こちらの動画は、坂井耳鼻咽喉科で利用できるWeb診察のサービス紹介動画です。
どういったサービスで、実際に利用する際はどのようにして利用すればいいのかについて動画で詳しく解説されています。
病院で受けられるサービスについて紹介する動画を制作するときに参考にしたい動画の一つです。
河野耳鼻咽喉科
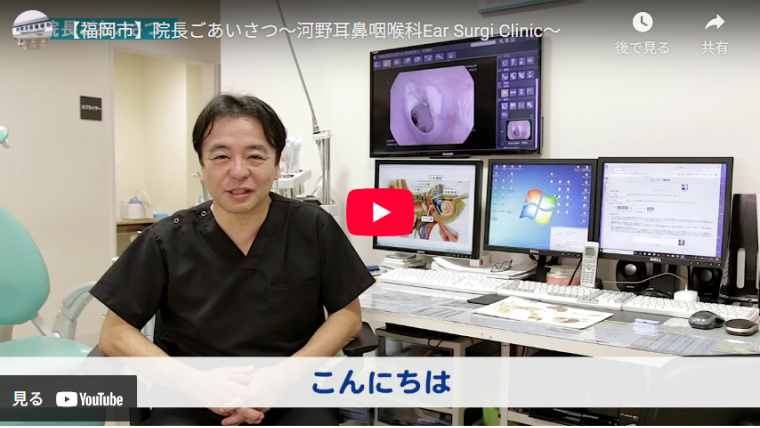
福岡市の中央区にある「河野耳鼻咽喉科」。
こちらの動画は、そんな河野耳鼻咽喉科の公式YouTubeチャンネルに公開されている病院の紹介動画です。
一般的な病院の紹介動画とは異なり、院長自身が病院について紹介するタイプの珍しい病院紹介動画となっています。
この動画の形式であれば、院長の紹介もかねながら病院の紹介が可能です。
いずはら耳鼻咽喉科
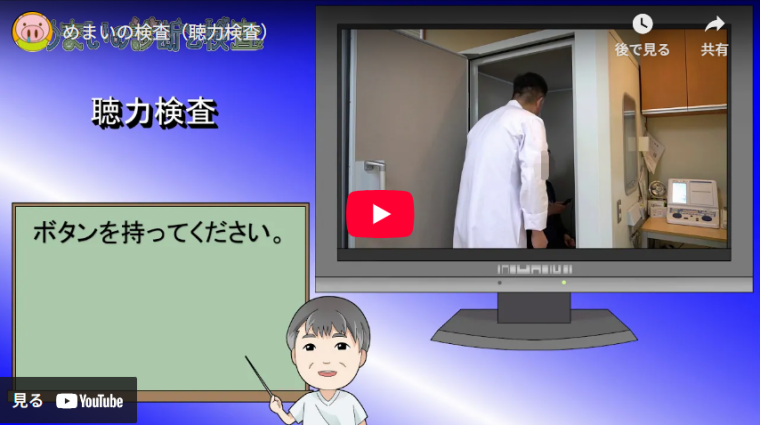
岐阜県各務原市にある、めまい専門医が在籍する耳鼻咽喉科「いずはら耳鼻咽喉科」。
いずはら耳鼻咽喉科も集客に動画をうまく活用している耳鼻咽喉科の一つです。
こちらの動画はめまいについての診察を受ける際におこなわれる検査の一つである聴力検査の流れについて解説している動画で、映像とナレーション、テキストをまじえながらわかりやすく解説しています。
どういった検査が受けられるのかだけでなく、実際に検査をおこなう際の流れまで事前に確認できるため、患者さんは不安を解消した状態で来院できるようになっています。
まとめ
実際に動画を活用している耳鼻咽喉科の事例に触れながら、耳鼻咽喉科におすすめの動画の活用法について紹介してきました。
動画は今最も注目されている集客方法で、業界を問わず活用されています。
しかし、耳鼻咽喉科を含む医療業界だと、動画を有効的に活用できているところはまだそれほど多くありません。
その状況は逆にチャンスでもあり、今から動画を活用し始めればライバルに大きな差をつけられる可能性が高いということにもなります。
今回紹介した活用法の中で取り入れられそうなものがあれば、ぜひ取り入れ、動画の活用に力を入れてみてはいかがでしょうか?