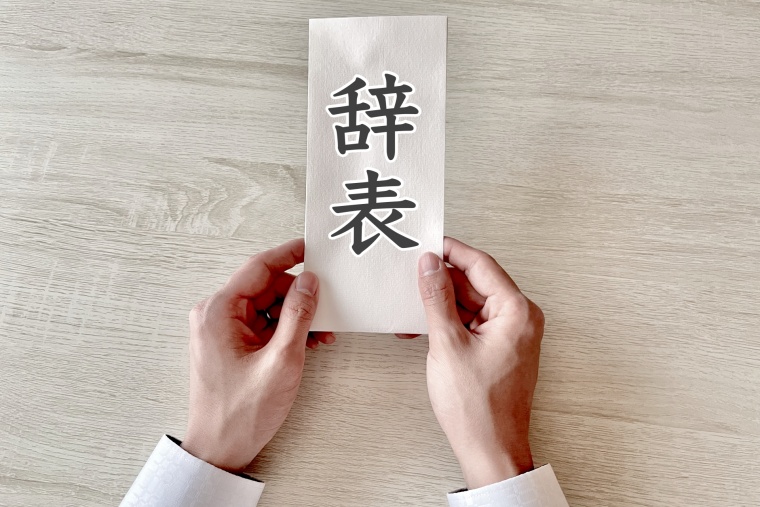企業の離職率はどれくらい?
離職率を下げるための対策をし始めるのであれば、まずは自社の離職率が高いかどうかについて正しく把握しなくてはいけません。
そこで参考になるのが、国内の企業における平均的な離職率と業界別の離職率です。
それぞれ詳しく解説していきます。
日本の平均離職率
国内企業全体における平均離職率は、厚生労働省が公表している「雇用動向調査」で確認することができます。
雇用動向調査の令和5年版によると、日本の平均離職率は「15.4%」となっています。
つまり、自社の離職率が15.4%よりも高くなってしまっている場合は、離職率を下げるための取り組みが必要になると言えるわけです。
業界別の離職率
離職率をチェックする場合は、日本の平均離職率だけでなく業界別の離職率についても確認しておくようにしましょう。
なぜなら、離職率の低い業界と高い業界とでは、離職率の値が大きく異なるからです。
以下は、同じく「雇用動向調査」で公表されている代表的な業界の離職率です。
| 業界 |
離職率 |
業界 |
離職率 |
| 鉱業 |
9.2% |
不動産 |
16.3% |
| 建設 |
10.1% |
宿泊 |
26.6% |
| 製造 |
9.7% |
生活関連サービス |
28.1% |
| インフラ |
10.4% |
教育 |
14.8% |
| 情報通信 |
12.8% |
医療 |
14.6% |
| 運輸 |
10.3% |
複合サービス |
7.8% |
| 小売 |
14.1% |
金融 |
10.5% |
離職率は業界によってこれだけ差が生じるため、日本の平均的な離職率と比較するのと同時に、自社と同じ業界の離職率についてもきちんとチェックする必要があります。
企業の離職率が高まる原因
離職率を下げたいのであれば、社員が会社を去っていく原因に目を向ける必要があります。
企業の離職率が高まる5つの主な原因について解説していきます。
給与が低い
離職率を高める大きな要因になりやすいのが、給与の低さです。
おこなっている仕事の割に給与が低かったり、仕事の内容に関係なくそもそもの受け取れる給与が低かったりすると、従業員は仕事を続けたい・頑張りたいと思わなくなり、転職を考え始めます。
福利厚生が充実していない
給与と同じく働いた対価として受ける権利を得られる福利厚生ですが、福利厚生が充実していない場合、離職につながってしまいかねません。
給与が多少低くても福利厚生が充実している職場は離職率を抑えられている傾向にあります。
一方、給与が低い上に福利厚生が充実していなかったり、給与は平均的でも福利厚生の恩恵を受けられない・受けにくい職場は離職率が高くなってしまいがちです。
成長する機会が用意されていない
全社員がそう考えているというわけではありませんが、経営者が考えている以上に向上心の強い社員はたくさんいます。
なぜなら、成長することでよりやりがいのある業務に携わることができたり、出世によって給与に反映される可能性が高いからです。
しかし、社員が成長できる機会を設けられていない企業は多く、そういった企業は離職率が高い傾向にあります。
仕事とプライベートを両立できていない
「ワークライフバランス」という言葉が出てくるほど仕事とプライベートを両立できるかどうかを重要視している従業員はたくさんいますし、今の時代、両立できるのが当たり前です。
しかし、両立できない職場や両立しづらい職場も少なくありません。
そういった職場だと、どちらかを諦めなくてはならなくなってしまうため、両立できる職場を求めて離職していってしまいます。
職場の人間関係がうまくいっていない
人間関係は、職場の悩みに関するアンケートにおいて毎回上位になる定番の悩みです。
その悩みが大きくなり、解決するのが難しくなってしまうと離職してしまう可能性が高くなります。
企業の離職率が高まることで生じるリスク
離職率が高い状態は、長期的に見れば企業の成長や安定的な経営に大きな影響を及ぼす深刻なリスクとなります。ここではその代表的なリスクを解説していきます。
生産性の低下
離職が増えると、業務に精通した人材が失われ、その分の穴を他の社員が埋める必要が出てきます。結果として一人あたりの業務負担が増え、残業や長時間労働が常態化しやすくなります。
さらに、新たに採用した社員が業務に慣れるまでには時間がかかるため、短期的にも長期的にも生産性が落ち込むのが現実です。
特に専門性の高い職種や長期的な経験の蓄積が必要な部門では、即戦力の喪失が致命的な影響を与えるケースもあります。
組織文化の停滞・崩壊
企業独自の価値観や文化は、社員が継続的に在籍し、日常の中で共有・蓄積されることで形成されます。しかし離職率が高いと、ノウハウや文化の継承が途切れ、組織全体に一体感が生まれにくくなります。
さらに「また同僚が辞めた」という心理的な影響が残る社員に広がれば、モチベーションの低下を招き、組織の結束が弱まります。結果として、企業の強みである文化そのものが形骸化し、組織の活力を失ってしまう恐れがあります。
顧客満足度の低下
人材の入れ替わりが頻発すると、顧客や取引先との信頼関係が築きにくくなります。
特に営業やカスタマーサポートのように顧客接点の多い部門では、担当者の変更が続くと「前任者との約束が引き継がれていない」「対応の品質が不安定」といった不満が生じやすくなります。
その結果、顧客満足度が低下し、最悪の場合は競合他社への乗り換えや契約解除といった形で売上に直結するリスクを抱えることになります。
採用市場での企業イメージ悪化
近年はSNSや口コミサイトの普及により、企業の評判が外部に伝わるスピードが非常に速くなっています。
離職率の高さは「働きにくい会社」「定着しない職場」といったマイナスの印象を持たれやすく、求職者からの応募が減少する要因となります。
結果として採用活動が難航し、優秀な人材を確保できず、さらに人手不足が加速するという悪循環に陥る危険性があります。人材獲得競争が激化する今の市場において、イメージ低下は致命的なダメージになりかねません。
企業の離職率を下げる方法7選
離職率が高まる原因を把握することができたら、それらの原因に対処するための方法を把握しましょう。
把握できたら、その方法を実践していけば企業の離職率は改善されるはずです。
企業の離職率を下げる7つの方法について解説していきます。
アンケートを実施する
先ほど主な離職率が高まる原因を紹介してきましたが、従業員がどこに不満を感じてるかはそれぞれの企業によって異なります。
また、経営者がそのことに気づけていないケースがほとんどなので、まずはアンケートをとり、どこを改善するべきかを把握しなくてはいけません。
アンケートをとらずに思い込みや思いつきだけで対応を進めてしまうと対策自体が失敗に終わってしまいかねませんので、必ずアンケートをとるところから始めるようにしてください。
給与を見直す
アンケートの結果、給与に不満を感じている従業員が多いことが判明したら、給与を見直さなくてはいけません。
同じ業界の企業と比べて給与水準が低いのであれば最低でも同じ水準まで見直さなければ人材の流出は防げません。
人材の流出を防ぎつつ、より優秀な人材を確保したいのであれば同業他社より給与を高めに設定しましょう。
福利厚生を見直す
給与に不満を感じている従業員が多い場合は給与を見直すべきだと紹介してきましたが、「会社の経営状況的に給与を見直すのが難しい…」というケースもあるかと思います。
その場合は福利厚生の部分を見直すようにしてください。
福利厚生が充実すれば給与が低くても多少であれば目をつぶってもらえますし、「給与の水準が多少高くなるよりも福利厚生が充実している方が嬉しい」という人もたくさんいます。
給与水準の見直しが難しい場合は福利厚生を充実させることで離職を思いとどまってもらいましょう。
成長する機会をあたえる
「若い社員が成長する機会を充分にあたえられていないな…」と感じるのであれば、成長するチャンスを用意できる仕組みづくりに取り組みましょう。
研修を充実させるのもいいですし、新しいプロジェクトを始めるときに未経験の若い世代に参加を促してみるのもおすすめです。
勤怠状況見直す・管理する
プライベートに影響が出てしまうほど残業が常態化してしまっている場合は、勤怠状況の見直しと管理が必要です。
従業員の数が足りていない場合は人を雇い入れるべきですし、効率が悪い場合は日々の業務を効率化しなくてはいけません。
有給を取得しやすい環境を整えるなどの対応も進めていきましょう。
人間関係についてヒアリングして対策する
人間関係の悩みを解決するにはヒアリングをおこなうしかありません。
悩みを聞いてあげるだけで楽になるケースは少なくないので、相談できる環境を整えてあげましょう。
採用動画を用意してイメージとの乖離をなるべく無くすようにする
離職してしまう人の中には、「思っていた職場や業務内容と違った…」という理由で離職してしまう人が結構な割合でいます。
その主な原因としては、求職者に対して業務内容やどういった企業なのかを正しく説明できていない点や紹介できていない点があげられるでしょう。
そういったイメージとのギャップをなるべく減らすためには、採用動画の活用がおすすめです。
動画には、テキストや画像で伝えるよりもイメージが伝わりやすくなるという大きなメリットがあります。
社員の一日に密着する動画や実際の業務内容を伝える動画などを用意しておけば、「イメージと違う」という理由での離職は一気に減るはずです。
まとめ
離職率が高くなってしまっていることに頭を悩ませている企業向けに、企業の離職率を下げる方法について紹介してきました。
国内の企業の平均的な離職率や業界ごとの離職率の平均と比較して自社の離職率が高くなってしまっている場合は、離職率を下げなくてはいけません。
平均値よりも離職率が高い状態は正常ではありませんし、このままだと健全な企業活動を持続することができなくなってしまう可能性もあります。
そのため、なるべく早いタイミングで離職率を下げるための取り組みをおこなうようにしましょう。
まずはアンケートを実施し、社員がどこに不満を抱えているのか探ってみるところから対応に着手してみてはいかがでしょうか?