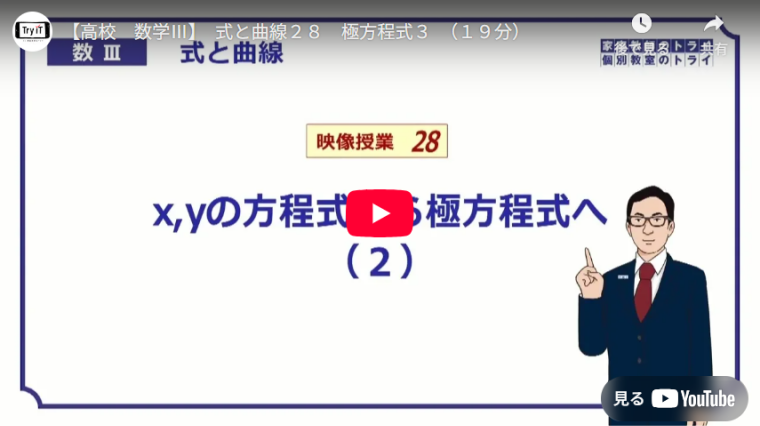この記事は、こんな方におすすめです
- ✅ 部門横断で「動画を使ったDX」を推進し、標準化・内製化の運用ルールまで整えたい
- ✅ 研修・営業・社内広報など複数ユースケースで動画を展開し、KPI(視聴完了率・再学習率等)まで一元管理したい
- ✅ 担当者の異動やリソース変動があっても、更新・配信・アクセス権限管理をクラウドで継続運用したい
▶ メディア博士の資料を見てみる
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
そもそもここ最近話題になっている「DX」とは何かについて解説します。
DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略で、デジタルの技術を活用し人々に浸透することで、あらゆる面でより豊かな生活が送れるように変革ができるものです。
2020年のコロナ禍初期では、オフィスで仕事ができなくなったためリモートワークが可能になるようなDXを推進していました。ハンコを廃止してデジタル署名に移行する点も、その事業の1つです。
今後、さまざまな面でDX化が進み、より豊かな生活を手に入れることができるでしょう。
DX推進を行うべき理由
なぜDX化を国を挙げて推進しているのでしょうか。推進する理由にはいくつかの理由があります。それぞれ解説していきましょう。
業務効率化
DX化が進むことで、私たちの業務が効率化します。今まで紙ベースで制作していた会議議事録はペーパーレスになることで、出力をする手間を省くことが可能です。
請求書制作も、デジタル上のやりとりでおこなうことができるので決済までの処理を簡素化できます。非効率であった業務を効率化することで、無駄な作業を減らし、他の作業に対応することが可能になります。DX化は業務を改善するうえでも必要なものなのです。
日本経済の損失
日本経済は現在、深刻な課題に直面しています。平均賃金では韓国に追い抜かれ、デジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れが経済成長の大きな障壁となっています。
特に、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」は、レガシーシステムの老朽化や、IT人材の不足により、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています。
このような状況下で、DXの推進は急務です。しかし、多くの企業がDX人材の不足や既存システムの複雑化といった課題に直面しており、全社的な戦略の欠如も問題視されています。
今後、日本が国際競争力を維持・向上させるためには、DXの加速とともに、IT人材の育成や既存システムの刷新が不可欠です。これにより、経済の持続的な成長と新たな価値創出が期待されます。(参考:ノムラシステムコーポレーション 経産省DXレポートの「2025年の崖」とは?問題点や対策をわかりやすく解説より)
事業継続計画を可能にするため
日本は感染症だけではなく、地震、洪水などの災害が頻繁に発生します。DX化が進めば、一部企業の中でも災害時でもスムーズにやりとりができ事業の効率化が可能です。
重要な書類を災害で紛失してしまった場合でも、デジタル上にデータが保存していれば復旧が可能で、以前の状態で業務を行うこともできます。
震災が発生したことで、物理的に業務を遂行することが難しい業種もありますが、DX化をすることで対策できることが増えるでしょう。
新たなイノベーションを起こす
DX化を進めることで、企業の業務効率化が進み、新たな技術革新を起こす可能性があります。NetflixやHuluのようなVODのようなネットコンテンツの拡充や、Spotify、Podcast音声配信サービスなど、これまでに注目されていなかったビジネスがここ数年誕生しています。
今後さまざまな分野でイノベーションが起きる可能性もあるでしょう。
動画を用いたDX推進のメリット
動画を用いたDX推進をおこなうことで、企業は仕事の進め方そのものをアップデートできます。具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。
情報発信の最適化
動画を用いることで、発信者の情報を届けたいターゲットに発信することが可能です。
以前は新商品情報を発信する場合、ポスティング、テレビCMなど非効率な発信方法をしていました。新商品の情報をWEB動画広告であれば、特定のターゲットにのみ表示されるように設定することも可能です。
SNSマーケティングと合わせておこなえば、どのSNSプラットフォームへの発信が最適かも予想することができます。さらに、動画はテキストに比べて3倍以上の情報発信が可能で、短時間で伝えたい情報を効率よく発信することもできます。
動画を用いることで、従来の方法に比べて効率よくユーザーに伝えたい情報を発信することができるでしょう。
業務効率化
動画を活用することで、業務効率化をおこなうことが可能です。従来の紙媒体で共有していた資料を、動画に置き換えることで情報を均一にすることができます。
研修に参加できなかった社員に研修資料を共有する場合、従来の紙資料の共有方法では受け手の理解度によって大きく左右されていました。その結果、研修内容が共有されないまま業務が行われ、トラブルが発生してしまうこともあります。
トラブルが発生してしまうと、再度研修を社内で実施したり、研修内容の見直しを検討せざるを得ません。
研修資料を動画にすることで、伝えたい情報を分かりやすく受け手に伝えることができるため、トラブルのない情報共有が可能です。
動画のDX化は情報の均一化だけではありません。動画をWEB上にアップロードすることで、社員が好きな時間、好きな場所からアクセスができます。
電車の移動時間や打ち合わせの合間など、隙間時間でも資料に目を通すことができるのでおすすめです。
知識資産の蓄積
動画によるDX推進を行うことで、組織の知識を資産化することができます。
ベテラン社員のノウハウ、成功事例の共有、操作手順、研修内容など、企業内に散らばる貴重なナレッジを動画の形で蓄積することで、社内の知識の断絶を防ぐことができます。
また、動画コンテンツは一度作って終わりではなく、改善やアップデートが容易です。新機能の追加や業務フローの変更があった際も、該当箇所のみ撮り直して差し替えればよいため、マニュアルを毎回作り直す必要もありません。
さらに、動画配信プラットフォームを活用すればさまざまなデータも取得できます。これらのデータは、業務改善や教育体制の見直しに活用でき、DX推進の改善サイクルを回す重要な指標になります。
動画を用いたDX推進のデメリット
動画はDX推進に大きな効果を発揮する一方で、準備や運用の設計を誤ると、かえって現場の負担が増えたり、DXそのものへの不信感を招いてしまうケースもあります。具体的にどのようなデメリットがあるのかを解説します。
初期コスト・制作工数が膨らみやすい
動画をDXの中心に据えようとすると、企画・撮影・編集・配信環境の整備など、多くの工程が必要になります。
外部制作会社に依頼する場合は制作費が、内製化する場合は機材や人件費、教育コストが発生し、「思っていたより費用も時間もかかる」という声が上がりやすいポイントです。
特にDXプロジェクトの初期段階では、どのレベルのクオリティが本当に必要なのか、どこまで内製し、どこから外注するのかといった線引きを明確にしないと、結果として投資対効果が見えにくくなってしまいます。
見られない動画が増える恐れがある
動画は情報量が多く、理解しやすい一方で、「環境が整っていて初めて機能するコンテンツ」です。
現場によっては、PCのスペックが低く再生が重い、社内ネットワークが遅くスムーズに視聴できない、音声を出せない現場が多い、といった理由から、せっかく作った動画が十分に活用されないケースも少なくありません。
さらに、動画配信プラットフォームの使い方が浸透していないと、「どこからアクセスすればいいか分からない」「検索しても目的の動画にたどり着けない」といった不満が生まれ、DX施策への抵抗感につながってしまいます。
これらの状況を避けるには、環境差を前提にした設計を行うことが重要です。
作ること自体が目的化してしまう
動画を用いたDX施策は、開始直後こそ社内外の反応が得られやすく、手応えを感じやすい取り組みです。
しかし、視聴回数や再生時間などのデータを追わずに運用を続けてしまうと、「作ること自体が目的化する」という落とし穴にはまりがちです。
例えば、研修動画を大量に用意しても、どの動画がよく視聴されているのか、視聴後に業務ミスが減ったのかなどを検証していなければ、改善の方向性が見えず、現場からも「本当に意味があるのか」と疑問を持たれてしまいます。
DX推進の観点では、動画視聴のログやアンケート結果を継続的に分析し、「どのテーマを増やすべきか」「どの内容はテキストの方が適しているか」といった判断材料にしていくことが不可欠です。
DXを考えた動画活用シーン
DXを動画として活用したシーンとして、具体的にどのようなものがあるのかについて解説していきましょう。
営業資料動画
営業担当者が共有する資料を、動画化することで商品・サービスを分かりやすく伝えることができます。Web上に共有することで、会議で簡単に情報共有をおこなうことも可能です。
営業中に、映像を停止しながら解説をおこなうことができるので、伝えたい情報を的確に訴えることもできます。
操作説明動画
機械・サービスの操作手順を紹介する動画を制作し、利用者に分かりやすく情報共有をおこなうことも可能です。実際の画面を元に操作方法を1つずつ紹介するので、ミスを防ぐことができます。
利用者向けに操作説明動画を制作することで、カスタマーサービスへの問い合わせ件数を減らし、スタッフの仕事内容を軽減することも可能です。
操作説明動画と相性の良いコンテンツは、デジタル機器の操作方法や、新サービスの紹介です。操作説明を活用して、ユーザーの顧客満足度を高めましょう。
プロモーションムービー
展示会、株主総会などイベントを企画する際に、プロモーション動画を制作することで企業のメッセージを参加者に訴えかけることが可能です。
プロモーションムービーをイベントの開催前に上映すると、イベントとしての演出も可能です。展示会で動画を活用すると、競合企業との差別化も期待できるでしょう。
商品のコンセプトを紹介するティーザー映像などがおすすめです。展示会や株主総会などのイベントで使用した動画は、SNSプラットフォームへの発信や、ホームページのトップページに掲載することもできます。
動画はさまざまな媒体に合わせたフォーマットで二次利用が可能なため、プロモーションムービーを制作してユーザーに向けて企業の思いを伝えましょう。
企業のDX推進事例
DXで成功するためには、成功事例の研究が必要です。以下では、企業の導入事例をいくつか解説し、導入時にどのようなことに注意をすれば良いのかについて解説します。
家庭教師のトライ
家庭教師のトライグループは、2015年に無料映像サービス「Try It」をリリースしました。従来のオンライン授業にあるような、講師による一方的な解説映像ではありません。
15分と映像を短くまとめることで、隙間時間でも気軽に視聴することができるメリットがあります。これまでに蓄積をしたノウハウがあるからこそ、動画コンテンツとしても有益なものとなり、多くの学生に支持されるサービスになりました。
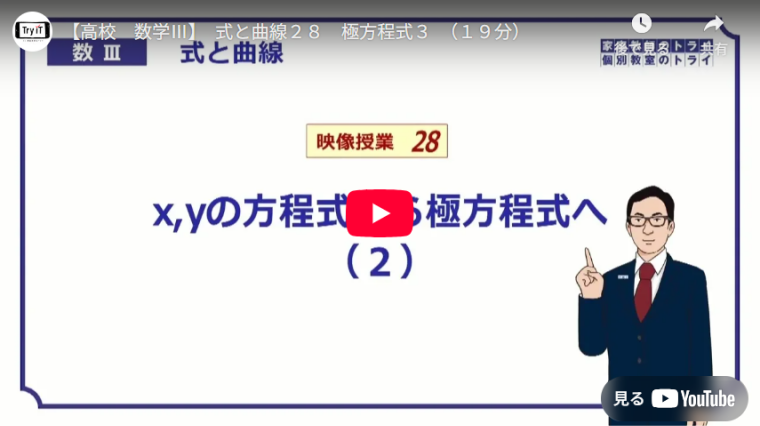
動画化する際には、利用者目線で動画の尺を設定しておきましょう。DX推進を成功するために大切なことは、「自社の強み」+「課題解決」です。
家庭教師トライのような動画コンテンツを制作する際の参考にしてください。
リコーのペーパーレス化サービスの導入
リコーが手がけるペーパーレスサービス「RICOH らくらく KIAZENサービス」は、技術情報をフォーマット化、データベース化するサービスです。
導入したことで、企業がどのような経緯で業務改善をおこなうことができたのかをYouTube動画で紹介しています。

本編では、DX推進に成功した企業、「東洋刃物株式会社」がどのような問題を抱えていたのか、サービスの魅力的なポイントを解説しています。
DX人材の採用促進とモノづくりの未来「村田製作所」
村田製作所は、DX推進を担う人材の確保を目的とした採用動画を公開しました。この動画では、同社の電子部品がラジオやテレビ、スマートフォンなど、身近な機器に幅広く活用されていることを紹介しながら、変化する時代のニーズに応じた技術革新の重要性を伝えています。
DXを推進する新たな視点を持つ人材が求められ、デジタル技術を活用して従来の製造プロセスを進化させることの必要性を述べています。

参考:youtube 【フルVer.】DX人材向け動画:ともに未来をつくるあなたを待っている
動画では、村田製作所が持つ長年の技術力と、DXを組み合わせることで生まれる新たな可能性を強調し、未来のものづくりに貢献したいと考える求職者に向けてメッセージを発信しています。
製造業のIoT活用によるデジタル化「東芝」
東芝は、製造業のDX推進を目的に、IoTとクラウド技術を活用した「ものづくりIoTクラウドサービス Meister ManufactX」を展開しています。
このサービスは、製造現場のIoTデータと、生産工程の品質や稼働状況のデータを組み合わせ、最適な分析と可視化を実現するものです。これにより、リアルタイムでの生産状況の把握が可能になり、トラブルの早期発見や業務の効率化を図ることができます。

参考:Youtube ”製造現場のものづくりDXとは” 「ものづくりIoT MeisterManufactX」紹介動画
動画では、東芝の技術がどのように工場の生産性向上や品質管理に貢献するかを具体的に説明し、製造業のデジタル化をサポートするソリューションとしての価値を強調しています。
建設業のDX推進による未来の働き方「大成建設」
大成建設は、建設業におけるDX推進の一環として、2030年の建設現場を描いた映像作品「the way we work.」を制作しました。この映像では、AIや現場管理システムを活用し、建設業のデジタル化が進んだ未来の働き方を紹介しています。
従来のアナログなイメージが強い建設業界で、DXを活用することで、より効率的で快適な作業環境を実現できることを発信しています。技術者や現場で働く人々の近未来、最新テクノロジーがどのように業務を支えるのかを具体的に示すストーリーが展開します。

参考:Youtube ショート版:大成建設、2030年の働き方DX動画「the way we work.」
この取り組みは、建設業のイメージ向上にもつながり、若い世代の関心を引くとともに、業界全体のデジタル化を推進する重要な役割を担っています。
DXをうまく進めるためのポイント
DXをうまく進めるためには、いくつか注意すべきポイントがあります。次の項目はうまく進めるために欠かせないポイントなので注意が必要です。
経営陣へDXへの理解を深める
DXを進める際には、経営陣のDX化への理解が必要です。DX化は単にデジタル機器の使用、サービスをデジタルへ移行するといったものではありません。
企業にとって、なぜDX化が必要なのか、DX化を導入することでどのようなメリットがあるのか具体的なイメージを描く必要があります。
具体的なイメージを共有することで、今までの業務の見直しが可能になり、企業をあげてDX化推進へと進めることが可能です。
経営陣への理解を得られないと、社内でのDX化に難色を示す社員もいるため浸透しません。DX化の必要性、DX化を進めるためにどのような施策を考えるべきか、具体的なプランを検討しましょう。
段階的にプロジェクトを進める
DX化で注意するべきことは、一度に進めるのではなく段階的に進めるようにすることです。段階的に進めることで、DX化が進むとどのように業務効率化が可能になるのか、サービスがどのように向上するのかを提示することが可能になります。
また、導入時にどのようなことを改善する必要があるのか、問題点をその都度整理することが可能です。一気に導入を進めてしまうと、業務が大幅に変わってしまうだけでなく、改善が必要な場合コストが膨大にかかってしまう恐れがあります。戸惑ってしまう場合もあります。
DXを進める際には、まずは業務に支障が出ないようなものから手をつけて徐々に導入をするようにしてください。
外部も巻き込んでDX化を進める
DX化を推進するためには、社内だけでなく、外部の担当も巻き込みながらプロジェクトを進めましょう。外部の人間を巻き込むことで、DX化を進める必要性を社内で共有でき、プロジェクトをより早く進めていくことが可能です。
外部を巻き込む際は、DX化に欠かすことができない取引先や、DX化に必要なサービスの営業担当者を巻き込みましょう。
長期的な視野でプロジェクトを進める
DX化は一気に進めるのではなく、長期的な計画で進めてください。1年後、3年後、5年後にどのようなものを導入するのか、中長期で目標を定めプロジェクトを進めていきましょう。
特に、顧客情報をはじめとした企業の根幹となるものは、一気にDX化を推進するのではなく、問題を1つずつ解決しながらトラブルのないように導入計画を進めてください。
DX化で気を付けること・失敗例
DX化を成功させるためにいくつか注意すべきことがあります。以下の項目は、特に失敗例として起きやすい問題です。
DX化を推進する中で、どのような問題が起きやすいのかについて解説します。
動画制作などDX化が目的になっている
最もよくある失敗例として、DXの導入=ゴールとなっているプロジェクトです。YouTubeチャンネルの例を元に解説をしましょう。
企業がYouTubeチャンネルを立ち上げて、従来のチラシで配布していた情報を動画化すると想定します。最初は動画制作をおこない、発信をしていたもののいつからか更新頻度がぴたりと止まり、そのまま数年以上も放置されている…。このようなYouTubeチャンネルを見たことがある方も多くいるのではないでしょうか。
上記のようなYouTubeチャンネルは、YouTubeチャンネルを立ち上げることが目的となってしまっていたため、具体的な戦略がなく、ただ動画を投稿しているだけになっていた可能性があります。
DX化もYouTubeチャンネル同様に、導入するための目的づくりが重要です。例えばAIやビッグデータを活用したサービスを導入する場合、明確な目的がなければ、ただ最先端のデジタルテクノロジーを導入しただけになってしまう恐れがあります。DX化が目的にならないように、注意をしながらDX化を進めていきましょう。
社内での理解不足
DX化を推進するうえでは、社内での理解が必要です。社内でDXに対する知識や理解が浸透していないと、「ウチは今までのやり方で十分」とプロジェクトに後ろ向きな意見が出てしまう恐れがあります。
部署内で意見の食い違いが発生すると、DX化を進める中で連携が取れずプロジェクトが遅れてしまう恐れがあります。
現場社員が導入への必要性を感じていても、経営陣がDXに対する理解が無い場合も、新たなプロジェクトを立ち上げようとしても認められないこともあります。
DX化は必要と感じている部署・チームだけで進めることは不可能です。プロジェクトの立ち上げとともに、DXの必要性を訴えかけるように心がけましょう。
DX化の活用事例をイメージしていない
DX化をしても、どのようにサービスを活用すればいいかイメージできないこともあります。イメージができていない状態で導入を試みても、サービスを十分に扱えない可能性があります。
さらに、業務改善など目に見える成果がなければ、「うちで導入しなくても良い」と判断されてしまう恐れがあります。
DX化をすることで、どのような業務改善が可能になるのか、どのようなメリットがあるのかをイメージできるようにしてください。
担当者でなければ操作方法がわからない
DX化を進める際に大切なことは、「どの部署の人間でも、簡単に利用できること」です。特定の社員のみしか扱えない場合は、DX化を推進しても担当社員のノウハウに依存をすることになります。
担当社員が退職をした場合や、病気などの理由で仕事ができない場合、別の人間がフォローできない問題があります。担当者だけがDXに関する情報を理解している状況は、DX化を進める中でも注意すべきポイントです。
社内の人間であれば、誰もが利用できるようにマニュアル等を作成して対処することをおすすめします。
動画によるDX推進を内製化する
動画を活用したDX推進では、「継続性」「動画制作の方法」「目的の設定」の3つのポイントが重要です。動画によるDX推進を内製化するために注意すべきポイントを紹介します。
継続性
ユーザーに向けて発信するコンテンツを制作する場合、最も重要になる要素は「継続性」です。動画によるDXの中でよくある失敗事例として、公開当初はコンスタントに動画を発信していたものの、ある時期を境に更新が途絶えてしまうものがあります。
動画は継続的に発信することが大切です。発信を継続的におこなうことで、新規ユーザーの獲得ができます。
継続的に動画コンテンツを制作しても、発信頻度に偏りがある場合も注意が必要です。無理のない更新頻度を設定し、動画を有意義な情報コンテンツにしてください。
動画の制作方法
動画制作は、企画構成、台本制作、撮影、編集とさまざまな工程を経て制作をおこなう必要があります。効率よく制作するために、チームで動画制作をおこないましょう。
チーム内に動画に関して知識のある経験者スタッフがいれば、動画の撮影、編集ノウハウを共有し制作することが可能です。
しかし、マニュアル化をしていないと担当社員が抜けてしまった時に、動画制作の体制がうまく作れない恐れがあります。
経験者が不在の状態でも滞りなく動画制作をおこなうことができるよう、社内担当の負担が大きい場合は外部クリエイターと連携を取りながらコンテンツを制作してください。社内での完全内製化を目指すのであれば、動画作成支援ツールの活用を検討してください。
目的の設定
動画が有効なコンテンツとして活用されるために、動画作成の目的を明確にしておくことも大切です。動画をどのようなプラットフォームに投稿し、ユーザーが視聴するのかを検討しましょう。
内製化をする際には、動画の目的を社内で共有し、目的を達成するためにどのような動画コンテンツを制作する必要があるのかを検討しましょう。
動画作成支援ツールの活用がおすすめ
動画制作の知識やノウハウが社内で蓄積されていない場合、低コストで動画制作を検討している方は動画作成支援ツールの活用がおすすめです。
動画作成支援ツールを活用することで、通常であれば制作に時間が必要な編集作業を大幅に短縮することができます。動画作成支援ツールを選ぶ際には以下の3つのポイントが大切です。
・サービスの操作性
・分かりやすさ
・実績
編集をしたことがない社員が実際に操作をしても直感的に扱えて、過去の実績が豊富なサービスがおすすめです。実績が豊富なサービスは、導入前にどのような方法で動画を活用できるのかを調べることができます。
スマホで撮影した動画を気軽に編集できるサービスもおすすめです。動画作成支援サービスをどれにすべきか分からない場合は、紹介したポイントを参考にしましょう。
まとめ
DX化はさまざまなコンテンツで導入され、今まで以上に急速に技術革新が進むことが予想されます。DX化を検討している企業の中で、動画を活用したサービスを検討している場合は動画作成支援ツールの導入がおすすめです。
メディア博士は3つのSTEPで動画を制作する支援ツールです。動画編集に慣れていない方でも、簡単に動画制作をおこなうことができます。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。