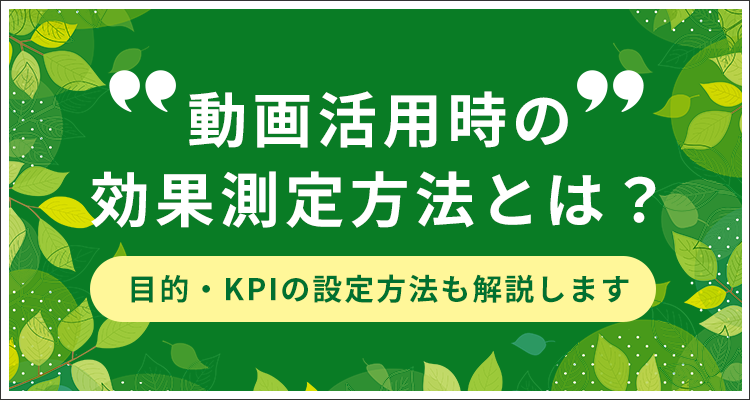この記事は、こんな方におすすめです
- ✅ 目的別(採用・営業・教育など)のKPI設計から測定・改善までを社内で回せる体制を作りたい
- ✅ 再生数ではなく、視聴維持率・クリック率・CVなど事業に直結する指標で動画の効果検証をしたい
- ✅ テンプレとダッシュボードで運用を標準化し、複数部門・複数拠点へ横展開したい
▶ メディア博士の資料を見てみる
動画マーケティング 効果測定の2ステップ
効果を測定する場合には、目的の明確化・KPIの設定という2ステップが必要です。それぞれどのように考えるべきなのか、詳細にご説明します。
目的を明確にする
まず、動画公開の目的は何なのか、明確にしましょう。商品やブランドについて知ってもらいたいのか、商品やブランドの価値を認識してもらいたいのか、もしくは、購入まで誘導したいのか、目的によって測定するべき指標が変わってくるのです。
動画マーケティングの目的として設定されることの多い、主な3つをご紹介します。
 ① 商品・ブランドの認知拡大
① 商品・ブランドの認知拡大
企業の場合、認知拡大を目的として動画を活用するケースが最も多いでしょう。動画は、静止画よりも短時間で多くの情報を伝えられるため、商品やブランドについて端的に分かりやすく説明できます。
また、視覚・聴覚に訴えることで視聴者の記憶に残りやすい特徴もあります。視聴者に強い印象を与え、共感を得られれば、拡散効果も期待できるでしょう。このような特徴により、動画は認知拡大を目的とした施策に向いているツールと言えるのです。
② 商品の売上促進
動画内で商品の魅力を訴求し、視聴者へ購入を促すことで、売上促進に繋がります。ECサイトに商品紹介動画を掲載することも効果的でしょう。動画の説明欄やECサイトには、商品の購入ページへ繋がるURLを掲載し、動画を見て興味を持った視聴者がすぐに購入できる導線を作ることが重要です。
情報伝達力の高い動画を活用することで、商品をより詳しく訴求できるうえ、購入ページへスムーズに誘導できるので、売上促進効果が期待できるのです。
③ ブランディング
商品やブランドのイメージは、なかなか文章で伝えてもお客様に伝わりづらいことがあります。
一方動画は、視覚・聴覚に訴えるため、世界観などの抽象的な概念が表現しやすいのです。言葉や画像だけで説明した場合、受け手によって抱く印象が変わる可能性がありますが、動画を活用すれば、企業の意図したイメージがそのまま伝わりやすくなります。
ブランディング動画によって、お客様のブランドロイヤリティを向上させることができれば、ブランド離れを防いだり、リピート率を高めたりする効果があるでしょう。
KPIを設定する
動画の目的を定めたら、その目的に合わせてKPIを設定しましょう。KPIとは、目的への達成度合いを計測するための定量的な指標のことです。動画制作の目的に応じたKPIの例をそれぞれご紹介します。
 ①「目的:商品・ブランドの認知拡大」の場合
①「目的:商品・ブランドの認知拡大」の場合
ブランドや商品の認知度を広めることを目的としているため、「動画をどのくらい多くの人に見てもらうことができたのか」を図るためのKPIを設定しましょう。
<KPIの例>
・再生回数:動画が再生された回数
・ユニークユーザー:動画を視聴した人数
・認知度:動画視聴前後の認知度を調査
動画を広告として使用する場合は、インプレッション(動画広告が画面上に表示された回数)や、クリック数動画広告がクリックされた回数)も計測するといいでしょう。
②「目的:商品の売上促進」の場合
動画を見てもらうだけでなく、視聴後「購入」というアクションを起こしてもらう必要があるため、その部分を図るためのKPIを設定しましょう。
<KPI例>
・コンバージョン数:設定したコンバージョンの合計数
・CVR:訪問数のうち、コンバージョンした数の割合
・購入意向度:動画視聴前後の購入意向を調査
③「目的:ブランディング」の場合
動画を長時間しっかりと見てもらうことで、商品やブランドに対して認識を深めてもらうことができます。そのため「どれだけ長く動画を見てもらえたのか」という部分に着目してKPIを設定するといいでしょう。
<KPI例>
・平均視聴時間:1再生あたりの平均視聴時間
・再生完了率:動画が表示された回数に対し、一定時間以上再生された確率
・総再生時間:動画が再生された時間の合計
・ブランド好感度:動画視聴前後でブランドに対する好感度を調査
このように、目的に応じて複数の評価指標を検討しましょう。多角的に測定することで、施策の効果を細かく把握することができます。
それぞれ具体的に目標値を設定し、目標達成までの期間も明確にしておくといいでしょう。期間は短いスパンで区切り、都度、達成度合いに応じて改善していくようにしてください。
動画の効果測定に使う3つのツール
動画の効果測定にはツールの活用が必要不可欠です。
動画の効果測定に活用できる3つのツールを紹介していきます。

YouTubeアナリティクス
YouTubeに動画を公開する場合は、投稿した動画のパフォーマンスを確認できる、YouTubeアナリティクスを活用しましょう。
YouTubeに備わっているアナリティクスツールは、「YouTube Studio」という名称で、YouTubeのチャンネルを持っていて動画を公開している方であれば誰でも使用できます。
無料で利用できるにも関わらず非常に高機能なツールで、チャンネル全体の指標はもちろん、動画単体でのさまざまな指標も詳細に確認することができます。
例えば、以下のような指標を確認することが可能です。
・チャンネルで公開されている動画全体の視聴回数や視聴時間
・動画ごとの視聴回数や視聴時間
・チャンネルにアップされている動画を視聴しているユーザーの属性
YouTubeにアップした動画に関するデータの収集と分析は、このYouTube Studioだけで十分と言っても過言ではないので、ぜひ積極的に活用するようにしてください。
Googleアナリティクス
Googleアナリティクスとは、Googleが無料で提供するWebページのアクセス解析サービスです。WEBサイトのアクセス数やコンバージョン、ページごとの離脱率などを計測できます。
また、Googleタグマネージャーという、タグをマネジメントできるツールに、アクセス解析したい動画を埋め込むことで、Googleアナリティクス上でアクセス解析することも可能です。動画の再生時間や視聴者の属性などを確認できるため、動画の効果検証に最適です。
動画広告を出稿するプラットフォームのツール
動画を制作して動画広告を出稿する場合は、広告を出稿するプラットフォームに備わっているアナリティクスツールを活用しましょう。
広告の出稿先となるプラットフォームにもよりますが、基本的にどのプラットフォームでもアナリティクスツールが用意されています。
機能や確認できる指標についてはそれぞれのツールによって異なりますが、
・広告の表示回数
・広告を最後まで視聴したユーザーの数
・広告を途中で離脱したユーザーの数
・ユーザーの離脱ポイント
・広告をクリックしたユーザーの数
など、さまざま指標を確認できるので、動画広告を公開したら
これらのデータを確認・分析し、次の施策に活かすようにしましょう。
動画の効果測定を行う際の注意点
動画の効果測定は、数字を確認して終わりにするものではありません。ここでは、効果測定を行う際に特に意識すべきポイントについて解説していきます。
単一の指標だけで判断しない
動画効果を判断するうえで最も避けたいのが、一つの指標だけを見て評価してしまうことです。
再生回数が多いからといって必ずしも成果が出ているとは限らず、逆に再生回数が少なくても視聴後の行動が大きく動いていれば、目的に対して高い成果を出している可能性があります。視聴完了率が高くても、問い合わせや購入につながっていなければ課題は別の場所にあります。
複数の指標を組み合わせ、動画が「どの層に届き」「どの段階で興味を失われているのか」を総合的に判断することが、正しい分析の第一歩となります。
サムネイル・タイトルの影響を考慮する
動画のクリック率を左右する最も大きな要因が、サムネイルとタイトルです。再生されない動画は、内容をどれだけ改善しても効果が出ません。
クリックされない場合、動画の内容ではなく入口であるサムネイルやタイトルに問題があるケースが非常に多く見られます。
特にYouTubeやSNSは、コンテンツが大量に並んでいるため、視聴者に一瞬で「見たい」と思わせる工夫が欠かせません。
視認性の高い構図になっているか、競合動画と比較して埋もれていないかなど、動画の中身以外の部分も効果測定の対象として捉える必要があります。
期間を区切って評価する
動画の数値は、公開直後と一定期間が経過した後では大きく変わります。
YouTubeやSNSのアルゴリズムは、一定の視聴データが集まってから本格的に表示されることも多く、公開直後の数値だけで判断すると誤った評価につながることがあります。
そのため、最初の数日、1か月、3か月といったように期間を区切り、複数のタイミングでパフォーマンスを比較する姿勢が欠かせません。
成長の仕方や視聴者層の違いを把握することで、長期的に評価すべき動画なのか、早急な改善が必要な動画なのかを適切に判別できるようになります。
外部要因の影響を踏まえて分析する
動画のパフォーマンスは、動画の内容だけではなく外部環境によっても大きく左右されます。
季節要因、業界の動き、競合の広告出稿状況、SNSでのトレンド、ニュースの影響など、さまざまなイベントが視聴数やクリック率に影響を与えるため、数値が急に上昇したり下降したりした場合は、動画以外の要因も必ず確認するようにしましょう。
例えば、競合が同じテーマの広告を増やしたことでクリック率が落ちている可能性や、自社のキャンペーン実施により一時的に数字が上昇しているケースなどが考えられます。
動画単体の評価ではなく、環境全体を踏まえたうえで判断することで、改善の方向性を誤らずに済みます。
動画マーケティングにおけるPDCAの回し方
ただ動画を作って公開するだけでなく、動画マーケティングの効果をしっかりと測定したいと考えているのであれば、動画マーケティングにおけるPDCAの回し方についても理解しておかなくてはいけません。
動画マーケティングでのPDCAは、以下のような手順で行っていきます。
1. 動画を制作してアップする
2. ツールを活用してデータを集める
3. 集まったデータを分析して仮説を立てる
4. 仮説を元に施策を考える
5. 施策を実施する
それぞれの工程を詳しく解説していきます。
1. 動画を制作してアップする
データを集めて分析するなどの効果測定を行うには、動画を制作してアップする必要があります。
「効果測定の2ステップ」で紹介した目的やKPIを達成するためにはどういった動画が必要になるのかを考えて企画を立て、制作していきましょう。
また、YouTubeやInstagramなどのSNSや動画広告のプラットフォームなど、制作した動画をどのようにして活用するのかについても事前に考え、決めておくようにしてください。
2. ツールを活用してデータを集める
動画を制作して公開したら、ツールを活用してその動画の視聴データを集めていきます。
効果測定にはデータが必要不可欠なので、先ほど紹介したYouTubeアナリティクスやGoogleアナリティクス、広告を出稿するプラットフォームに備わっているツールを活用し、データが蓄積される環境を整えましょう。
3. 集まったデータを分析して仮説を立てる
データが集まったら、それらのデータを分析していきます。
YouTubeアナリティクスやGoogleアナリティクス、動画広告のプラットフォームに備わっているアナリティクスツールでは、さまざまなデータを集められるようになっているので、それらを詳細にチェックして分析しましょう。
また、分析していく過程で仮説を立てることも忘れないようにしてください。
例えば、YouTubeアナリティクスで確認できるデータを元に立てられる仮説としては、以下のようなものがあげられます。
| データ |
仮説 |
| 動画の冒頭から離脱するユーザーが多い |
動画の冒頭でユーザーの興味をひけていないため、動画の冒頭を見直すことで離脱を防げるようになる |
| 特定の箇所で離脱するユーザーが多い |
そこまでの内容で多くのユーザーが満足している
そのポイント以降の内容がユーザーの興味をひくものではない |
| 動画の低評価率が高い |
タイトルやサムネイルと動画の内容が乖離している
ユーザーが知りたい情報を届けられていない |
これらはあくまでも仮説であり、この時点で当たっているかどうかを気にする必要はありません。
この段階では、データを元にさまざまな仮説を出していくことが重要になるので、どんどん仮説を立てていくようにしましょう。
4. 仮説を元に施策を考える
データを分析して仮説を立てたら、それらの仮説を元に、次に行う施策の候補をどんどん出していきましょう。
YouTubeにアップした動画があまり露出されていないのであれば、動画の内容を見直し、改めて作り直さなくてはいけません。
YouTubeにアップした動画や出稿した動画広告が十分に露出されているもののクリック率が低い場合は、タイトルやサムネイル画像、テキストなどが魅力的でないと想定されるため、それらを挿し替えて公開し直したり、出稿し直す必要があるでしょう。
動画を最後まで視聴しているユーザーが多いにも関わらず、LPへの誘導などの成果につながっていない場合は、誘導の仕方を変えてみるのもおすすめです。
ここでは、実施するかどうかはあまり考えず、仮説を元にどんどん新しい施策のアイデアを出していきましょう。
出た施策の案を実施するかどうかは、次の工程で決めていきます。
5. 施策を実施する
仮説を元に次に行う施策を考えたら、それらの施策を実際に行っていきます。
マーケティングにおける施策は、実際にやってみないとどういった反応が得られるかわからないという側面が強いので、よほど成功する可能性が低いと思われる施策以外はどんどん実施していきましょう。
仮に思うような成果につながらなくても、そこから学べることや気付けることはありますし、次の施策の精度を高めるのに大きく貢献してくれます。
あとは、
・データを集める
・集まったデータを分析する
・分析したデータを元に次の施策を考える
・施策を実施する
というサイクルをひたすら繰り返していき、ノウハウを蓄積しながら、マーケティングの精度をどんどん高めていきましょう。
これらの工程は、継続して行わなくては意味がありません。
そのため、思いついたときに行うのではなく、スケジュールを決め、決められたタイミングで定期的に分析や次の施策の立案を行うようにしてください。
まとめ
この記事では、動画活用における効果測定方法についてご紹介しました。しっかりと動画の目的を明確にした上で、KPIを設定することが重要です。公開した動画は、ご紹介した解析ツールを活用して目標値への達成度合いを確認してください。
動画マーケティングにおいて重要なことは、定期的に効果測定をおこない、PDCAサイクルを回していくことです。PDCAサイクルとは、
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を繰り返すことによって、継続的に改善し、施策効果を高めていく手法です。このPDCAサイクルを細かいスパンで回して、随時改善を加えていくことで、施策効果が高まっていくでしょう。