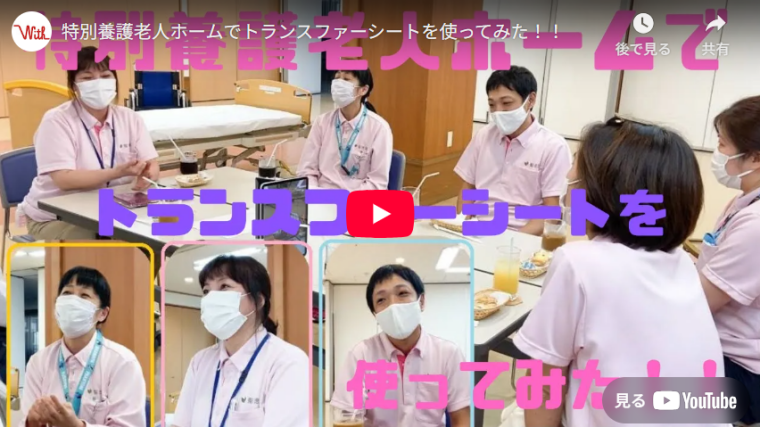世界中で人気の動画投稿サイトYouTubeには個人の投稿だけではなく、各国の大手企業の公式チャンネルが自社のPR動画やユニークな動画などさまざまな動画を投稿しています。
もちろんこれらはマーケティングの一環です。今、さまざまな企業が動画を使ったマーケティングを展開しています。
今回は介護用品などの福祉用具を取り扱うお店に向けて、動画を活用することへのメリットを解説していきます。
福祉用具に関する動画のメリット
どうしても費用や制作時間などコストがかかってしまう動画制作。それでも多くの企業が動画を作り活用する理由とは何なのでしょうか。
ここでは動画制作のメリットを解説します。
動画を作るメリットとは
動画は、映像・音・文字・図形(グラフィック)など、いろいろな情報を一度にたくさん相手に伝えることができます。その情報量の多さは、紙媒体に比べ格段に多く、効率的に情報発信できるメディアといえるでしょう。
人は動くものに対して目で追ってしまう性質があり、人々の目にとまりやすいかどうかが重要な広告やPRにおいて、非常に優れたツールです。
文字よりも映像の方が記憶に残りやすいという説もあることから、より宣伝効果の高いのが動画なのです。
また、費用面のメリットもあります。
YouTubeなど動画投稿サイトは基本的にチャンネルを開設し、投稿するだけであれば利用料はかかりません。つまり、広告費をかけずに宣伝効果を得られる可能性があるということです。
もちろん動画を投稿しただけでは見てもらうことはあまり期待できません。自社のWebサイトやECサイトへの掲載、SNSへの連携もあわせて行っていくことで動画視聴回数をアップすることができます。
福祉用具動画を作るメリット
福祉用具メーカーやそれらを取り扱うお店が動画を作るメリットはさまざまです。
どのような内容の動画を作るかによって得られるメリットは多少変わり、購入・レンタル前に見てもらう動画か、利用者の手元に製品が渡った後に見てもらいたい動画かによって内容が決まってきます。
どのような内容の動画であれ、福祉用具の動画を制作する大きなメリットは「認知度を高める」「信頼を得る」ことにあります。
福祉用具の名前やレンタルや購入の悩みを検索したときに、自社動画がヒットして視聴してもらい満足・納得してもらえるとそれが認知や信頼につながるのです。
特に、福祉用具の使い方の説明などは動画を作ってそれを見てもらえばわかる状態にしておくことで、利用者の問い合わせる手間、そして企業(お店)側の対応する時間を減らすことができます。
いわゆるアフターフォロー的な役割をしてくれるのが動画のメリットでもあります。
制作にコストはかかりますが、動画を作るだけではなくうまく運用していくことで、デメリットを上回るメリットを得ることができるといえます。
動画制作の方法
動画制作には、外部の映像制作会社に依頼する「外注」と、社内制作の「
インハウス(内製)」という方法の2種類があります。
CG合成や4Kの高画質撮影など、プロの機材や技術がないと難しい動画を希望する場合には外注をした方が安心です。ただし、制作料金は高額になる可能性があることを留意しておいてください。
もし上記のような動画でなくても良いという場合には、予算や制作時間を抑えることのできるインハウスをオススメします。自社での制作となりますので、撮影や編集機材は購入する必要があります。
しかし、継続的に動画制作をすることでそのノウハウが蓄積され、動画のクオリティを上げていくことができるでしょう。
また、インハウスで動画制作をする場合でもオススメしたいのが第三者のサポートを受けること。よりクオリティの高い動画を制作し活用していくために、客観的な視点でプロのアドバイスをもらうことは効率的で非常に有効な手段です。
弊社のサービスであるクラウド動画編集ツール「メディア博士」は、企画制作サポートも行っています。
インハウス化を希望される際にはぜひ検討してみてください。
福祉用具に関する動画を制作する際に気を付けるポイント
福祉用具の動画制作は、単なる商品の紹介にとどまらず、利用者の安心や信頼の獲得に直結します。ここでは、福祉用具に関する動画を制作する際に気を付けるポイントを紹介します。
視聴者のリテラシーに合わせた表現にする
福祉用具の動画を見る人は、高齢者本人やその家族、介護スタッフなど多岐にわたります。中でも多くの人が、動画視聴に慣れていない場合があるため、専門用語を多用したり、早口なナレーション、複雑な編集は避けたほうが無難です。
ポイントは「誰に向けた動画か」を最初に明確にすること。
例えば、介護職員向けの業務用説明動画であれば詳細な構造や法制度に触れても問題ありませんが、高齢者やそのご家族が対象の場合は、もっとシンプルな構成と、日常に近い視点での紹介が求められます。
動作や手順はゆっくり・丁寧に見せる
福祉用具の操作方法などを説明する動画では、動作や工程を見せる速度が非常に重要です。動画制作者側が「これくらいで伝わるだろう」と思って作っても、視聴者にとっては速すぎたり、重要な部分を見逃してしまうことがあります。
各動作の間には必ず「間」をとること。必要であれば同じ動作を2回繰り返す、テロップや図解を入れて補足するなど、視聴者が安心して理解できるような工夫が求められます。
手元のアップ映像や、カメラ位置の切り替えも効果的です。
実際の使用シーンを入れることでリアリティを持たせる
例えば、歩行器や移乗用リフトの紹介動画を作る際、スタジオで撮影された映像だけでは、視聴者が「自分の環境で使えるかどうか」を想像するのが難しいこともあります。
そのため、できる限り実際の使用シーンを取り入れた構成にすることをおすすめします。
自宅の室内、福祉施設、病院など、リアルな利用現場での撮影は、製品の利便性や設置スペースの目安なども伝わりやすく、信頼感の醸成にもつながります。
個人情報やプライバシーへの配慮を忘れずに
特に福祉や医療に関わる現場での撮影では、利用者や入居者の顔・氏名・居住環境など、個人が特定される恐れのある情報が映り込むケースがあります。
撮影の際は必ず許可を取り、必要に応じて顔や背景をぼかす処理を行うなど、編集段階でもプライバシー保護を徹底しましょう。また、介護スタッフや現場職員が出演する場合も、事前の同意書を交わすのが望ましいです。
どのような福祉用具の動画があるのか
ここではYouTubeに公開されている福祉用具に関する動画をご紹介します。
製品の動画だけでなく、福祉用具サービス全般に関わる動画などさまざまです。ぜひ参考にしてみてください。
福祉用具の選び方
・あっぷる横浜「歩行器の選び方ポイントを分かりやすく解説!」

介護サービスと介護用品を取り扱っているあっぷる横浜が、歩行器の選び方について説明した動画です。
数種類の歩行器を並べ、何が違うのかメリット・デメリットも含め、どのタイプがどんな人にオススメなのか実際に使用しながら説明しています。
これから歩行器を選ぶ方に向けて比較しながら説明してくれるので自分にはどれが合うのか合わないのかがわかりやすいです。
使用シーンや病気や症状の具体例をあげて説明されると視聴者からの信頼は得やすくなります。種類があり、かつ個人で購入するような福祉用具の場合にオススメの動画です。
福祉用具の使い方
・株式会社いうら「EL570 c1 ベッドから車椅子への移乗」

介護機器、福祉機器、看護・医療用品の製造メーカーである株式会社いうら。YouTubeの公式チャンネルには、自社製造の福祉用具の操作方法動画が並んでいます。
こちらの動画もその中のひとつで、移動用リフトの操作説明です。
このような施設で使用するような福祉用具は、説明動画があれば一度に複数の支援員に見てもらうことができ、操作説明時間をおさえることができます。
また、YouTubeに公開していることで事前に個人的に見ておくことや繰り返し見ることもできるので、製品を使用する側に喜ばれる動画ではないでしょうか。
サービスの紹介
・ダスキンヘルスレント「ダスキンヘルスレントとは?」

清掃業務をメインに外食産業も展開するダスキンが介護商品・福祉用具のレンタルと販売をおこなっているのがこのダスキンヘルスレント。この動画はそのサービス内容についての紹介動画です。
利用者へ寄り添う姿勢やフォローの充実をアピールしています。
自分たちはどのようなサービスを行なっているか、利用者にどのようなメリットがあるのかを知ってもらうことは非常に重要です。
まずは、このような動画から作ってみても良いかもしれません。
そのほか
・株式会社ウィズ「特別養護老人ホームでトランスファーシートを使ってみた!!」
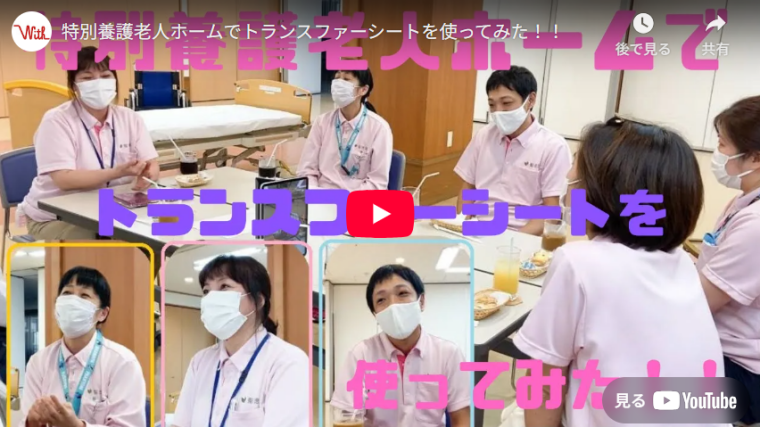
株式会社ウィズが製造販売している移乗用スライディングシート「トランスファーシート」を実際に特別養護老人ホームで使用してもらい、現場の方に感想をインタビューしている動画です。
現場の方は介護のプロなので、説得力が違います。感想を言ってもらい製品の信頼性を高める手法はテレビや雑誌などでもよく使われます。
ただ、演出をしすぎるとわざとらしく嘘っぽい動画になってしまい、逆に信頼を落とすことになりかねませんので注意が必要です。
まとめ
高齢者や障害者など福祉用具を必要とする人はこれからも増えていくと予想されます。その需要を逃さないように、ぜひ動画を活用して売り上げアップのチャンスをつかんでいきましょう。