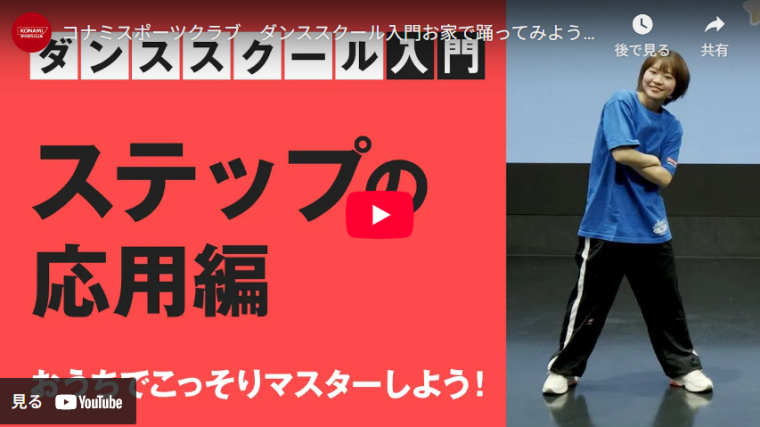フィットネス・スポーツジムの現状
コロナによる自宅待機の影響で近年健康志向が高まり、今までスポーツに手を出してこなかった人もフィットネスやスポーツジムを体験するようになりました。さらに多くの業界がコロナで疲弊するなか、本業界も例外ではありません。
しかしフィットネス・スポーツジム業界の売上は2020年7月には回復するなど、コロナを乗り越えようとする動きが見られます。
こういった状況を見た一部フィットネス・スポーツジム企業は店舗を必要としないサービス展開を始めるなどのアフターコロナに向けた工夫を事前に施しています。
では実際にコロナによってフィットネス・スポーツジム業界はどのように変化していったのか紐解いていきましょう。
コロナ渦のフィットネス・スポーツジム業界はどうなった?
経済産業省第3次産業活動指数でスポーツ施設提供業の内訳(利用者数の変動)を見てみると、フィットネスクラブは2014年以降から2020年初頭にかけてゆるやかな上昇傾向にあったものの、コロナの影響を受けて2020年5月まで急激な指数低下を記録しました。
しかし7月には急速に回復、2021年5月には6割程度(2020年1月と比較)までにとどまっています。
このようにとどまった要因は『コロナ禍でできるリフレッシュがスポーツに向いたため』と考えられています。
スポーツ庁の発表によると『36.5%がコロナによって日常生活の変化が生じたため』、『30%が仕事が忙しくなくなったため』運動を実施したと回答しました。
約60%以上がコロナをきっかけに運動の実施を増やしたものの、その多くがジョギングや身近にできるストレッチやヨガなどを行っています。
結果フィットネス・スポーツジム業界はコロナによって生まれたスポーツ新規勢を顧客として獲得できていません。
コロナ渦で成功したフィットネス・スポーツジム業界のポイント
業界全体でみるとコロナによって生まれたスポーツ新規勢を顧客として獲得できていません。しかし業界を詳しく見てみると、成功した一部フィットネス・スポーツジム企業は顧客を獲得しコロナ禍にもかかわらず売上を上げています。
そこで今回は成功したフィットネス・スポーツジム企業のポイントを押さえていきましょう。
フィットネス・スポーツジム企業は従来のような大型施設をコロナ禍ではサービス提供することができませんでした。そういった課題を解決するため、マンションの一部屋を利用した『パーソナルトレーナーによる個別指導タイプ』、『自宅でできるリモート指導タイプ』など、利用者それぞれの生活に合わせたサービスへと転換していきました。
このような転換ポイントをおさえた企業は緊急事態宣言の中でも事業回復をし、売上を大きく伸ばすことができました。
フィットネス・スポーツジム業界の将来性
フィットネス・スポーツジム業界の現状やコロナ禍の中で成功するポイントを紹介してきました。ではコロナが収束した後、業界の将来はどのような見込みがあるのでしょうか?推測していきましょう。
フィットネス・スポーツジム業界の市場規模はコロナ禍で一時的に縮小してしまいました。早期に業績回復させるためには、以下のポイントを工夫する必要があります。
・事業モデルの転換
・顧客志向のマーケティング
・若手の育成
以上3つのポイントを重点的に取り組むことで集客UPや生産性を上げ、早期に事業回復ができます。
GWIウェルネスレポートによると世界のフィットネス・スポーツジム業界の規模は2019年に8282億米ドルに達し、ジムの店舗数やクラブ会員数は過去最高を記録するなど世界的にフィットネス・スポーツジムが注目を浴びていました。
このことからコロナの影響から素早く回復できた企業がコロナ以前のフィットネス・スポーツジム業界の収益を獲得できることでしょう。このようにフィットネス・スポーツジム業界の将来性は他業界と比べて明るく思われます。
フィットネス・スポーツジム業界におすすめの動画活用事例
将来性が十分あるフィットネス・スポーツジム業界ですが、早期に事業回復のためには様々なマーケティングを施す必要があります。そのうちの一つが動画活用です。
なぜフィットネス・スポーツジム業界が動画活用すべきなのか?実例をもとに紹介していきます。
パーソナルトレーニングを動画活用でアピール
こちらは名古屋にてパーソナルトレーナーとして活動している方の実際のトレーニング様子になります。
パーソナルトレーニングを受けてみたいものの、どんなものかイメージがつかないという方も多くいます。そういった顧客に向けて実際のトレーニング姿を見せることで入会する方も増えます。
またトレーニング内容や手法によってトレーナーのレベルも判断できるのでトレーニングの質もアピールすることができます。
動画活用でオンラインスポーツジム
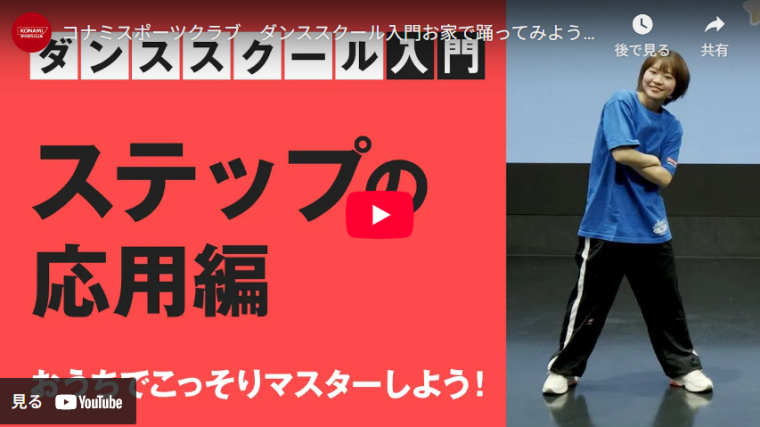
こちらはコナミスポーツクラブ ダンシングスターズのディレクターとインストラクターがレクチャーする、ダンススクール動画になります。
コロナの影響でジムに行けず、室内で体を動かしたいと感じる人は多くいます。そういった方に向けてオンライン上で指導するオンラインスポーツジムを提供することをおすすめします。
生配信で他生徒と連携しながらするもよし、動画として発信してしまうのも良いでしょう。
フィットネス・スポーツジム業界が動画を活用する際の注意点
動画活用にはいくつかのリスクや注意点も存在します。ここを軽視すると、せっかくの動画が逆効果となりブランド価値を損ねる可能性もあるため、戦略的かつ慎重に運用する必要があります。
ここでは、具体的な注意点を整理していきます。
安全性と正しいフォームを伝えること
トレーニング動画で最も大切なのは「安全性への配慮」です。利用者の多くは動画を参考に自宅で運動を真似しますが、間違ったフォームや過度な負荷のかけ方を示してしまうと、怪我につながる恐れがあります。
そのため動画制作時には、必ず正しいフォームを明示し、難易度ごとに段階的なバリエーションを示すことが効果的です。
さらに「無理をせず体調に合わせて行ってください」といった注意書きやナレーションを入れると、視聴者は安心して取り組むことができます。
個人情報・プライバシーの保護
ジム内での撮影では、他の利用者やスタッフが映り込む可能性があります。本人の許可なく公開するとプライバシー侵害となり、トラブルの原因になります。
施設紹介やトレーニング動画を撮影する際は、出演者を限定する、一般利用時間外に撮影する、モザイク処理を施すといった配慮が不可欠です。
また、会員インタビューを行う場合は必ず書面や口頭で使用許諾を得ることで、後々のリスクを避けられます。
誇張表現を避け、リアルな効果を伝える
フィットネスの世界では「短期間で必ず痩せる」「誰でも劇的に変わる」といったキャッチコピーが使われがちです。しかし過度な誇張は消費者庁による景品表示法違反のリスクがあり、信頼を失う要因となります。
動画では実際のトレーニング内容や会員のリアルな声を届けることが重要です。例えば「3か月で〇kg減量」といった数字を使う場合には、個人の成果であることを明示し、全員が同じ結果を得られるわけではないことを補足する必要があります。
音楽や映像素材の著作権に注意する
動画制作においてBGMや映像素材を安易に使用すると、著作権侵害につながるリスクがあります。特にYouTubeやSNSは自動検出システムが厳しく、無断利用が判明すると動画が削除されたりアカウント停止になることもあります。
必ず著作権フリー素材やライセンス契約済みの楽曲を利用するようにしましょう。さらに、ジム内で流れている音楽がそのまま録音される場合にも注意が必要です。
まとめ
さて今回はフィットネス・スポーツジム業界について基礎知識を交えながら、どういった動画活用をすべきか紹介してきました。
コロナの影響を受けながらも既に回復の兆しを見せており、将来的にも有望な本業界は動画活用などITを駆使することでさらに発展することでしょう。ぜひ動画活用を導入してみてはいかがでしょうか?