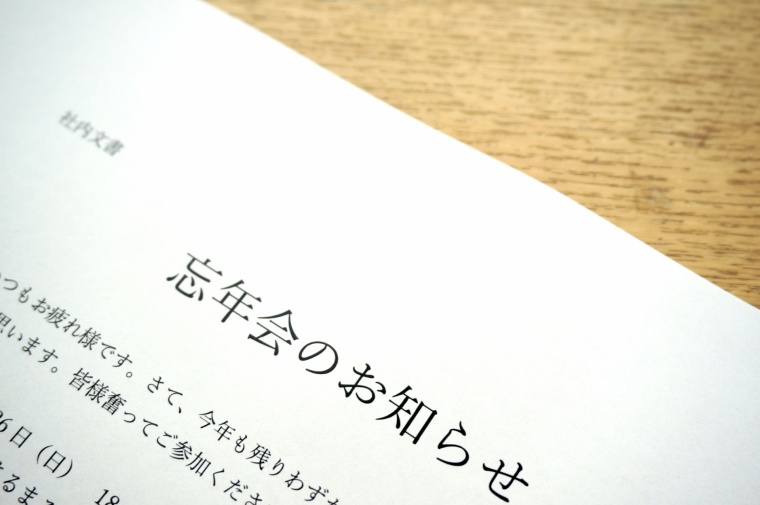社内報を作成することになり、作ってはみたもののしっくりこないということはありませんか?また、社内報を作成するために良いデザインは何かと、悩んだことはありませんか?
この記事では、良い社内報を作成するにあたってどんなデザインにすればよいかについて解説していきます。また、社内報のレイアウトを決めていくときにどのようなことがポイントになるのかや作成における注意点などを詳しく解説していきます。
社内報を活用する目的とは
社内報とは、会社内で情報を共有するために制作された媒体のことです。以前は、紙媒体で配布されることが多かったのですが、近年はメールや動画、社内共有アプリを使用するなどして発信されることが多くなりました。
では、社内報はどのような目的で発信されているのでしょうか。以下、会社が社内報を発信する目的を解説します。
①情報共有のため
規模が大きい会社になると、業務は様々な部署で分担して行うことになります。さらに大きな会社であれば、同じ部署でも課が別れることもあるでしょう。
業務を細分化し分担して行うと、どうしても他の部署で行っている仕事については、把握しきれないということがおきます。知らなくても完全に支障がない場合は良いかもしれません。
しかし、多くの仕事では他部署の情報も把握しておくことが役に立つ場合があります。社内の情報をこまめに共有するため、社内報が役に立つのです。
②社員間のコミュニケーションのため
規模が大きい会社になると、努めてコミュニケーションをとるようにしなければ、互いの関係性が希薄になってしまいがちです。
もし、仕事で協力が必要だったりする場合にも声をかけ辛くなるかもしれませんし、社内で共有していれば解決できた問題が起こってしまうかもしれません。
そうなると、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまったり、ミスを事前に防げなかったりすることが考えられます。
普段から、コミュニケーションをとる一つの手段としても、社内報が活用できます。社内報の記事をきっかけに社内でのビジネスチャンスが広がったり、話しかけたりするきっかけにすることができるでしょう。
③企業理念やビジョンを共有するため
企業が何のためにあるのか、会社の目指すところは何か、といった企業理念やビジョンを共有するのにも社内報が役に立ちます。
企業理念やビジョンは、普段から意識をしていなければ忘れてしまいそうになるものです。また、入社してから間もない間は意識できていても、長年勤めているうちに忘れてしまったりする場合もあります。
そこで社内報を利用して、経営陣からメッセージを送ったり経営方針を改めて確認したりする機会をつくります。そうすることで、企業理念やビジョンに立ち帰り、社内が一丸となって業務にあたることができるのです。
④社員のモチベーションアップのため
例えば社内報で、営業成績のいい社員や活躍をした社員を表彰する機会を作ります。企業として望ましい行動をした社員を取り上げることで、良い行動を促すことができます。取り上げられる機会をつくることで、社員のモチベーションアップが期待できます。
内容は頻繁に変えてしまうと定着しないので、最低でも半年程度継続していくべきですが、慣れてしまうとやらなくなってしまう事を防ぐために、企画は定期的に変えていくのが望ましいです。
⑤企業に愛着をもたせるため
社内報で、自社製品の紹介をしたり、自社の取り組みを発表することで、会社に対する愛着向上を期待できます。自社のことをより深く知ってもらうことで、興味関心を引き出し愛着を持ってもらうことがねらいです。
社内報ができるまでの流れ
社内報を作るにはどのような手順ですすめていけばよいのでしょうか。この章では、社内報ができるまでの流れを解説します。
企画・立案
はじめに、企画立案です。なぜなら明確な目的がなければ効果的なコミュニケーションは難しいからです。
まず、目的やターゲットを明確にしましょう。例えば、新プロジェクトの進捗報告や社員の活動紹介など。
次に、伝えたいメッセージや情報を整理し、興味を引くトピックを選定します。例えば、社員の成功体験や新しいイニシアティブの導入などがあります。
企画の骨子ができれば、その後のステップもスムーズに進行します。企画が魅力的で的確な方向性を持っていれば、社内報は組織内の結束力向上や情報共有の促進に寄与します。
原稿・取材依頼の担当者を決める
次に、原稿・取材依頼の担当者を決めることです。これは円滑な情報収集と編集作業を確保する鍵です。担当者が明確であれば、情報が漏れず、タイムリーに収集できます。
例えば、新商品の取材依頼があれば、製品担当者が的確な情報を提供し、スムーズに記事がまとまります。
担当者の選定が大切な理由は、的確な情報共有ができ、結果として社内報の品質向上に繋がるからです。
取材・撮影
続いて、取材撮影です。これは企業の内外に向けてリアルで魅力的な情報を提供するための欠かせないステップです。取材撮影を通じて、社員の活動やイベント、製品などを生の姿で伝えることができます。
例えば、社員の活躍を紹介する記事では、職場の雰囲気やチームワークを効果的に表現できます。
取材撮影は視覚的な要素を通じて読者にリアルな印象を与え、企業の活力や魅力をアピールする上で重要な要素となります。
原稿作成
取材撮影が終わったら、原稿を作成します。これは企業の内外に向けて的確かつ魅力的な情報を伝えるために必要です。原稿は企画や取材をもとに、読み手にわかりやすく興味深い形で情報を提示します。
例えば、社員の成功事例やプロジェクトの進捗状況を伝える記事では、事実を基にわかりやすい言葉でストーリーを組み立て、読者に共感を呼び起こします。
原稿作成は的確な表現と情報の整理が求められ、これを通じて社内報が読者にとって価値のあるものとなります。
レイアウト決めとデザイン
その後、社内報のレイアウト決めとデザインを考えます。これは情報の視認性や伝達効果を高める重要なプロセスです。適切なレイアウトとデザインにより、読み手が情報をスムーズに理解しやすくなります。
例えば、目次や見出しを工夫して配置することで、読者が興味を引きやすくなります。また、企業のブランドイメージに合ったデザインを取り入れることで、社内報が一貫性を持ち、プロフェッショナルな印象を与えます。
見やすいデザインは読者の興味を引きつけ、情報を効果的に伝えるのに重要です。
校正
次に、社内報の校正作業です。校正は正確な情報伝達を保つ上で不可欠です。誤字や文法ミスがあると、読者に誤った印象を与える可能性があります。
また、校正は一貫性も確認する重要な作業で、表現スタイルや用語の統一を図ります。例えば、同じ言葉が異なる表記で使われている場合、校正作業で修正することで読み手の混乱を避けることができます。
要点を明確に伝え、信頼性を高めるために、校正は丁寧かつ徹底的に行うべきです。
印刷・完成
ここまで終わったら、社内報の印刷・完成作業です。印刷はコンセプトを具現化し、情報を広く社内に発信する重要なステップです。完成された印刷物は視覚的にも訴えかけ、読者に直感的に情報を伝えます。
例えば、企業が新しいビジョンを掲げ、その戦略を共有する場合、カラフルで鮮やかなデザインやグラフィックを活用することで、メッセージの印象が強まります。
印刷によって情報の永続性も確保され、社員は随時手に取りながら情報をキャッチアップできます。
「良い社内報のデザイン」って何?
社内報を発信する目的は様々ですが、どれも達成するにはまず社員に読んでもらわなければ意味がありません。では、「良い社内報のデザイン」とはどんなものでしょうか。
社員はそれぞれ、日々の業務に追われています。文の量が多く見え長い社内報だと、内容をきちんと読んでもらえずに終わってしまうかもしれません。
まず、社員の目に留まり、読んでみたいと思わせる見た目にすることが必要です。そして、時間の無い社員にとって、読みやすい内容や分量であることが必要です。
また、趣旨が分りやすかったり、要点がはっきりしているレイアウトにしておく必要もあります。レイアウトがごちゃごちゃしていて読みづらい社内報も好ましくありません。
見た目だけでなくそこに書かれた内容も、社員の興味を惹くものであれば好ましいです。社員が知りたい内容であったり、目にするのが楽しみだったりする内容であればさらに良いでしょう。
それには、記載内容を読み手に合わせたものにするという工夫も重要です。
さらに、そもそも読みやすい読み物を作成するというテクニックも重要です。文字の大きさや配置、色使い、強調ラインや囲みなどもこだわるとさらに良くなります。
また、写真や図を取り入れ、それらをどのように配置するかについても工夫が必要です。沢山盛り込めばよいというわけではないので、バランス感覚も重要です。
社員にとって読みやすいレイアウトで、かつ読んでみたいなと思える内容であれば、良い社内報と言えるでしょう。
では、そんな「良い社内報」にするレイアウトや、デザインとはどんなものでしょうか。次項からは、社内報のレイアウトを決めるポイントやデザインを作成するポイントと、その注意点について詳しく解説していきます。
社内報のレイアウトを決めるポイント
社内報を作成する目的は様々ありました。その目的を達成する重要な要素の1つが、適切なレイアウトです。では、どのようなレイアウトにすると良いのでしょうか。
ここでは、社内報のレイアウトを決めるポイントについて解説します。
社内報の目的に応じたレイアウトにする
社内報を発信する目的に応じて、レイアウトを決めます。例えば、社内報の目的が、「社員間のコミュニケーションを図るため」であれば、新入社員の自己紹介や、部署のメンバー紹介や仕事内容の紹介などが記事になります。
伝えたい内容が決まれば、読み手に取って読みやすく、見た目に見やすい構成になるようレイアウトを決めます。
社内報の企画は、目的に応じてさまざまものがあります。どんな内容を伝えるのか決めたうえで、目的に応じた企画を設定し、見やすくレイアウトします。
コンテンツで構成を切り分ける
できるだけ、1ページに掲載するテーマは1つに絞るようにすると見やすくなります。
ただし、ページの関係で、いくつかのコンテンツが同じページに並ぶ場合もあるかもしれません。その場合には、構成を分けコンテンツの区切りがわかるようにします。
適切に余白をとる
社内報に限らず、文章のレイアウトにおいては、適切に余白をとりましょう。行間が狭かったり余白がない文章は大変読み辛いです。文章はできれば、3~4行に一度は改行を入れるようにし、行間や余白を適度に設計しましょう。
社内報のレイアウトを決める際の注意点
この項では、社内報のレイアウトを決める際に注意すべき点をまとめました。以下のような点に注意すれば、効果的な社内報が作成できます。
目線の動きを考えたレイアウトにする
Zの法則と言って、人は横書きになっている紙媒体を目で追う時に、「左上→右上→左下→右下」の順で目線が動きやすい傾向があると言われています。
そのため、紙媒体の社内報を作成する時には、まず最初に目線がくる左上にはタイトルやトピックスを配置し、後で読んでもいいコラムのようなものは左下に配置するようにしましょう。
一方、WEB媒体の場合は、横書きの文字を読むように左から右に目線を移動し、下に向かって目線を動かして読む傾向があります。ちなみに、これはFの法則と言います。
また人は、大きく書いてあるものを先に見て、順に小さいものへ目線を映していく傾向があります。そのため、特にみて欲しいものは大きく書くのもテクニックの1つです。
レイアウトに統一感を持たせる
ページごとに作成者が異なったり、テーマによってページのカラーを変えたくなる場合もあるかもしれません。ですが、それぞれのページで全くバラバラのレイアウトになっていると、とても見にくくなってしまいます。レイアウトには統一感を持たせた方が、読み手にとって読みやすい社内報になります。
また、社内報は基本的に一回で終わりではなくシリーズ化して続けていくものです。レイアウトが同じだと、社員も一目で社内報とわかるので保管もし易くなります。
会社のカラーに沿った構成にする
社内報を作成する際には、自社のイメージに合っているか考える必要があります。社内でみるものとはいえど、あまりにも逸脱したものになっていると、社員に受け入れられず読んでもらえない可能性があるからです。
社内報は、社内でのブランディングとしての役割も担っているので、会社のカラーに合ったレイアウトにすることも重要です。
先進的なイメージを打ち出したいのであれば、斬新なレイアウトや独創的なコンテンツを盛り込んで作成するのも適切でしょう。もしくは、堅実なイメージを持つ会社であれば、落ち着いたレイアウトの社内報がマッチします。
社内報のデザインを作成するポイント
社内報はどのようなデザインが良いでしょうか。ここでは、社内報のデザインを作成するポイントについて解説します。
ターゲットに合わせたデザインにする
社内報に関わらず、発信したい内容については、見てもらえないと意味がありません。
ですが、目的を度外視して出来るだけ多くの人に見てもらおうと無難なデザインにしてしまうと、結果として誰にも見てもらえないという危険性もあります。
まずは、「誰をターゲットにするのか」という事を明確に設定する必要があります。ターゲットの年齢層(若手なのか、中堅以上なのか)、職種(オフィスか、現場か)によってもマッチする表現は大きく変わります。
男女の差によっても、好まれるレイアウトは変わってくるでしょう。そのため読んでもらいたいターゲットにあわせたデザインになるよう工夫する必要があります。
例えば、読んでもらいたい層が若手社員だった場合は、写真や図などを用いて、見た目にインパクトのあるデザインにするという方法もあります。また、動画を取り入れたりなど、まるでSNSをみているかのようなデザインも好評になるでしょう。
あるいはターゲットが管理職や年齢が50代などの社員の場合は、新聞のようなテキスト中心の方が読まれやすいかもしれません。このように、デザインはターゲットに合わせて工夫しましょう。
企業のブランドカラーやイメージカラーを用いる
社内報のデザインを作成するポイントの一つは、企業のブランドカラーやイメージカラーを活用することです。ブランドカラーやイメージカラーは、企業のアイデンティティや価値観を視覚的に表現するツールです。
例えば、コカ・コーラは赤といったように、視覚で瞬間的に企業をイメージできるため、統一感が生まれ、視覚的なまとまりや印象を与えることができます。
社内報にもこれらのカラーを活かし、従業員は視覚的に企業を認識しやすくなり、ブランドへの愛着や誇りを感じやすくなります。
タイトル・見出し・本文で形成する
社内報のデザインでは、タイトルは簡潔で興味を引くものにし、見出しは情報を整理しやすい構成にしましょう。
例えば、「新プロジェクト始動!」や「社員インタビュー:成功の秘訣」などが挙げられます。本文は分かりやすく、要点を明確に伝えることが大切です。芸術性が高いものよりも、読みやすいデザインに仕上げましょう。
社内報は、社員との効果的なコミュニケーションを促進するツールなので、情報をスムーズに吸収できるよう心がけましょう。
文字について
記事の内容によって書体を変えたりするのもポイントです。例えば、会社の情報共有や経営陣からのメッセージなどは硬く力強いフォントを使用したりします。
一方で、社員紹介やコラムなどはポップな親しみやすいフォントを使用するなどといった方法があります。
ただし、あまりにも沢山のフォントを使い過ぎてしまうと、フォントが目立ってしまい内容が分りにくくなることがあります。フォントのバリエーションは2~3種類程度に抑えるのが賢明です。
さらに、一行当たりの文字数も20~30文字程度にするのが読みやすいと言われています。一文を長くし過ぎないなど、読みやすくする工夫を心がけましょう。
色使いについて
色使いにも配慮が必要です。効果的に色分けをすることによって、項目ごとに対比しながら読むことができたり、重要な項目を目立たせることができます。
ただ、目立たせようとするあまり、多くの色を使い過ぎるとかえって見づらくなってしまいます。ベースカラーの他に、メインカラー、アクセントカラーと3色程度でまとめましょう。
会社のイメージカラーも意識すべきです。カラーバリエーションは増やし過ぎず、強調色は効果的に使用し、伝えたい内容に合わせて使用しましょう。
写真について
写真は社内報において、印象を大きく左右する重要なものです。使用する写真は、社内報のコンセプトに応じて写真加工ツールでトーンを揃えたり、レイアウトにまとまりを持たせる工夫が必要です。
また、記事のコンセプトによって写真の大きさを変えるなどの工夫も必要です。例えば経営者や社長のインタビュー記事では、紙面の大部分を写真にすると印象深い記事になります。
新入社員のインタビューなら、全員の写真を同じサイズで並べるなどして、コメントやプロフィールを記載すると良いでしょう。写真の使い方にもこだわりをもって作成しましょう。
社内報のデザインを作成する際の注意点
社内報のデザインを作成する際に注意すべき点はどのようなことでしょうか。ここでは、社内報のデザインを作成する際の注意点について解説します。
アイキャッチを入れる
読み手の印象に残る工夫が必要です。社内報を読むときは、全てに集中して隅々まで読む人は少数です。
多くの社員は、さっと読み飛ばしてしまうので、その中で目に留まるようなアイキャッチを入れる工夫が必要です。興味を惹くようなキャッチフレーズが盛り込まれたタイトルや、記事見出しを意識しましょう。
文字を装飾する
文章を読んでもらう工夫として、文の装飾も意識しましょう。文字を大きくしたり、色を付けるのはもちろんのこと、枠を付ける、線を引くなど、目に留まる工夫をしましょう。
また、背景色を変更したり、コンテンツごと囲んだり、文字列の向きを変えたりするのも有効です。ただし、全てに装飾をしてしまうと、みて欲しいものが目立たなくなってしまいます。装飾する部分は、特に注視して欲しい部分に限りましょう。
リード文をつける
アイキャッチの後には、リード文を入れます。この記事はどのような記事なのかという記事要約を書いておきます。社員は日々の業務で忙しいので、記事をじっくりと時間をかけて読んでいるわけにはいきません。
記事の内容や作成意図、この記事を読むとどうなるのか等を書いておきます。そうすれば、この記事を読み進めるべきなのかの取捨選択ができ、また読みたいという動機づけをすることができます。
写真や画像をつける
社員の中には、文字が多い記事は読まないという人もいます。また文章を読むのに抵抗がない社員でも、長々とテキストだけが続く記事を読むのは大変で、最後まで読まずに飽きてしまったりする可能性があります。
そんな時、写真や画像のビジュアル要素が入れば、すんなりと記事を見てもらえるということがあります。文字を読むのが苦手な人でも、写真や画像は抵抗なく見れることが多いので、記事には写真や画像をつけましょう。
分量や掲載情報に過不足はないか
社内報に載せる情報量は、読み手の負担も考え多過ぎることが無いようにしましょう。あるいは情報量が少なすぎて、内容が十分伝わらないといった事も避けましょう。
趣旨に沿って、何を伝えたいのか目的を明確にしたうえで、必要な情報を過不足なく適量で届けられるようにしましょう。
社内報作成にテンプレートを使用する
社内報を作成する時には、テンプレートを使用すると便利です。テンプレートを作成すると記事が作りやすくなるということ以外にも、様々なメリットがあります。
一方で、テンプレート使用がそぐわない場合もあります。それぞれについて説明します。
テンプレート使用のメリット
テンプレートを使用するメリットの一つは、記事に統一感がでることです。毎回バラバラな構成になると、読んでいる人にとっては読みにくくなるものです。
社内報は、定期的に発信するものなので、統一感を持たせるためにも、テンプレート化することがおすすめです。
また、テンプレート化すると、社内報の作成を持ち回りにしたとしても、毎回統一感のある記事が作成できます。さらに、新入社員や異動して間もない社員など、これまでの流れを知らない人でも、社内報を作成することができます。
特定の社員がずっと作り続けるのは、負担になる可能性がありますが、テンプレートを作成しておけば負担を減らすことができます。
ただし、何年も同じにしてしまうと飽きてしまうので、時折変えるのも良いです。例えば、年度毎に変えるなどしていくとよいでしょう。
テンプレート使用が合わないことも
一方で、テンプレート化がそぐわない場合もあります。例えば、社内報の目的を変えたいとか、臨時のイベントのために使用するといった場合です。この場合、これまでとは違う構成にする必要が出てきます。
社内報の目的が変わるときには再度、レイアウトやデザインも刷新し、ターゲットに合わせた社内報の構成を練り直しましょう。また、臨時のイベントに使用する際も、これまでのテンプレートは内容に応じて作り直しましょう。
おすすめテンプレートサイト5選
WEB上では、社内報のデザインができるテンプレートサイトがいくつもあります。ここではその中でも、おすすめのテンプレートサイトを5つ厳選してご紹介します。
Canva

引用:Canva
Canva(キャンバ)は、無料で使えるデザインツールです。社内報やチラシの作成ができますが、SNS用のサムネイルや名刺も作成することができます。おしゃれなテンプレートが豊富に用意されているのが特徴です。
bookma

引用:
bookma(ブックマ)
bookma(ブックマ)は、株式会社エルム・パブリッシングが運営する無料で本のデザインが作れるフリーソフトです。このフリーソフトでは、社内報の他、パンフレットやカタログ、フリーペーパー等のデザインもできます。
パワポン

引用:
パワポン
パワポンは、アスクル株式会社が運営している、
パワーポイントで編集できるデザインテンプレートを扱っているサイトです。会員登録は無料で、登録するとパワポンの全てのテンプレートが使用できます。
Microsoft Office テンプレート

引用:
Microsoft Office テンプレート
マイクロソフトが運営する、無料で使えるテンプレートを扱っているサイトです。テンプレートの種類は2,000種類以上あり、誰でも簡単に資料や作品を作ることができます。
Adobe InDesing テンプレート

引用:
Adobe InDesing
アドビ社が提供するテンプレートソフトです。パンフレット、ポートフォリオなどが作成でき、電子出版や印刷物などの作成ができます。7日間の無料体験も可能です。
社内報として使えるネタ
社内報を継続的に発行していく上で、「どんな内容を載せればいいのか分からない」という悩みは多くの企業で共通です。ここでは、会社の規模や業種を問わず使えるネタを紹介します。
社員紹介・チーム紹介
最も定番でありながら、常に需要のあるのが「社員紹介」や「チーム紹介」です。新入社員や中途採用者の紹介はもちろん、部署単位の取り組み紹介やチームリーダーのインタビューなども効果的です。
特に、普段関わりの少ない部署や拠点の人の顔と名前を知る機会になるため、コミュニケーション促進に役立ちます。
社員紹介を行う際は、単なるプロフィールの羅列にせず、「最近ハマっていること」「仕事で大切にしていること」など、個性が伝わる質問を交えると親近感が生まれます。
社長・経営陣メッセージ
経営層からのメッセージも、社内報に欠かせない重要コンテンツです。年度の始まりや期の区切り、組織変更、ビジョン刷新のタイミングなどに合わせて発信することで、社員が会社の方向性を正しく理解しやすくなります。
単なる「挨拶文」にとどまらず、「今期の重点施策」「社員に期待する姿勢」など、具体的な行動の指針を示すとより効果的です。
また、社員に親近感を持たせるために、趣味や最近の出来事などパーソナルな話題を少し加えるのもおすすめです。文字だけでなく、短いコメント動画を添えると、より温度感が伝わる社内報になります。
社内イベント・表彰・福利厚生の活用紹介
社員旅行、表彰式、運動会、忘年会、ボランティア活動などの「社内イベント」も人気の高いコンテンツです。
特に、写真を多く掲載することで参加できなかった社員も雰囲気を味わうことができ、次回の参加意欲を高める効果があります。イベント時の「裏側」や「準備担当の声」などを特集すると、読者がより関心を持ちやすくなります。
また、「福利厚生の活用紹介」も有効なネタです。例えば「社食メニュー特集」「健康診断のオプション紹介」「資格取得支援制度の活用事例」などを記事化すると、制度の利用促進につながります。
アンケート・投稿コーナー
最後に紹介するのは、社員が直接参加できる「双方向型コンテンツ」です。社内報が一方的な情報発信に偏ると、どうしても読むだけの存在になってしまいます。
そこで、「社員アンケート」「お題投稿」「おすすめ紹介」など、社員が意見を出し合えるコーナーを設けると活気が生まれます。
例えば、「今月のおすすめランチ」「私の仕事効率化グッズ」「最近うれしかったこと」といったテーマを設定すれば、部署や役職を問わず誰でも参加できます。
まとめ
この記事では良い社内報のデザインとはどんなものか、社内報のレイアウトやデザインを作成する時のポイントや注意点について解説をしました。また、社内報にテンプレを使用する時のメリットデメリットにもふれました。
社内報を作成するには、目的を明確にしてそれを達成できるようにレイアウトやデザインを決めていくことが大切です。そのような情報を発信したくて、そのターゲットは誰が適切なのか、ターゲットはどんな内容を求めているかと、細かく設定することが必要です。
どの社員がターゲットになったとしても、基本的に社員はいつも忙しく業務にあたっています。
限られた時間の中で社内報を読んでもらうには、まずは目に留まりやすくする必要があります。また、要点が分りやすく読みやすい工夫も必要になります。
さらに、どの社員に向けて発信したいのかターゲットを明確にして、そのターゲットに響く内容にする工夫も重要です。あくまで社内向けの社内報とはいっても、社員に確実に届くようにするには多くの工夫が必要になるものです。
ぜひこの記事を参考にして、良い社内報づくりに活用してみてください。