コンテンツ
事例紹介
活用方法
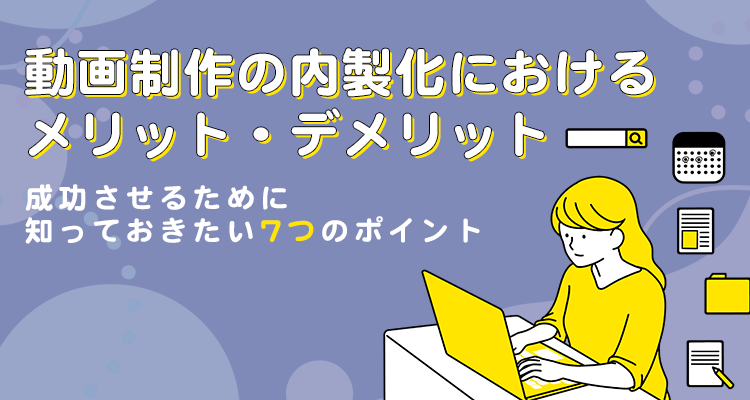
クラウド動画編集ツールのご案内資料
今すぐ無料ダウンロードこの記事は、こんな方におすすめです
動画制作の内製化とは、企画から撮影・編集・公開(社内共有を含む)までを、社内の担当者・チームで完結できる状態に近づけていく取り組みです。
ここでいう「完結」は、必ずしもプロレベルの映像品質を意味しません。企業活動で必要な情報を、必要な人に、必要なタイミングで届けられることが目的です。
たとえば研修や業務マニュアルの動画は、映像表現の凝り具合よりも「迷わず理解できること」「最新版が見つかること」「更新が回ること」の方が重要になりやすい領域です。
逆に、企業のブランドイメージに大きく影響する動画は、内製と外注を組み合わせる判断が現実的になることもあります。
企業の動画活用は、販促や広報だけでなく、研修、業務マニュアル、社内共有、営業資料など幅広い業務に広がっています。
更新頻度が高い領域ほど、外注だけでは回らなくなりやすく、内製化の検討が進みます。動画内製化のポイントは「作れるようにする」だけでなく、「継続して使われ続ける状態をつくる」ことにあります。
内製化と相性がよいのは、撮り直しや更新が前提の動画です。毎回ゼロから作るのではなく、テンプレート化や再利用が効くため、社内で回せるほど効果が出やすくなります。
特に、組織内で知識や手順を標準化したい場面では、動画は文章よりも伝達のブレが少なくなりやすいのが特徴です。
これらの動画は、発生頻度が高い一方で「毎回外注するほどではない」「社内事情に合わせてすぐ更新したい」というニーズが出やすい分野です。
まずは、このような“量が必要で更新が前提”の動画から内製化を始めると、投下した工数が無駄になりにくく、成功体験を積みやすくなります。
一方、アニメーションや高度な撮影表現が必要な動画、短期間で大規模に制作する案件などは、社内だけで抱えるとスケジュールや品質のリスクが増えがちです。
内製化を進めるほど、何でも社内でやりたくなりますが、あくまで業務として回る範囲を見極めることがポイントです。
内製化がうまくいかない理由のひとつは、「最初から全部内製でやろう」としてしまうことです。現実的には、社内のリソースには限りがあり、必要なスキルも段階的に育てる必要があります。
さらに、社内向けの動画と社外向けの動画では、求められる確認体制やリスク管理の重みも変わります。
おすすめは、内製と外注の役割を分ける考え方です。たとえば、日常的に量産・更新が必要な動画は内製に寄せ、企画の骨子づくりや表現設計が難しい動画は外部の力を借りる、という整理をすると運用が止まりにくくなります。
分けるときの判断軸としては、次のような観点が使えます。
大切なのは「どこまでを社内で持つと、業務が回り、成果につながるか」を先に決めることです。動画内製化のポイントは“編集担当者の頑張り”ではなく、“組織として無理がない設計”にあります。
動画内製化のポイントは、編集スキルよりも先に“設計”にあります。目的が曖昧なまま機材やソフトを揃えると、作った動画が使われず、担当者の負担だけが増えてしまいます。
さらに、関係部署が増えるほど「誰が主導するのか」「誰の業務をどう楽にするのか」がぼやけ、内製化のプロジェクトが“改善ではなく追加業務”として扱われてしまいがちです。
だからこそ、最初は派手な成果よりも、社内で合意を取りやすい整理から始めましょう。目的、体制、ルールという順に整えると、運用の土台が固まりやすくなります。
最初に決めたいのは、「なぜ動画を内製化するのか」です。目的が定まると、必要な動画の種類、求める品質、運用の頻度、関係者の範囲が自然に決まってきます。
ここで重要なのは、動画を“作ること”ではなく、動画で“業務をどう変えるか”に置くことです。
目的の例としては、研修の標準化、問い合わせ対応の効率化、営業活動の平準化、社内共有のスピード向上などが挙げられます。
さらに一段踏み込むなら、目的を「困りごと」に結びつけて言語化すると、社内の合意形成が進みやすくなります。
このような課題が明確になると、動画のテーマ選定もブレにくくなります。また、ゴールは「動画を何本作る」よりも、「誰が何をできるようになる」「何の工数が減る」など、業務成果に寄せる方が運用につながります。
たとえば、次のようなゴール設定は現場で使いやすいです。
目的とゴールが定まれば、動画内製化のポイントが「制作」から「運用」へ自然と移っていきます。
内製化が止まりやすい典型は、担当者1名に“全部”が集まる状態です。撮影、編集、確認、公開、社内周知、素材管理まで一人で抱えると、通常業務の繁忙期に途切れてしまいます。
内製化は、始めるよりも“続けること”の方が難しいため、最初に体制を設計しておくのが重要です。
小さく始める場合でも、最低限の役割は分けて設計しておくと安定します。
兼務でも構いませんが、「誰が最終的にOKを出すか」「更新の責任はどこか」を曖昧にしないことが、動画内製化のポイントです。
特に、マニュアルや研修は“正しさ”が重要なので、監修者の設定がないと現場が使いにくくなります。
また、制作担当者だけが頑張る形にしないために、次のような運用ルールも効きます。
体制づくりは立派な組織図を作ることではありません。小さな分担でもいいので、止まりやすいポイントを先に潰しておくことが大切です。
企業の動画は、情報管理やコンプライアンスの観点からも運用ルールが欠かせません。ルールがないと、公開範囲が曖昧になったり、古い情報のまま残り続けたりして、現場が困ります。
特に社内向け動画でも、部署をまたいで共有するようになると「どこまで見せて良いか」「どの情報が機微情報か」が話題になりやすくなります。
最初から厳密にしすぎると動きが止まるため、まずは“ゆるく”決めて、回しながら整えるのが現実的です。
ここで見落とされがちなのが「動画の寿命」です。制度、料金、仕様、手順など、変わりやすい情報を含む動画は、作った瞬間から“古くなる可能性”を抱えます。
動画内製化のポイントとして、次のような簡単なルールを持っておくと安心です。
この“回収ルール”がないと、動画が増えるほど整備コストが増え、内製化が負担になっていきます。ルールは制作のためではなく、使うためのものとして設計しましょう。
動画内製化の判断は、メリットだけでなく、デメリットとリスクも踏まえたうえで進めることが大切です。期待値を上げすぎず、現実的な運用イメージを持つことが、結果的に成功への近道になります。
特に企業では、短期の成果だけでなく、担当者の異動や体制変更が起きても続くかどうかが重要です。
内製化の代表的なメリットは、スピードと継続性です。外注の調整や待ち時間が減り、社内の事情に合わせて改善しやすくなります。
さらに、動画の活用が広がるほど「説明を動画に寄せる」という文化が根づき、業務の標準化が進みやすくなります。
特に、研修やマニュアルのように更新が前提の領域では、内製化の効果が出やすい傾向があります。
文章マニュアルだと読まれない、理解に差が出る、といった課題も、動画にすると改善するケースがあります。もちろん万能ではありませんが、「見れば一回でわかる」情報は、動画に向いています。
また、動画が増えることで、社内の共有スピードが上がりやすくなります。
口頭で伝える文化だと、伝達の漏れや解釈のブレが出やすいですが、動画が基準になると、説明が揃いやすくなります。これは、営業やカスタマー対応など“説明の品質”が成果に影響する業務で特に効きます。
一方で、内製化には乗り越えるべき壁もあります。ここを見落とすと、途中で頓挫しやすくなります。
特に「内製化=コスト削減」とだけ捉えてしまうと、必要な工数や教育の負担を見誤り、社内で反発が起きることがあります。
さらに企業では、次のようなリスクも意識しておくと安心です。
だからこそ、次章の「失敗しない動画内製化のポイント」を押さえ、運用として回る仕組みづくりに力を入れることが重要です。
動画内製化のポイントは、制作スキルの高さではなく「誰が作っても一定の品質で、必要なときに更新できる」状態を作ることです。
企業での内製化は、担当者の“作品づくり”ではなく、業務の“再現性”が価値になります。ここでは、運用を止めないための具体的な考え方を整理します。
内製化の初期は、プロのような完成度を狙うよりも、視聴者が迷わず理解できる“わかりやすさ”を優先するのがおすすめです。
標準化のコツは、細かな演出よりも、構成と見せ方を揃えることにあります。特にマニュアルや研修では「何を見ればいいか」が明確であるほど、視聴者のストレスが下がります。
この“型”があるだけで、担当者が変わっても運用が継続しやすくなります。
たとえば撮影条件は、必ずしも高価な機材を揃える必要はありません。むしろ「毎回同じ条件で撮れる」ことが重要です。社内の会議室の一角を撮影場所として決め、照明やマイクの置き方を固定すると、制作の準備時間が短くなります。
編集についても、最初は凝った演出よりも、視聴者の理解を助ける編集に絞るのが現実的です。
たとえば、不要な沈黙をカットする、手順の区切りで画面を切り替える、重要な言葉だけ強調する、といった基本だけでも十分に見やすくなります。
また、標準化を進める上で効果的なのが「チェックリスト」です。動画内製化のポイントとして、制作のたびに確認する項目を短く持っておくと品質が安定します。
この程度でも、属人化や品質のブレを抑えやすくなります。
動画が増えるほど重要になるのが、素材と完成データの管理です。探せない、最新版がわからない、同じ動画をまた作る、といった状況になると、内製化のメリットが薄れてしまいます。
動画は文章より容量が大きく、ファイルの受け渡しも煩雑になりやすい分、管理のルールがないと混乱しやすいのが実情です。
最低限、次の観点を揃えておくと運用が安定します。
分類については、社内の言葉に合わせるのがコツです。
たとえば「新人向け」「現場向け」「管理者向け」といった対象別の切り口は、探す側にとってわかりやすくなります。タイトルも「何をするときの動画か」が一目でわかるようにしておくと、視聴される確率が上がります。
さらに、運用が進むと「作った動画をどう浸透させるか」という課題も出てきます。動画は置いただけでは見られません。動画内製化のポイントとして、次のような浸透策を仕組みにしておくと効果が出やすくなります。
動画は“作った瞬間が完成”ではなく、業務や制度の変化に合わせて育てていく社内資産です。作って終わりにしないために、共有と更新の仕組みを最初から意識することが、動画内製化の大事なポイントになります。
動画内製化を継続するうえでよくある悩みが、「制作はできても、共有と運用が属人化する」「部署ごとにやり方がバラバラになる」「更新の管理が追いつかない」といった運用面のつまずきです。
特に、動画が増えてくると、ファイルの保管場所が散らばり、誰がどこまで見てよいかも曖昧になりやすくなります。
こうした課題に対しては、制作から共有までを一つの流れとして扱える環境があると、担当者の負担を減らしながら定着させやすくなります。
たとえばメディア博士を活用すれば、動画制作を社内完結で進めつつ、複数部署での活用や、用途別の整理・展開もしやすくなります。
内製化で大事なのは「制作ができる」だけでなく、「必要な人が迷わず見つけられる」「更新が必要なときに差し替えできる」「改善点が次の制作に活きる」という循環です。
動画内製化のポイントは、この循環が止まらないことにあります。
「まずは研修動画から」「次に業務マニュアルへ」「最後に営業支援へ」というように、段階的に内製化の範囲を広げたい企業にとって、運用を止めないための選択肢の一つになります。
社内の動画活用が広がるほど、制作担当者だけでなく、現場の協力や監修の仕組みも重要になります。ツール選びは“作る人”だけでなく“使う人”の視点でも考えると、定着しやすくなります。
Q. 内製化を始めるなら、最初の一本は何がおすすめですか?
更新頻度が高く、効果が見えやすいテーマがおすすめです。たとえば「新入社員が最初に迷いやすい業務手順」「問い合わせが多い手続き」「社内ツールの基本操作」などは、視聴者が明確で成果が出やすい傾向があります。
最初の一本で成功しやすいのは、撮影がシンプルで、関係者が少なく、監修の手戻りが少ないテーマです。
Q. 品質が不安で、社外公開の動画まで内製できるか迷っています。
最初から社外向けの重要動画を内製に寄せる必要はありません。まずは社内向けで型と運用を固め、社外向けは必要に応じて外注と組み合わせるなど、ハイブリッドで設計するほうが安全です。
社外向けは公開範囲が広い分、承認や確認の負担も増えます。内製化の範囲は、段階的に広げる方が失敗しにくいです。
Q. 担当者が忙しく、運用が止まりそうです。
体制と役割を分け、テンプレート化と素材管理を整えることで止まりにくくなります。特に「企画・監修・運用」を一人に集めないこと、更新ルールを“ゆるく”でも決めておくことがポイントです。
また、撮影や監修を現場が分担できるようにすると、制作担当者の負担が下がり、継続しやすくなります。
Q. どこまで標準化すると現場が受け入れやすいですか?
最初は細かいルールより、最低限の型を決めるのがおすすめです。
たとえば「冒頭で目的を言う」「手順は番号で区切る」「注意点は最後にまとめる」など、視聴者の理解を助けるルールに絞ると反発が出にくく、運用しながら改善できます。
動画内製化のポイントは、編集スキルの習得だけではなく、企業の業務として“回る仕組み”を作ることにあります。
まずは目的とゴールを言語化し、体制と役割分担、ルールと承認フローを整えたうえで、撮影・編集は最低限の標準化から始めるのが現実的です。
そのうえで、素材管理とナレッジ共有を仕組み化し、更新できる状態を作ると、動画は作り捨てではなく社内資産として積み上がっていきます。
内製と外注を使い分けながら、スモールスタートで成功パターンを作り、段階的に範囲を広げていきましょう。
動画内製化は、短期的な“制作コスト”だけで判断するとつまずきやすい一方、研修やマニュアル、営業支援など、継続的に情報を届ける業務に組み込めると、効果が出やすい取り組みです。
まずは「更新が必要で、使われる動画」から着手し、運用に乗せることを最優先に進めるのが成功の近道です。

株式会社博士.com
メディア事業・プロモーション業務管轄
サブマネージャー
博士.comに2017年に中途入社し、不動産会社のHP制作やSEOコンサルタントとして従事。
これまでに累計で80社以上のクライアントを担当し、幅広い支援実績を持つ。
その後、メディア事業部へ異動し、これまで培ったSEOやコンテンツ戦略の知見を活かしながら、動画活用のコンサルティングに携わっている。

株式会社博士.com
メディア事業・プロモーション業務管轄 サブマネージャー
博士.comに2017年に中途入社し、不動産会社のHP制作やSEOコンサルタントとして従事。
これまでに累計で80社以上のクライアントを担当し、幅広い支援実績を持つ。
その後、メディア事業部へ異動し、これまで培ったSEOやコンテンツ戦略の知見を活かしながら、動画活用のコンサルティングに携わっている。
動画制作・企画・撮影・編集・発信を総合サポート
企業の動画活用内製化支援ツール【メディア博士】
クラウド動画作成ツールのメディア博士ならブランディング動画・プロモーション動画・社内広報動画・広告動画などを簡単制作!
メディア博士での動画作成には、難しい操作や知識は必要ありません。初心者でも手間なく短時間で完成させることができAI機能や専属コンサルタントが動画作成をサポートします。
また、定額プランで月に何本作ってもOK!いつでも更新・アップロードができます。

1分でわかる【メディア博士】最新パンフレット

【企業担当者向け】社内の誰もができる!スマートフォンでの動画撮影テクニック

[飲食業界・外食チェーン向け]現場教育に効果的な動画マニュアル活用のポイント

動画構成の考え方と作り方!「伝わる」動画にするためのポイント

企業が取り入れたい動画活用スタートガイド

YouTubeマーケティング手法とVSEO(動画SEO)のポイント

動画のインハウス化の失敗事例から学ぶ 内製化成功のポイント

動画作成に役立つ!字コンテ作成用テンプレート&活用サンプル

スマートフォン動画撮影チェックシート【全31項目】

動画制作の費用を抑えるコツ!内訳別・種類別の費用相場

[消費者の動画視聴と購買行動から考える]企業の動画事業活用シーンまとめ

動画活用のコンサルティングサポートガイド

手振れなし!スマホを使った動画撮影の手引き|電動ジンバルの活用

すべてのタグ一覧
