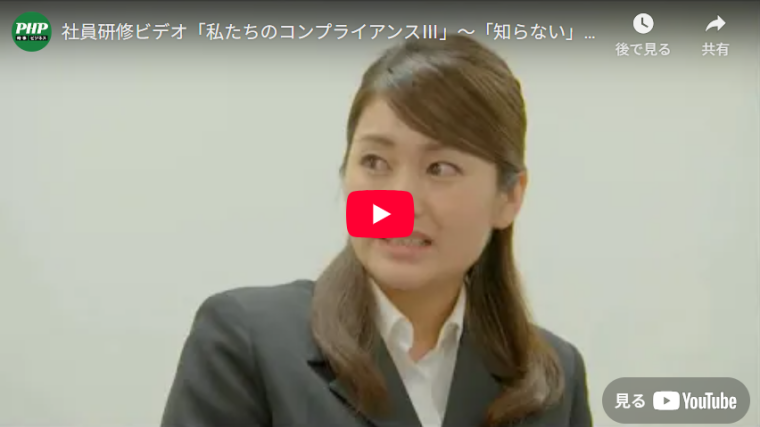インターネットやスマートフォンの普及により、動画に触れる機会は昔よりも多くなりました。デジタル化が進み、情報量が多くなっている今の社会において、動画の用途はますます増えています。
動画はビジネスのあらゆる面で活用できるというメリットがあるので、今回はその具体例を示していきます。今後動画を活用するための参考にしてください。
この記事は、こんな方におすすめです
- ✅ さまざまな業務で動画活用を検討しているが、何から始めれば良いか迷っている
- ✅ 社内外への説明や研修を効率化しながら、印象にも残る伝え方を模索している
- ✅ 動画の用途や活用事例を把握した上で、自社に最適な導入方法を知りたい
▶ メディア博士の資料を見てみる
動画を活用するメリット
インターネットやスマートフォンの普及により、誰もが手軽に動画を見る時代になった今、動画活用の有無が情報の伝わり方に大きな差を生み出しています。ここでは、動画を活用するメリットについて解説していきます。
短時間で情報を伝えられる
情報量が多い現代において、人々の可処分時間は限られており、短い時間で効率的に情報を得たいというニーズが強まっています。
動画は、テキストよりも圧倒的に多くの情報を短時間で伝えることができる媒体です。映像、音声、テロップ、動きといった複数の情報が一体となって構成されているため、例えば製品の使い方や会社紹介といった内容も、2〜3分の動画で直感的かつ網羅的に伝えることが可能です。
これは営業やプレゼンの場面でも有効で、相手の関心を引きつけたまま必要な要素をしっかり届けることができます。
ユーザーに見てもらいやすい
動画は「受動的なコンテンツ」として、ユーザーがストレスなく情報にアクセスできる点が強みです。テキストは読みに行く必要がありますが、動画は再生ボタンを押すだけで内容が進みます。
特にSNSやYouTubeでは、興味の有無に関わらず自動再生されることも多く、自然と視聴に引き込まれる設計がされています。
この「気軽に見られる」という特性が、コンテンツとしての到達率や理解促進に大きく寄与しています。また、動画ならではのリズムや音声によって、視聴者の注意を持続させやすく、最後まで見てもらえる確率も高まります。
視聴者の感情に訴えかけやすい
感情に訴える力という点でも、動画は他のメディアを大きく上回ります。表情、声のトーン、音楽、映像の流れなど、複数の要素が合わさることで、感動や共感といった情緒的な体験を視聴者に提供できます。
企業の理念や想い、社会貢献活動の紹介なども、文章で読むより動画で視聴したほうが説得力があり、人の心に響きやすくなります。
ブランディングの場面では特に、消費者とのつながりを深め、信頼感を構築するうえで動画の存在が大きな意味を持ちます。
SNSやWeb上で拡散されやすい
近年のWebマーケティングでは、SNSでの拡散力がブランドの知名度や信頼感を高める上で重要な指標になっています。
動画コンテンツはその特性上、SNSユーザーの目を引きやすく、感情を動かしたり驚きを与えたりする構成ができれば自然と拡散されていきます。
ハッシュタグやサムネイルの工夫によって再生数を伸ばしやすく、場合によっては広告費をかけずに何万、何十万という人にリーチすることも可能です。従来の文字ベースのコンテンツよりもSNS上での受け入れられ方に優れているのが動画の特長です。
動画の主な活用用途
商品・サービス紹介

自社の商品やサービスの価値を魅力的に伝えたい時に効果的です。
自社のサービスサイトでは十分に魅力を伝えきれなくても、情報伝達力が高い動画であれば世界観や魅力を正しく伝えやすくなります。機能が複雑な商品でも利用シーンがイメージしやすいので、購買意欲を上げられます。飲食や保険など形のないサービスであれば、
アニメーションやナレーションで視覚的に簡単に理解できるでしょう。
ブランディング
商品やサービスは、機能や価格だけでなく
ブランドへの信頼感も、購入時の重要な要素になります。
消費者とブランドのつながりを強くできれば、お客様の購買活動を大いに刺激できます。信頼感を得るために、企業はブランドの理念や世界観を消費者に伝えなければいけませんが、テキストのみだと細かいニュアンスは伝わりにくいものです。動画を使えば、映像と音を使うため、直感的に視聴者に情報が伝わります。
関連リンク:ブランディング動画でブランド力アップ!動画活用の効果と事例をご紹介
プロモーション
購買意欲を刺激するためにプロモーションは必須です。インターネット上には企業の広告が溢れており、Webページを開けば至るところに広告があるはずです。
数ある広告に埋もれないためにも、お客様に届くように目を引く動画広告を打ち出す必要があります。動画だと目と耳で情報を受け取るので記憶に残りやすくなるので、認知度アップという点でも優れています。
プレゼン動画

資料を用意して読んでもらうよりも、動画を視聴してもらう方が理解しやすいです。商品やサービスによっては、テキストだけでは特徴や魅力が伝わりづらいものがあります。
動画を用いて説明すれば、資料に掲載するサービスや商品などを視覚的に表現することができるので、見る人の理解度を上げられます。
インターネット上での再利用も可能なので、企業内のプレゼンだけでなく、自社サイトにアップして多くの視聴者にみてもらうという活用法もあります。
関連リンク:営業ツールとしての動画活用法5選!メリットや企業事例、制作時のポイントもご紹介
アプリ紹介

アプリストアでアプリの紹介をするときに、テキストや画像のみだと実際アプリを使用した時のイメージがつきにくいでしょう。アプリの持つ雰囲気やイメージ・特徴などを動画で説明することで、サービスの魅力を最大限に伝えられます。
動画を通してユーザーがアプリの疑似体験をできるので、雰囲気や使い方を確認しやすいです。
アプリのイメージが具体化できれば、ダウンロード数も伸びますし、
SNSで拡散される可能性もあります。アプリの世界観も表現できるので、ターゲットのユーザーに刺さりやすいです。
教育研修
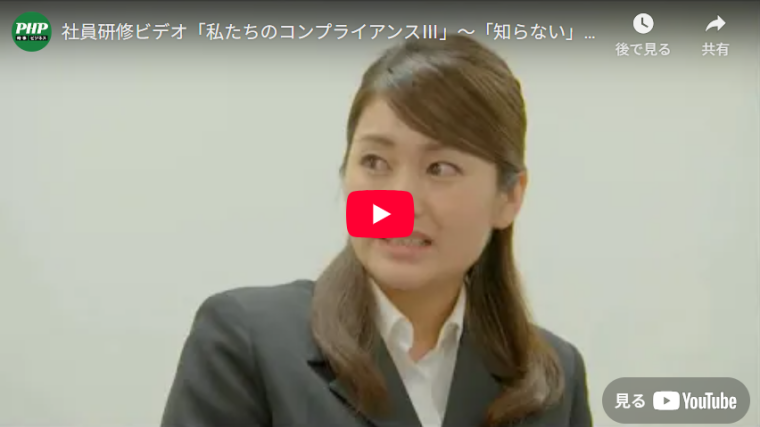
文章に比べて視覚効果が高い動画は、記憶に残りやすいので教材として優良です。テキストのみの教材だと、業務内容を理解するのが難しい上に単調な教材ゆえに文字を追うだけになってしまい、学習意欲が低下してしまいがちです。
動画であれば、音と映像で学べて単調になりにくいので、学習に対する姿勢を維持しつつ効率的に学べます。業務の言語化しにくい部分も、動画なら短時間で直感的に伝えられます。
関連リンク:社員研修に動画を取り入れるメリットと作る上でのポイント
セミナー動画
セミナーを動画で行えば、会場がいらないためコストがかかりません。そのため、集客できなかった時の赤字のリスクを無くせます。
会場までの移動がなく、距離的な問題を抱えている人も参加できるので、オフラインのセミナーより参加者を集めやすいです。セミナーは本来1回限りで終わるものですが、動画であれば再利用ができるので、何回でも繰り返し使えます。
採用案内
動画ならリアルな会社の雰囲気を伝えられるのが強みです。普段の業務を口頭で説明しても、なかなか求職者には伝わりづらいものです。
動画では、言語化しづらい業務内容や会社の雰囲気などの情報も伝えることができます。どんな仕事かを把握しやすいため、企業と応募者のミスマッチを未然に防ぎやすくなります。
関連リンク:新卒採用で動画を活用すべき理由と事例【新卒採用担当者は必見】 関連リンク:中途採用でも動画を活用しよう!活用する上でのポイントと事例を紹介
会社紹介
動画で会社紹介を行えば、企業のビジョンや事業内容を具体的にイメージできます。消費者から信頼を獲得し、サービスを魅力的だと感じてもらうには、会社をよく知ってもらわなければならなりません。
ビジョンを認知してもらうために、情報伝達能力が高い動画は最適です。外部からなかなか把握しづらい、事業内容などの情報も伝えることができます。
関連リンク:会社案内の動画は効果的!?会社案内動画を作成するメリット
広報

企業などの広報活動に活用できます。消費者に企業や商品に対する関心を持ってもらい、認知を拡大することを目的としています。
広報において、企業や商品・サービスのストーリー性が重視されます。コンテンツに関してストーリーがあれば、視聴者の共感を得ることができるので、顧客となってもらいやすいです。画像や文章だけでも伝えられますが、動画であれば音と映像を駆使し、より効果的にストーリーを伝えられます。
How to動画・マニュアル

マニュアルを動画で作成すれば、テキストや写真のみの場合よりも手順をおさらいしやすくなります。商品やサービスの利用法が知りたければ、動画であれば実際に使用している様を見れるので、利用の際のお手本にしやすいです。
接客マニュアルなども動画で説明することで、お客様と接する際の微妙な接客のニュアンスを伝えられます。動画なので、スマホなどのデバイスがあればいつでもどこでも何度でも学べます。
動画を活用する際のポイント
動画の魅力は確かに大きいものの、その特性を理解して適切な形で制作・配信しなければ、本来の効果を引き出すことはできません。ここでは、動画を活用する際のポイントについて紹介していきます。
目的と視聴者を明確にする
動画を制作する際、最初に意識すべきは「何のために作るのか」「誰に向けて作るのか」という点です。目的が曖昧なまま動画を作ると、構成や表現が散漫になり、視聴者の心に届きません。
例えば、新製品の紹介動画であれば、商品特性の紹介だけでなく、想定される利用シーンや課題解決のイメージを明確に伝える必要があります。
採用動画であれば、求職者が気になる社風や働き方を前面に出すことが大切です。目的と視聴者を定めることで、動画の長さやトーン、ナレーションの有無、編集の方向性なども自然と定まってきます。
冒頭10秒で視聴者の関心を引く
動画は途中で離脱される可能性が高いメディアです。特にSNSやWeb広告においては、最初の数秒で興味を持たれなければ、最後まで見てもらえることはほとんどありません。そのため、冒頭の演出は非常に重要です。
インパクトのある映像や問いかけ、結論を先に提示するなど、「見続ける理由」を明示する工夫が必要です。
例えば、「たった1分でわかる○○の使い方」「初公開!開発者が語る製品の裏話」といった導入は、視聴者の好奇心を刺激しやすくなります。どれほど丁寧に作り込まれた内容でも、最初に関心を惹けなければ成果には結びつきません。
視認性・聴きやすさに配慮する
ビジネス動画においては、伝えたい内容が明確に「届く」ことが前提となります。そのためには、映像と音声の見やすさ・聞きやすさに細かく気を配る必要があります。
映像が暗すぎたり、背景と文字の色が被って見づらかったりすると、情報が伝わりにくくなります。テロップや図解を用いる場合は、フォントサイズや色のコントラストにも注意を払いましょう。
また、音声もクリアであることが重要です。話し手の声が聞き取りにくい、BGMが大きすぎて内容がわからないといったトラブルは避けるべきです。視聴環境はスマートフォンやイヤホンなど多様化しているため、事前のテスト視聴も有効です。
再利用しやすい構成で作る
動画は「作って終わり」ではなく、「どのように再活用できるか」がポイントになります。
セミナーやイベントの記録動画であれば、ダイジェスト版や個別トピックごとの分割コンテンツに編集することで、さまざまな場面で使い回すことが可能になります。
マニュアル動画を徹底解説!メリットや作成のコツ、参考事例もご紹介 【需要急上昇中】ハウツー(HOWTO)動画の作り方を詳しく解説
まとめ
今回は企業の動画の活用用途について紹介しました。
動画はビジネスの様々なシーンで活用できます。場面に応じて目的に沿った動画を作成できれば、ターゲットに効果的に届けられます。動画には色々な用途があるので、自社の目的に合った動画を作成してみてください。